
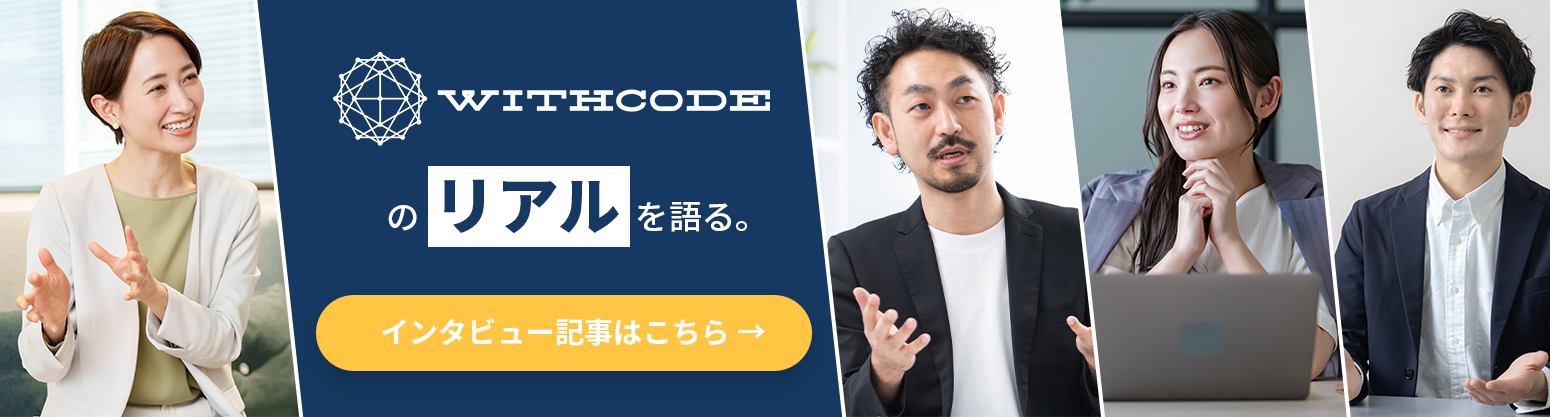
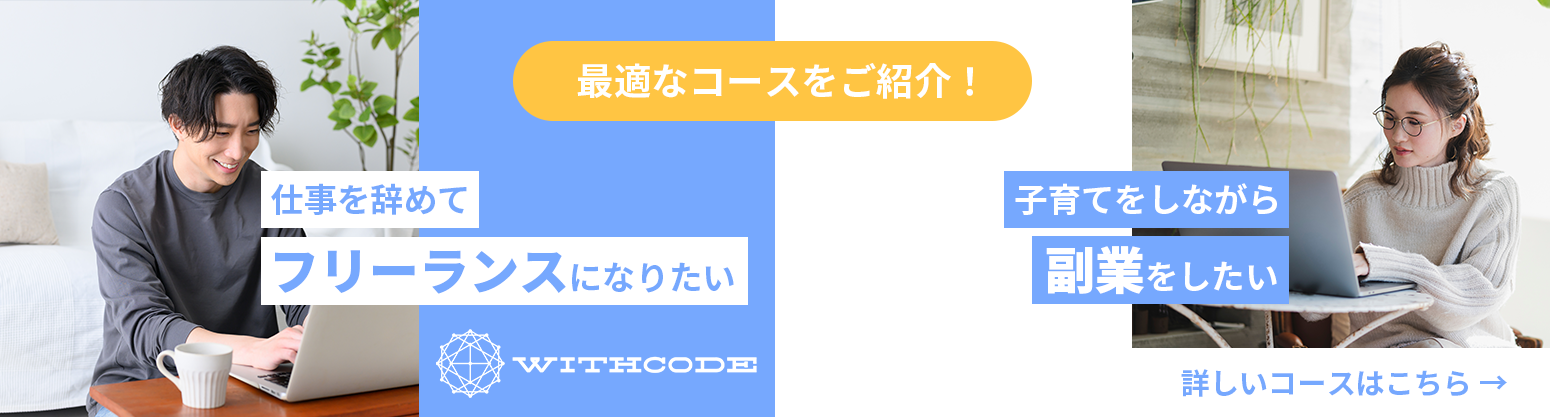
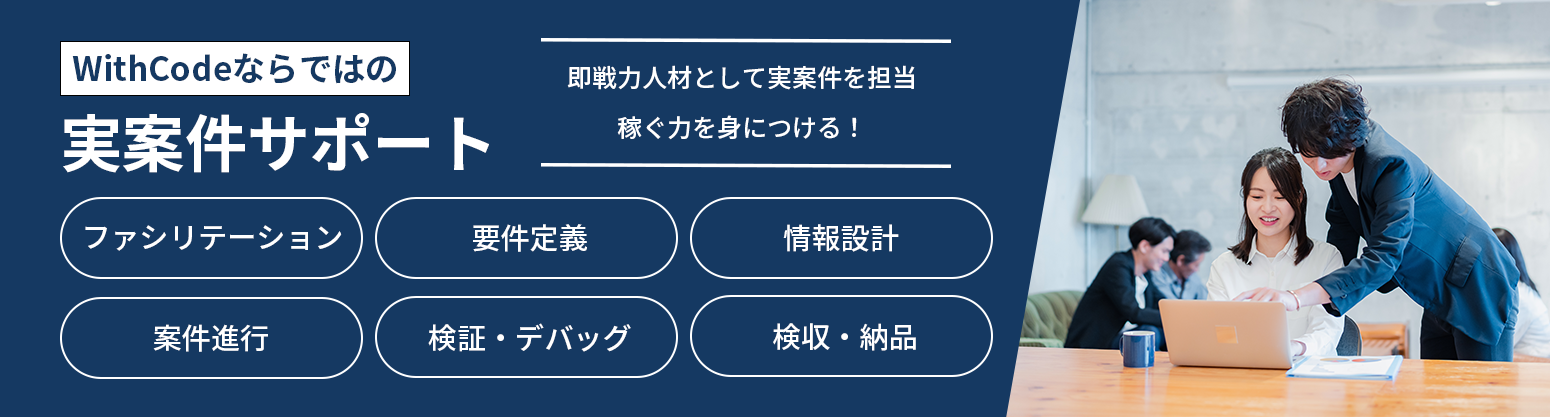
WithCodeMedia-1-pc
WithCodeMedia-2-pc
WithCodeMedia-3-pc
WithCodeMedia-4-pc



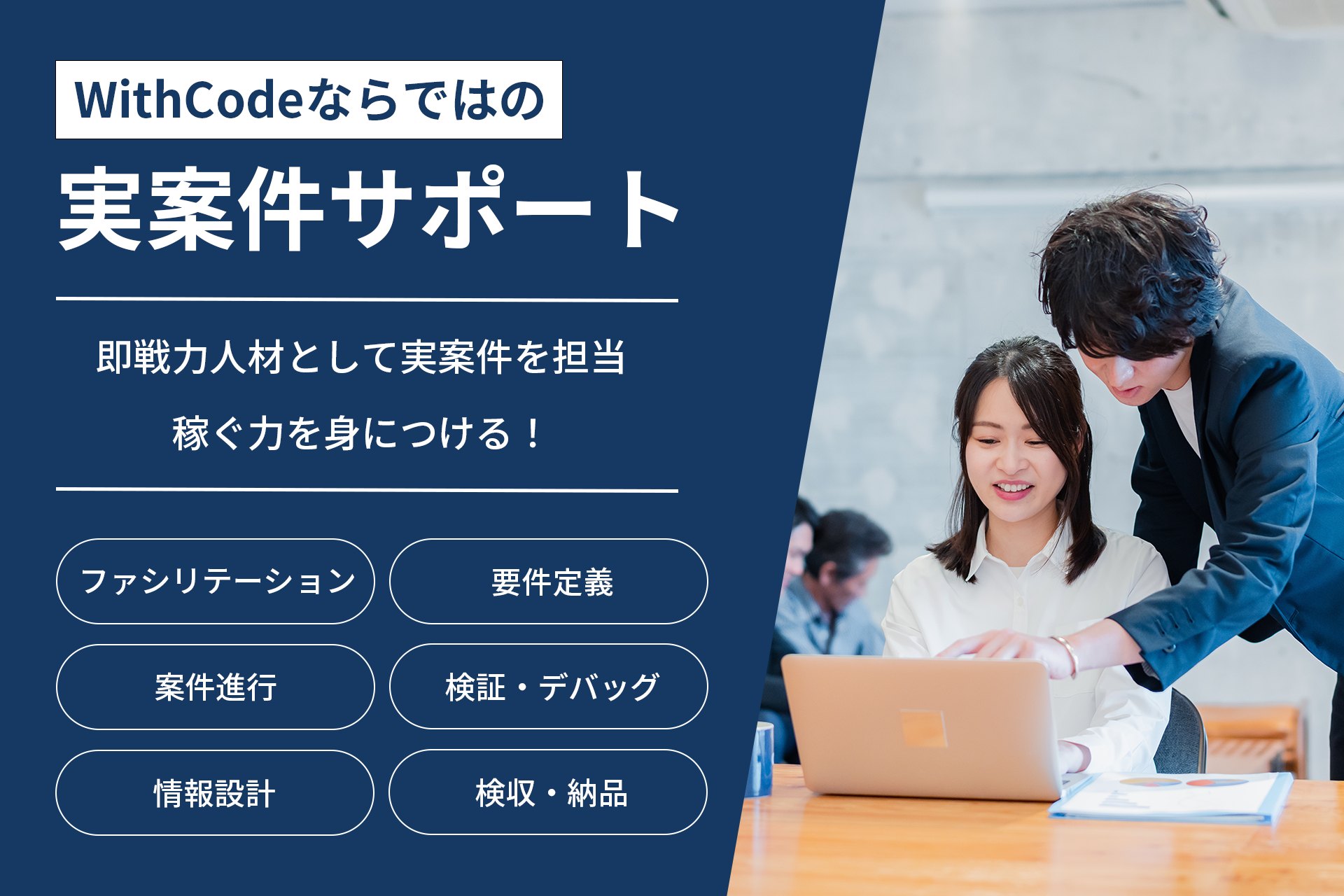
WithCodeMedia-1-sp
WithCodeMedia-2-sp
WithCodeMedia-3-sp
WithCodeMedia-4-sp

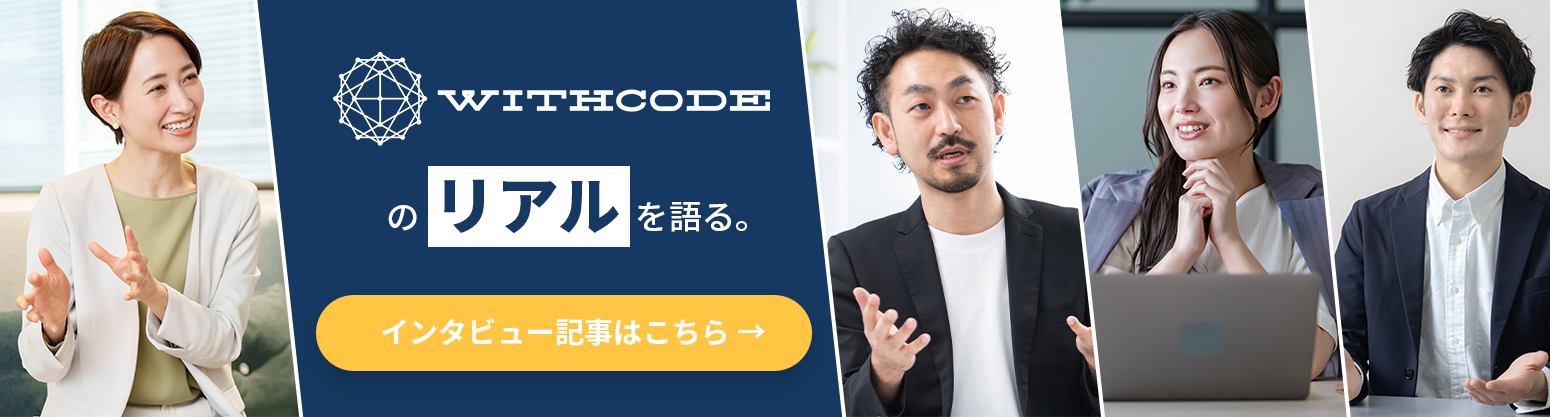
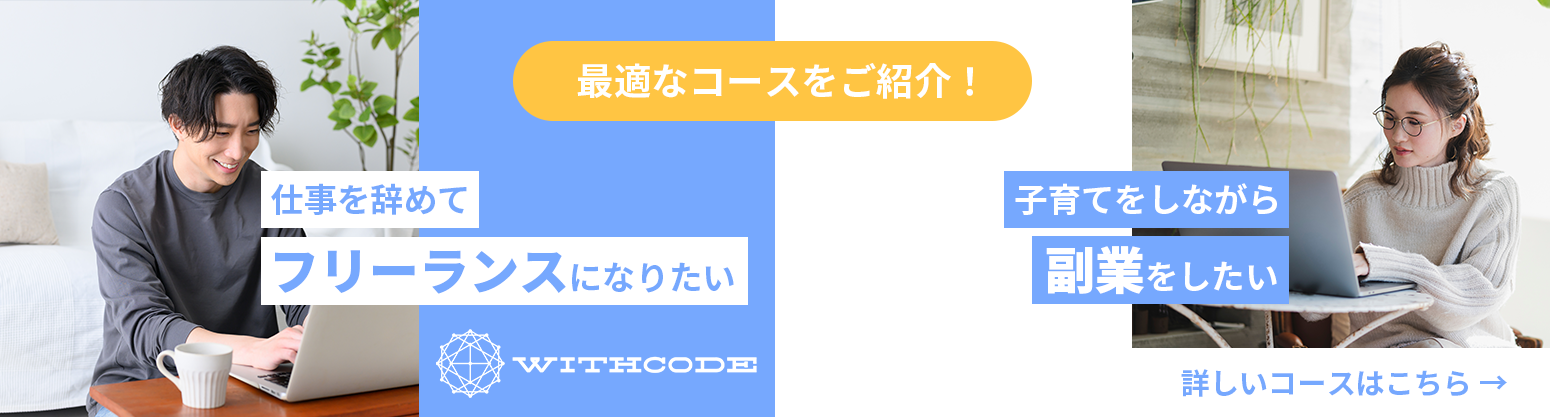
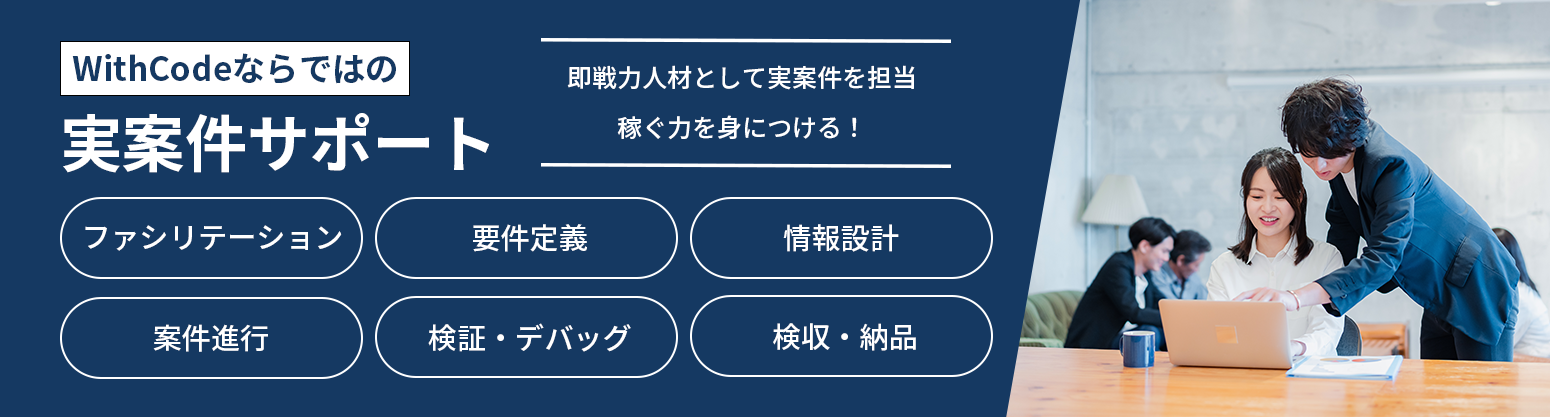



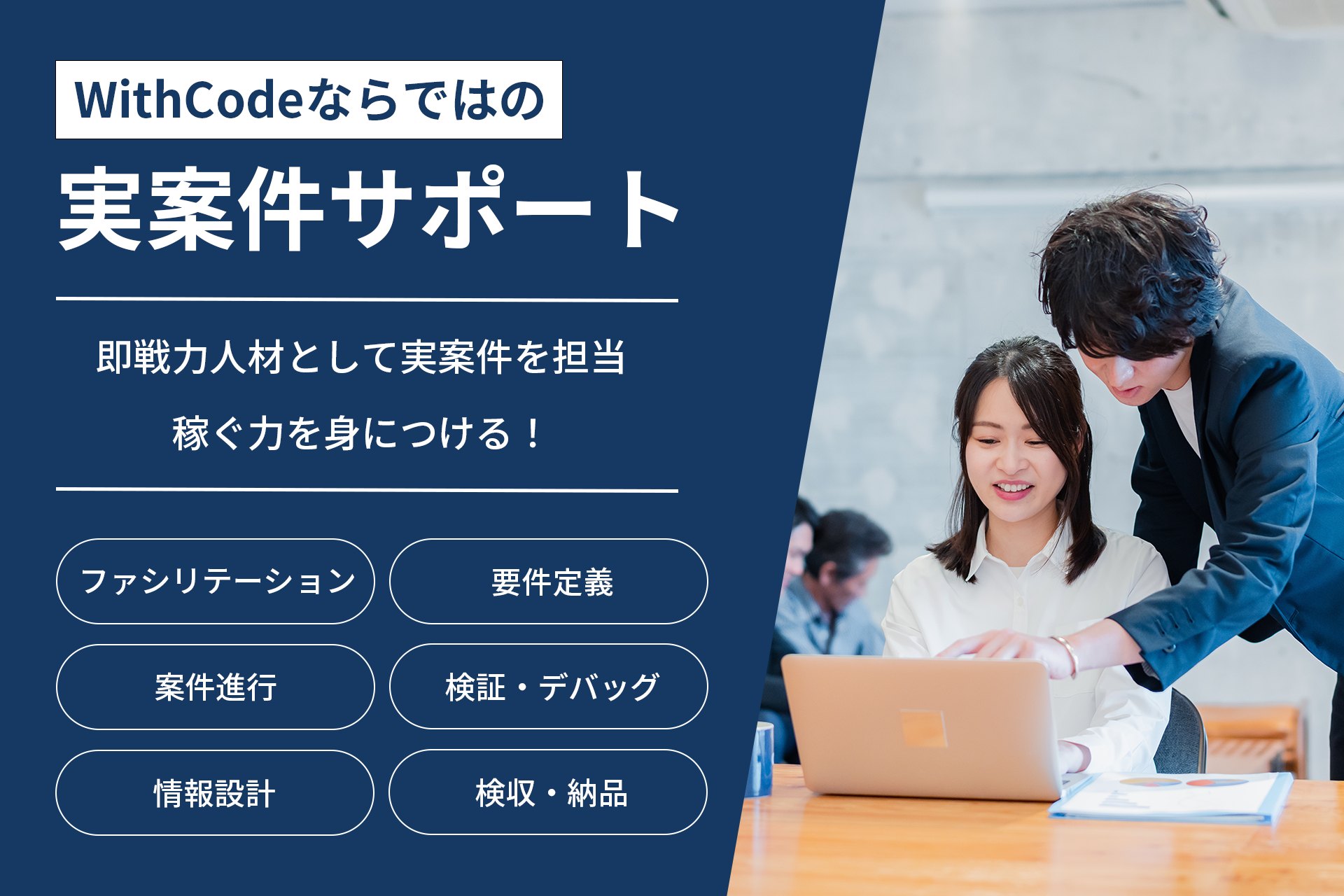

「自社のWebサイト、なんかダサい気がする」
「同業他社と比べて見劣りしていないか不安」
そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問や悩みを抱えている方に向けて以下のポイントを解説します。
本記事を読めば、デザインに自信が持てない方でも「何をどう直せばいいか」が明確になり、「ダサい」と言われないWebサイトを作れるようになるでしょう。
閲覧者がWebサイトを見て「ダサい」と判断するのは、感覚的な印象による場合が少なくありません。しかしその印象は、具体的な要素の積み重ねで形成されています。
例えば、彩度やトーンがバラバラで読み手が疲れてしまう・文字サイズやフォントが不揃いで読みにくい、レイアウトが崩れていて見づらいなど視覚的な不快感があると直感的に「ダサい」と受け取られやすくなります。また、情報が整理されていない構成や操作しづらいUIも、古さや雑さの印象を与える原因になるでしょう。
特に中小企業のWebサイトでは、自作や低予算で制作されたページが多く、統一感に欠けるデザインや無料素材の多用によってプロのサイトとの差が目立ちやすくなります。サイト全体に一貫性がなく、ブランドや目的が見えてこない場合、ユーザーからの信頼も得られにくくなります。
Webサイトのデザインは2〜3年で時代遅れになります。リニューアルの目安として、公開から3年以上経過していて、以下のような状態が見られる場合は見直しの検討が必要です。
なによりモバイル対応が不十分なサイトは、ユーザーの離脱率が高く、検索順位にも悪影響が出やすくなります。加えて、競合他社のサイトが洗練されている場合、自社サイトだけが取り残されているように見えるため信頼性や第一印象にも影響するでしょう。
ユーザーは複数のサイトを比較しながら閲覧しており、無意識に「どこが見やすいか」「どこが信頼できそうか」を判断しています。競合サイトと比べて、自社のサイトに違和感がある場合、以下の点が見劣りしている可能性があります。
また、競合がプロのデザイナーを起用している場合、自社サイトとのクオリティ差がさらに際立ちます。見た目の印象だけでなく操作性や導線のわかりやすさも含めて、総合的なユーザー体験で負けてしまうと、問い合わせや資料請求といったアクションにつながりにくくなってしまうでしょう。
以下は、自社サイトと競合サイトを比較するためのチェックリストです。
| 評価項目 | 自社サイト | 競合サイトA | 競合サイトB |
| 配色の統一感 | △ | 〇 | 〇 |
| フォントの読みやすさ | ✕ | 〇 | 〇 |
| スマートフォンでの見やすさ | ✕ | 〇 | △ |
| ナビゲーションの分かりやすさ | △ | 〇 | 〇 |
| 写真・画像のクオリティ | ✕ | 〇 | 〇 |
| サービス内容の伝わりやすさ | △ | 〇 | 〇 |
項目ごとに分解して客観的に比較すると、どの部分が改善の優先ポイントかが明確になります。数値化できない印象の差も、視覚的な品質や設計で十分に埋められるのです。
日本のWebサイトは、見た目の美しさよりも情報量の多さを優先する傾向があります。背景には、細かく丁寧に説明する文化やユーザーが事前にあらゆる情報を把握してから行動を決めたいという消費者心理があります。
企業のサイトでは特に、文字数の多い説明や詳細なスペック・PDF資料の添付など、「網羅性」を重視するレイアウトが多く見られるでしょう。
加えて、日本のインターネット黎明期に普及したホームページビルダーや汎用CMSの影響で、装飾や情報の詰め込みが「普通」として定着した面もあります。視覚より情報整理に時間をかけるデザイン方針は、紙文化との親和性も高く、パンフレットやカタログをそのままWebに落とし込んだような構成が生まれやすくなっています。
こうした傾向は、視覚的にすっきり見せる海外のWebサイトとは大きく異なり、情報過多に見える要因となるでしょう。
Webデザインの評価は、見る人によって変わります。日本では年齢層が高めのユーザーを想定した設計が多く、なにより中小企業では50代以上をターゲットにするケースも珍しくありません。そのため、見慣れたボタンの形や明確な説明文を重視するレイアウトが好まれ、シンプルなデザインはかえって不安や分かりにくさを与える場合があります。
一方で、海外のWebサイトは若年層やITリテラシーが高い層を中心に設計されている場合が多く、無駄を削ぎ落としたインターフェースや、写真や動画で直感的に魅力を伝える構成が多く採用されています。この違いが、「ダサい」「時代遅れ」といった印象を生む一因となっているでしょう。
つまり、どちらが優れているかではなく、想定しているユーザーのニーズが異なっているため、デザインの正解にも違いが生まれているのです。
日本のWebデザインには、視覚的な華やかさでは見劣りしても、細やかな情報設計や導線のわかりやすさなど機能性に優れた点があります。
例えば、サービス内容を複数のセクションに分けて整理したり、ページ上部と下部の両方に問い合わせボタンを配置するなどユーザーが迷わず行動できるよう工夫されているケースも少なくありません。
また、業種や目的に応じて必要な情報をきちんと揃える慎重さも、日本ならではの信頼感につながります。視覚的には地味でも、比較検討に役立つ情報が揃っていれば、ユーザーの納得感や意思決定のしやすさを後押しできます。
海外のデザインをそのまま真似するのではなく、自社の目的やターゲットに合った設計ができていれば、必ずしも「ダサい」とは限りません。見た目より機能や情報を重視する設計もまた、ひとつの強みです。
配色やフォントが統一されていないWebサイトは、視覚的な違和感を生みやすく、信頼性にも影響します。
例えば、赤・青・緑といった原色を複数使っている場合、全体が騒がしく見え、情報が頭に入ってこなくなります。また、本文に明朝体・見出しにゴシック・ボタンに手書き風フォントを使用するなど書体の種類やウエイトが混在していると、読みにくさが増すだけでなく方向性も伝わりません。
色やフォントは視覚的な印象を決定づける要素です。ブランドカラーが定まっていない・使用ルールが存在しない場合、印象は場当たり的になりがちです。ユーザーに不安を与えず、安心感を与えるためには、配色と書体に一貫性を持たせましょう。
まず3色以内の基本色を決め、見出しと本文に使うフォントを固定するだけでも印象は大きく変わります。
情報量が多すぎるWebサイトは、かえって内容が伝わらなくなります。文字数が多く、改行が少ないページは読む気力を削り、レイアウトに秩序がないと「どこから見ればいいか分からない」状態に陥ります。特にトップページに複数の見出しやバナー・説明文やボタンが並ぶ構成はユーザーの集中力を奪ってしまうでしょう。
以下のような状態があれば、情報過多の可能性が高いです。
ユーザーは「全部読みたい」とは思っていません。必要な情報に素早くアクセスできる構成であれば、内容の理解も促進され、ストレスなく行動に移せます。
画像やイラストの品質は、サイトの信頼性に直結します。フリー素材の写真を多用したページや低解像度の画像をそのまま掲載した構成は、すぐに「作りが甘い」「お金をかけていない」といった印象を与えます。安さや雑さが滲み出たデザインでは、ユーザーの興味も持続しません。
以下のような素材が目立つ場合は改善が必要です。
ビジュアルは雰囲気づくりだけでなく、サービスや企業の信頼度を伝える役割も持ちます。色味を揃える、撮影クオリティを見直すといった細かな配慮で、全体の印象を大きく改善できるでしょう。
レイアウトの乱れは、見た目の問題にとどまらず、内容の理解や操作にも悪影響を及ぼします。余白が足りない・配置がずれている・整列されていない場合、視線の流れが阻害されて読みにくくなります。読む側に負荷を与えるページは、どれだけ内容が良くても読まれません。
以下のような見た目になっているなら、レイアウトに問題があります。
Webサイトの印象は整った構造で決まります。余白を確保し、配置ルールを統一するだけで印象がガラリと変わります。整った構造にすれば、Webサイトの読みやすさと信頼性の両方を高められるでしょう。
スマートフォンでの表示最適化が不十分なWebサイトは、ユーザーに不便を与えます。文字が極端に小さい・画面が左右にスクロールする・ボタンが指で押しづらいなど、基本的な操作に支障が出る状態では、すぐに離脱につながります。
特に次のような要素に問題がある場合は改善が必要です。
スマートフォンでの利用を前提に設計し直すことで、操作の快適さと見やすさが向上します。今は多くのユーザーがスマホからアクセスしているため、モバイル最適化は最優先で取り組むべきでしょう。
テンプレートを使って構築されたWebサイトでも、うまく調整されていれば古臭く見えることはありません。しかし、何年も前の無料テーマをそのまま使用している場合や、初期デザインに一切手を加えていない構成では、どうしても時代遅れに見えてしまいます。
次のような特徴が見られる場合はテンプレート依存が強い状態です。
テンプレートを使うこと自体は問題ではありません。大切なのは、見せ方を目的やブランドに合わせて調整できているかどうかです。

デザインの印象は、色と書体の選び方で大きく左右されます。視覚的な統一感がないと、全体が散らかって見え、信頼性も損なわれます。ブランドイメージに合わない配色や安定感のないフォントの組み合わせは、どれだけ内容が良くても「ダサい」と思われる原因になるでしょう。
まずは、軸となるベースカラー1色と、アクセントカラー2色までに絞り、サイト全体に共通して使います。フォントも同様に、用途別にルールを決めると整って見えます。
例えば、見出しにはゴシック体・本文には読みやすい明朝体というように役割ごとに書体を分けると視認性が高まり、ページの印象も引き締まります。
Webデザインは色と文字で雰囲気をつくる面が強いため、配色とフォント設計を見直すだけで印象を変えられるでしょう。
配色に関して詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
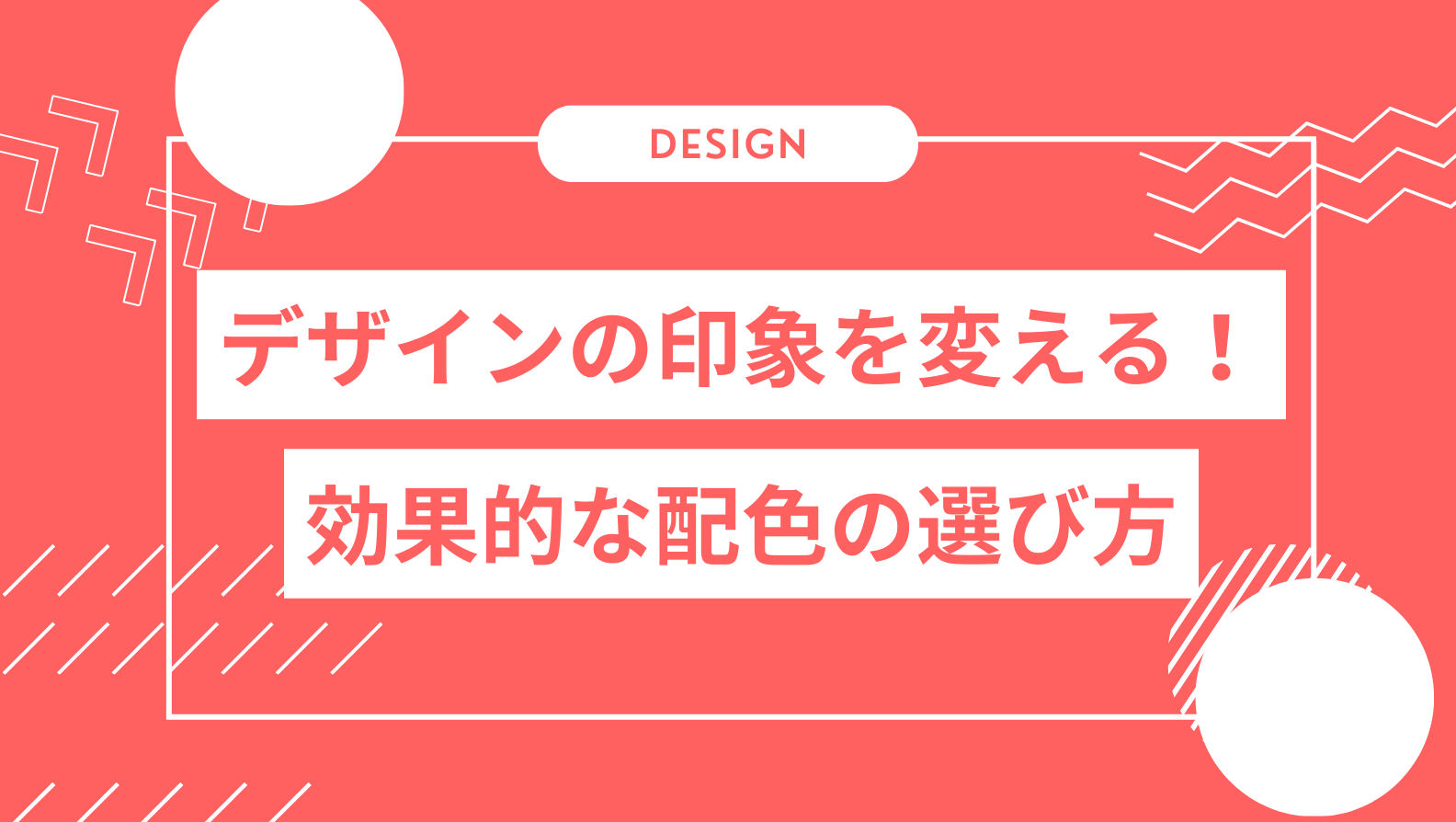
写真やイラストの品質は、Webサイト全体の印象を大きく左右します。特に、無料素材を使い回した画像は見覚えのあるものが多く、安っぽく感じられてしまうでしょう。
よくあるのが、ビジネススーツの笑顔の男女やデスクワーク風景など、どこかで見たような写真の多用です。視覚の印象は一瞬で判断されるため、ありきたりな画像ばかり使っていると、内容よりも見た目で損をします。
見直すべきポイントは以下の通りです。
可能であれば、オリジナルの撮影素材や統一感のある有料素材を選びましょう。色やスタイルを合わせるだけでも、サイト全体の質感が良くなります。
Webサイトに情報を詰め込みすぎると、伝えたい内容がぼやけてしまいます。なにより中小企業のサイトでは、「全部載せておかないと不安」という理由で、ユーザーが必要とする情報以上の内容を並べがちです。結果として、ユーザーは何を読めばいいのか分からず、離脱につながってしまうでしょう。
情報整理のためには、まず優先順位を明確にし、1ページあたりの目的を絞り込む必要があります。
以下のような点をチェックすると、削るべき要素が見えてきます。
すべてを見せるのではなく、「誰に、何を伝えるか」を絞れば、情報の密度が上がり読みやすさも向上します。
ごちゃついた印象のWebサイトには、共通して「余白が足りない」「要素が詰まりすぎている」という問題があります。要素を詰め込むほど情報量は増えますが、逆に読みづらくなり、ユーザーの集中力を奪ってしまうでしょう。余白は「スペースの無駄」ではなく、情報を引き立たせるための大切な要素です。
まずは、各セクションの間隔や行間を意識的に広めにとりましょう。文字と画像の間に十分なスペースがあるだけで、視線の流れがスムーズになり、読みやすさが格段に向上します。
さらに、要素の配置も整えることで、バランスの取れた構成になります。中央揃え・左寄せ・グリッドレイアウトなど、どれを採用するかを明確にし、一貫して使い分けると見た目にも安定感が生まれるでしょう。
余白に関して詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

スマートフォンでの閲覧が主流になっている今、モバイルでの表示と操作性が整っていないサイトは、どれだけ内容が優れていても高確率で離脱されます。横スクロールが必要だったりリンクやボタンが小さく押しづらかったりすると、ストレスを感じる要因になり、次のページに読み進まれません。
改善のためには、スマートフォンの画面サイズに合わせてレイアウトを再設計する必要があります。特に、1カラム構成への最適化・行間やフォントサイズの調整・タップしやすいボタン配置が大切です。
加えて、UIの見直しも欠かせません。目的の情報にたどり着きやすいナビゲーションや無駄な動きを省いた設計は、操作の快適さを大きく向上させます。あわせて、画面サイズに応じて自動的にレイアウトを調整する「レスポンシブ対応」も、モバイル最適化においては大切です。
モバイル対応の精度が高いほど、離脱を防げる可能性が高まるでしょう。
レスポンシブデザインに関して詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
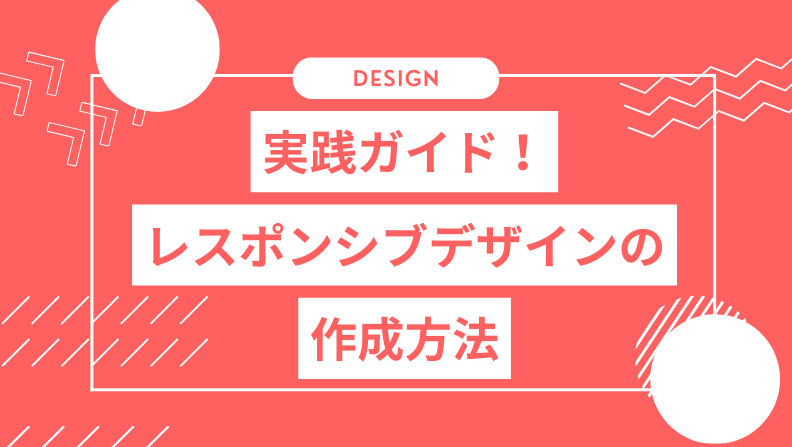
本記事では、「Webデザインがダサい」と感じられる原因や典型的なNG例、自社サイトを洗練された印象に変えるための改善方法を解説しました。
Webデザインの印象は、配色・フォント・レイアウト・情報整理・スマホでの見やすさといった細部の積み重ねで決まります。誰に何を伝えるかを明確にし、それに沿った設計が大切です。
以下が本記事の要点です。
本記事を参考に小さな見直しから始めて、ユーザーが読みやすいWebサイトを目指しましょう。

副業・フリーランスが主流になっている今こそ、自らのスキルで稼げる人材を目指してみませんか?
未経験でも心配することありません。初級コースを受講される方の大多数はプログラミング未経験です。まずは無料カウンセリングで、悩みや不安をお聞かせください!
↓
公式サイト より
今すぐ
無料カウンセリング
を予約!