
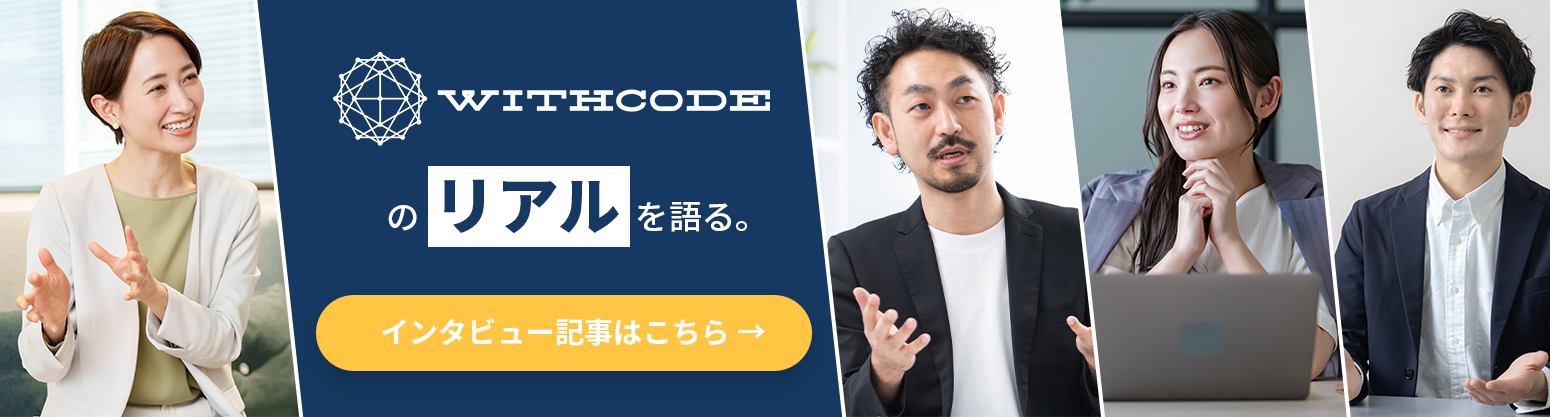
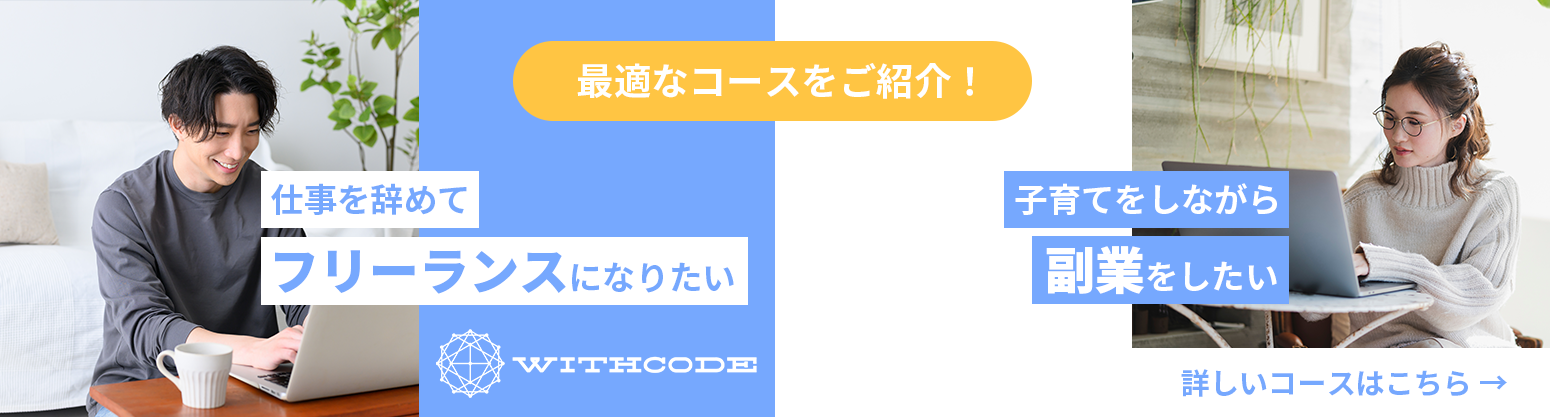
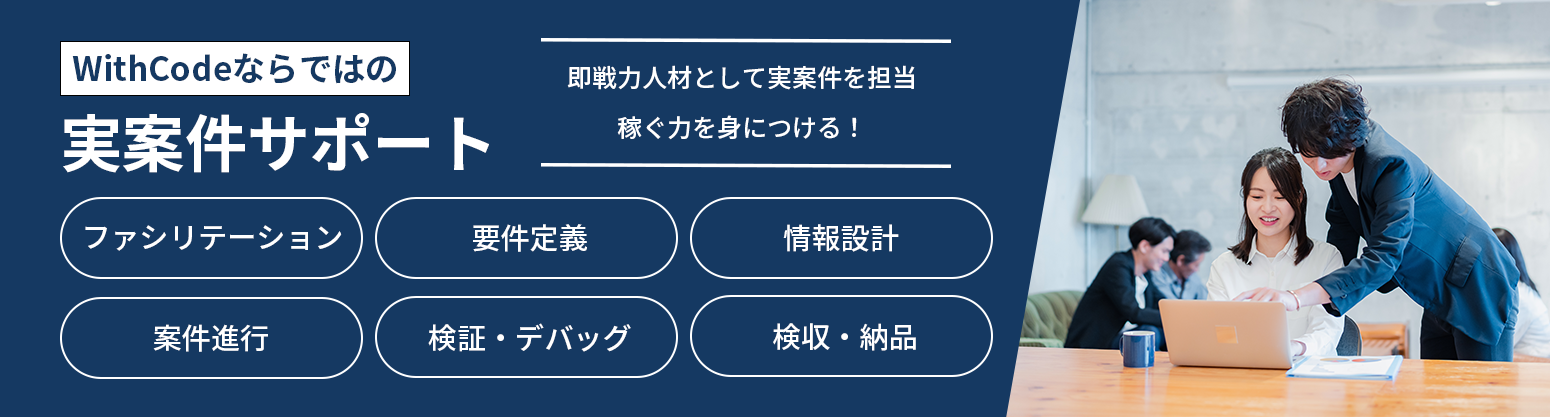
WithCodeMedia-1-pc
WithCodeMedia-2-pc
WithCodeMedia-3-pc
WithCodeMedia-4-pc



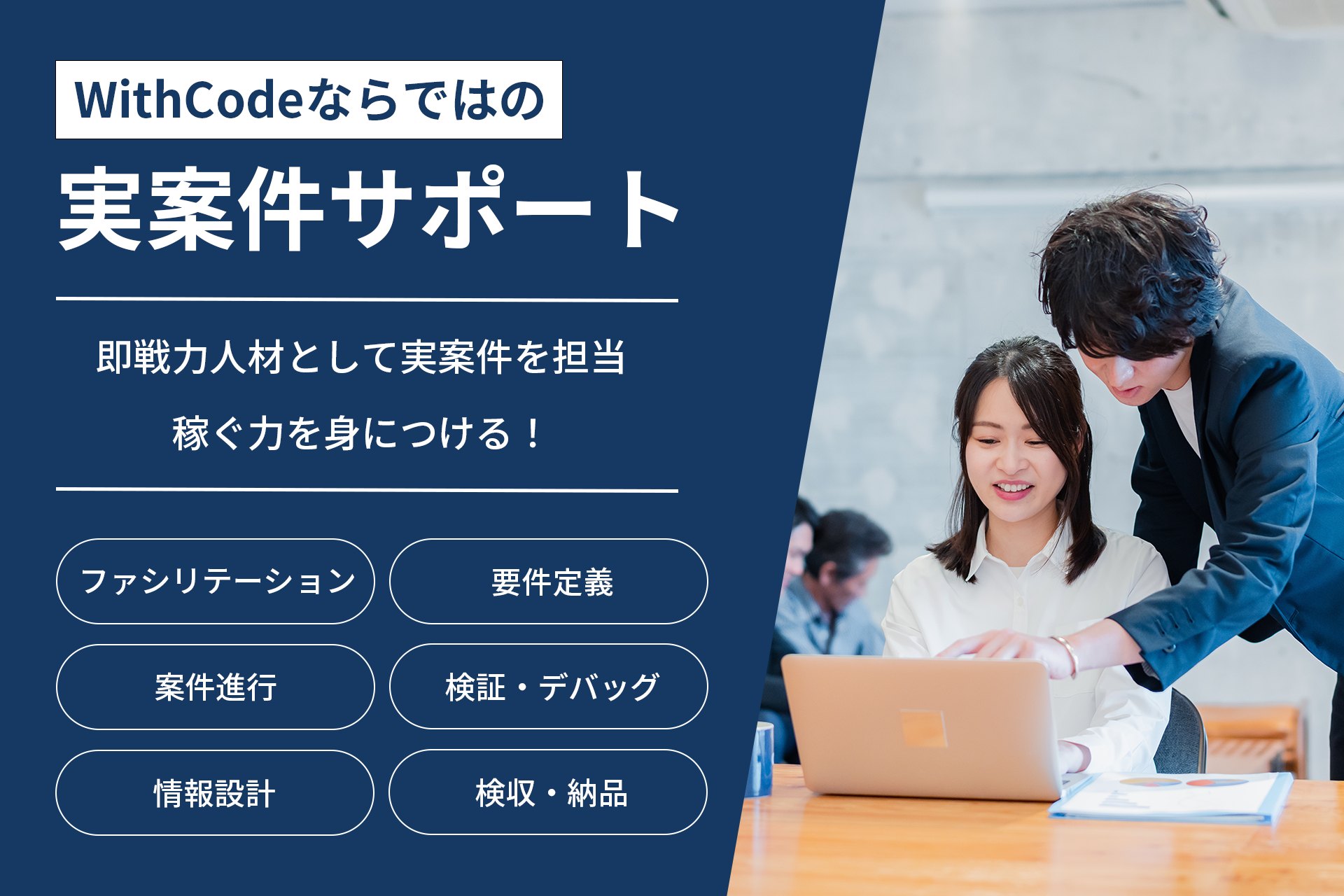
WithCodeMedia-1-sp
WithCodeMedia-2-sp
WithCodeMedia-3-sp
WithCodeMedia-4-sp

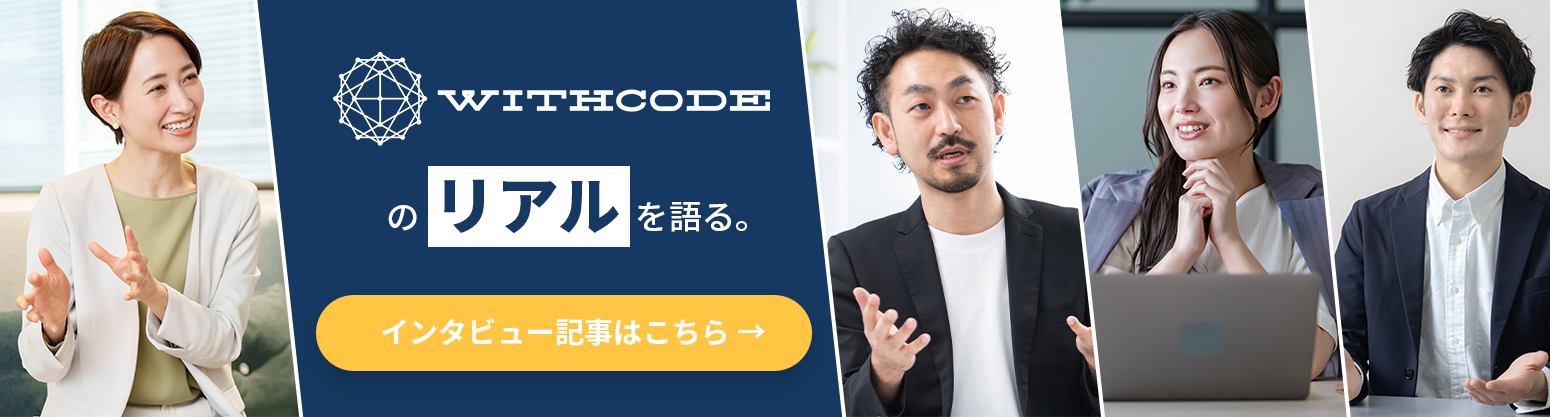
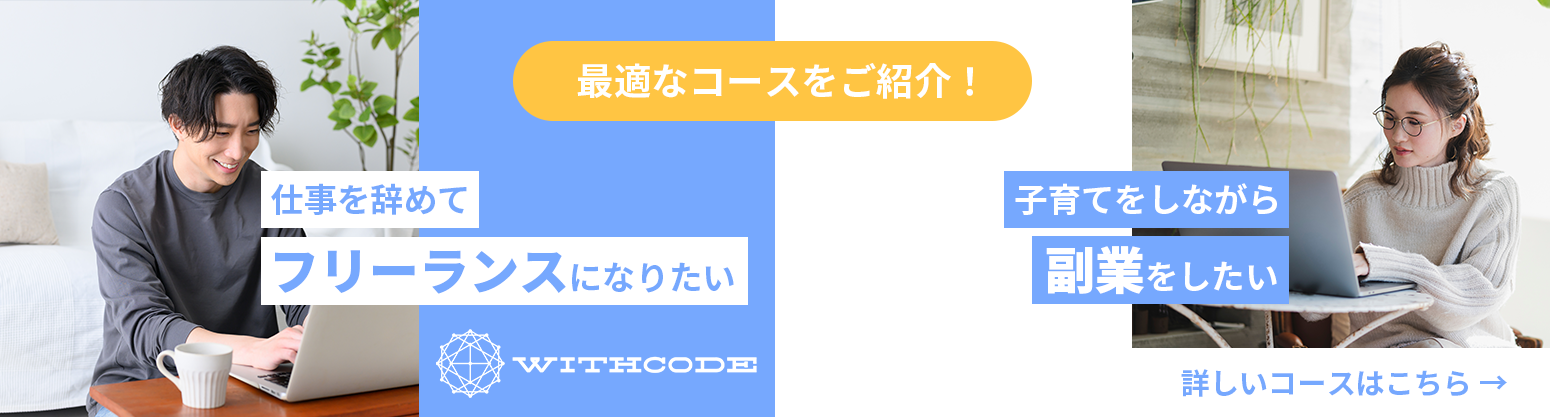
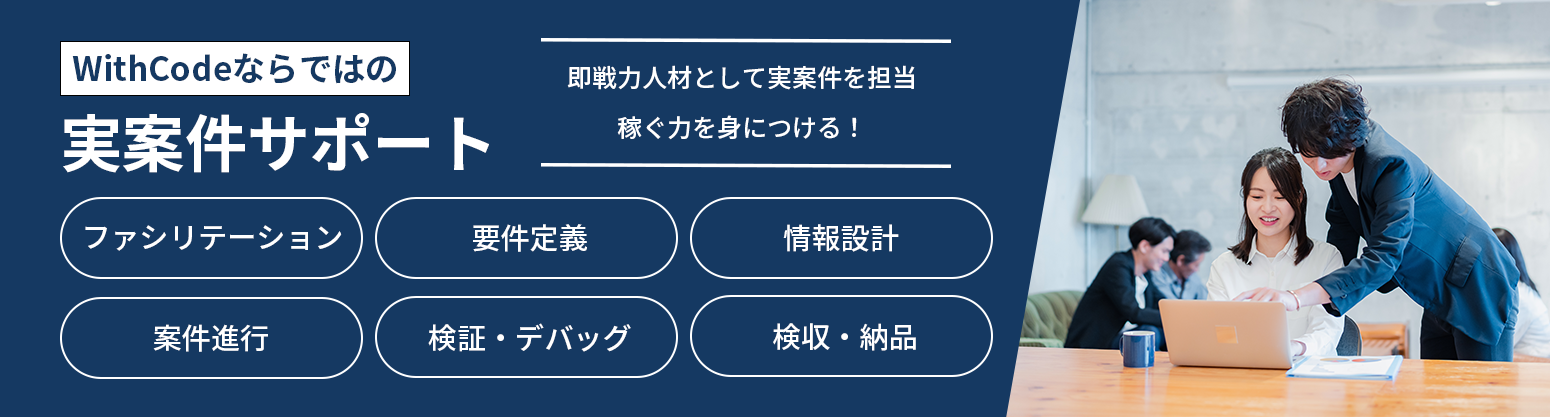



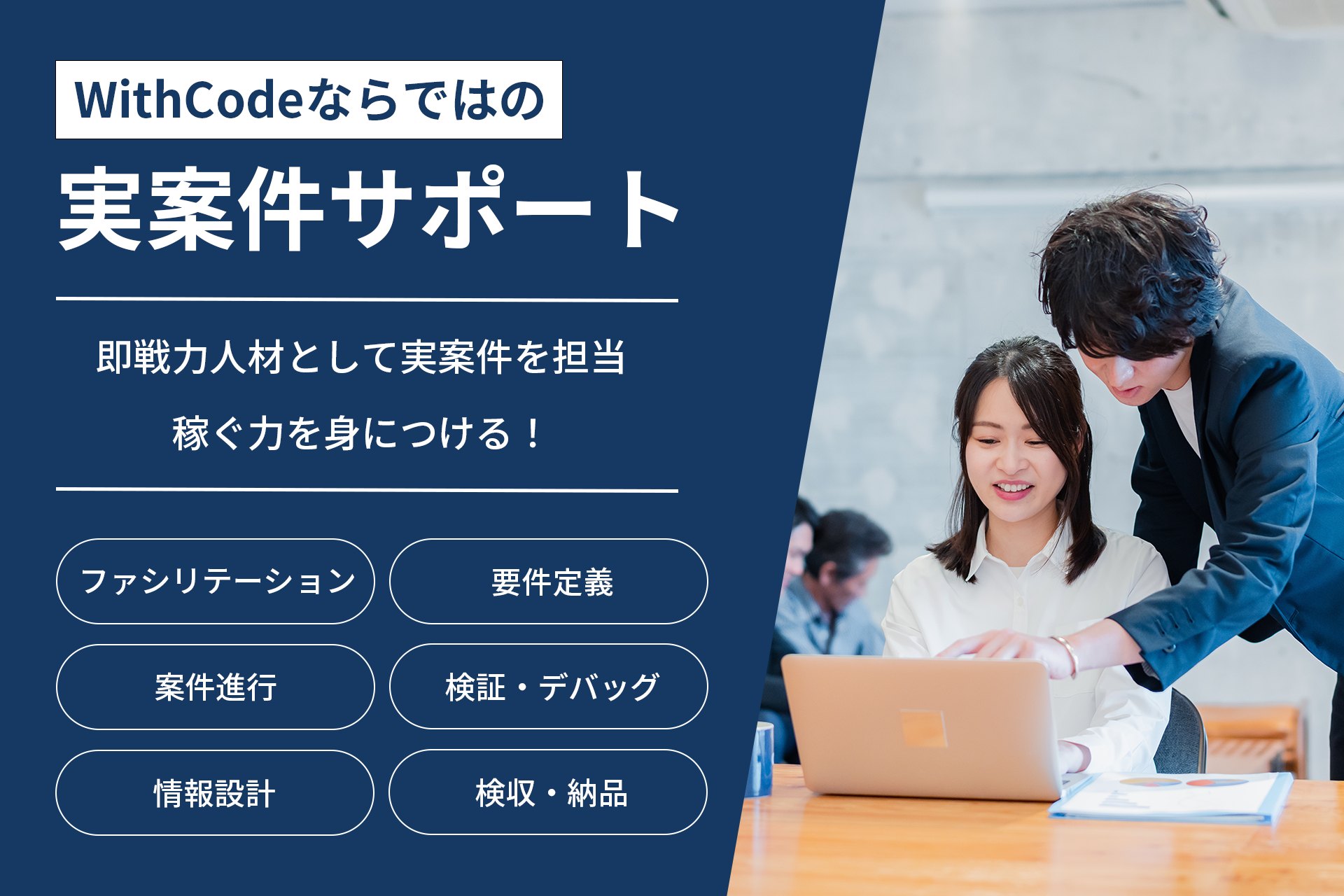
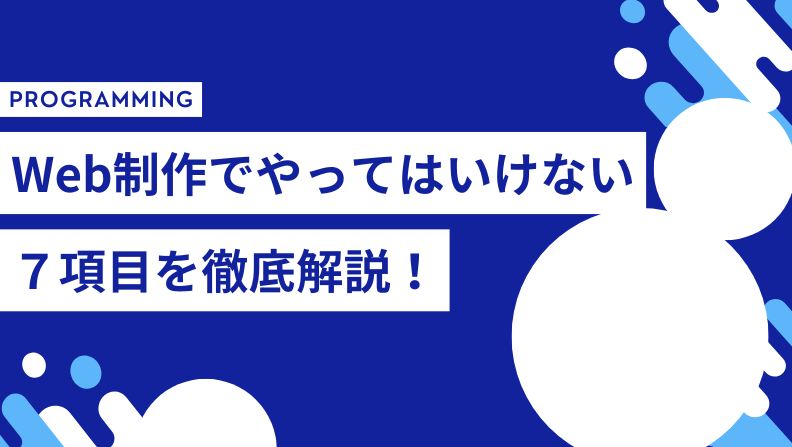
 生徒
生徒ペン博士! Web制作でやってはいけないことって、どんな項目があるんですか?
気をつけているつもりなんですが、不安で……。



良い質問じゃな! 実はな、制作中にやってしまいがちなミスは意外と多いんじゃ。
サーバー選びやデザインの作り方、SEO対策まで、気を抜くと大きな損失につながるぞ!



そうなんですね!ぜひ詳しく教えてください!
「Web制作を始めたけれど、どんなことに気をつければいいのかわからない…」そんな悩みはありませんか?
デザインや機能に集中するあまり、思わぬミスをしてしまうケースは少なくありません。
本記事では、企画・設計から運用・保守まで、Web制作でやってはいけないことを段階ごとに詳しく解説します。
「学習→案件獲得」につなげた受講生のリアルな体験談も公開中!
働き方を変えたい方にも響くストーリーです。
菅井さん
将来的への不安と子育てという背景から「副業」に挑戦しようと決意。独学からプログラミングの学習を開始していたが、WithCodeに出会い体験コースを受講。約4ヶ月の学習に取り組み、当初の目標であった卒業テスト合格を実現した。WithCode Platinumにて3件の案件を担当し、現在は副業だけでなく本格的に「フリーランス」として在宅で活躍していきたいと考えるようになる。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
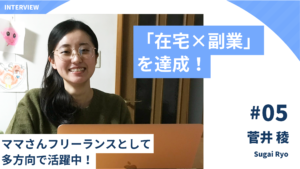
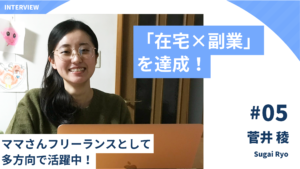
菅井さんの主な制作実績はこちら





Web制作の出発点となる「企画・設計」は、最も重要なフェーズなんじゃ!
この段階を誤ると、どれほど優れたデザインや機能を取り入れても、期待する結果が得られなくなるんじゃ!
ここでは、初期設計でやってはいけないことを紹介するぞ!
「とりあえず会社のサイトを作ろう」「名刺代わりになれば十分」――。
このように目的が曖昧なまま制作を進めると、途中で方向性がぶれてしまいます。
その結果、最終的な成果につながりにくくなるおそれがあります。
Webサイトは、「誰に」「何を」「なぜ」伝えるのかを明確にしたうえで設計することが大切です。
目的が不明確なまま制作を始めると、ページ構成やデザイン、導線設計が後から合わなくなり、修正に大きな手間とコストがかかります。
例えば、以下のように目的によって設計の方向性は大きく変わります。
・集客が目的の場合:SEO対策やコンテンツ戦略を重視する。
・採用が目的の場合:企業文化や職場の雰囲気を伝えるビジュアルが重要。
・ブランド認知・売上向上が目的の場合:それぞれに適した構成や導線設計を考える必要がある。
このように、「なぜ作るのか」という視点でサイトの役割を整理することが、成功への第一歩です。
Web制作でよく見られる失敗のひとつが、「誰に向けたサイトなのか」を明確にしないまま進めてしまうことです。
同じデザインでも、想定するユーザーによって受ける印象は大きく異なります。
例えば、主婦層を対象とする場合は、柔らかいフォントや温かみのある配色が効果的です。
一方で、法人向けサイトでは、信頼性を感じさせる落ち着いたトーンや構成が求められます。
ターゲットが曖昧なままだと、メッセージが伝わりにくく、印象に残らないサイトになるでしょう。
その結果、訴求軸がぶれ十分な成果を得にくくなります。
そのため、ペルソナ(理想的な顧客像)を設定し、以下のような要素を明確に定義しておくことが重要です。
・性別・年齢
・職業や立場
・抱えている課題や悩み
・行動特性・価値観
ペルソナが明確になれば、コンテンツの内容・デザイン・トーンが統一され、訴求力が格段に高まります。
Webサイトの成果は「感覚」ではなく、明確な数値で判断します。
しかし、具体的な目標を設定しないまま制作を進めるケースはいまだに多いのが現状です。
例えば「月5,000PVを達成する」「月50件の問い合わせを獲得する」といった目標を設定すれば、必要な施策を逆算できます。
これにより、重点的に強化すべきページや重視すべき流入経路が明確になるでしょう。
一方で、目標を決めずに制作を進めると、公開後の分析や改善方針が定まりにくくなります。
結果として、アクセスや成果の伸びを十分に引き出せないおそれがあります。
数値目標はサイト運営の羅針盤です。
設計段階で達成基準を定義し、ゴールを明確にしておくことが成果につながります。



なるほど!最初の企画段階でズレてたら、その後の全部に影響しますもんね。



そうじゃ。設計は“地図”のようなもの。最初に方向を誤ると、到着地点もまったく違ってしまうんじゃよ。





サイト構築の段階では、デザインよりもまず「基盤づくり」が重要なんじゃ!
サーバーの選定やURL設計、セキュリティ対策を誤ると、どれほど洗練されたデザインでも安定した運用は望めんのじゃ!
ここでは、構築段階でやってはいけないこと紹介するぞ!
ホームページを公開するには、データを保管するサーバーが必要です。
このサーバーの性能が、表示速度や安定性を大きく左右します。
しかし、コストを抑えるために低スペックなサーバーを選ぶ人が非常に多いです。
たしかに初期費用を抑えられる点では魅力的です。
ただし、その代償として以下のような問題が起きやすくなります。
・表示速度の遅延
・アクセス集中時の制限・エラー
・動作の不安定化やサーバーダウン
特に企業の公式サイトや集客を目的としたページでサーバーが頻繁にダウンすると、ユーザーに不信感を与える結果になりかねません。
その結果、問い合わせや購入といったコンバージョンの機会を逃すおそれがあります。
また、ページの表示速度は検索エンジンの評価にも影響し、、遅いサイトはSEOの面で不利になる可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐには、サイトの規模やアクセス見込みに合ったサーバーを選定することが重要です。
ドメインはWebサイトの「住所」にあたる要素であり、企業の信頼度を左右する指標でもあります。
しかし、「とりあえず取得できるものでいい」と安易に決めてしまうと、ブランドイメージやSEO評価に悪影響を及ぼすことがあります。
特に、見慣れないドメイン名は、悪質サイトやスパムを連想させやすく、ユーザーに不安を与える要因となるでしょう。
その結果、安心して閲覧されにくくなり、サイトの信頼性を損ねるおそれがあります。
そのため、目的や立場に応じて次のように選ぶのが無難です。
・法人サイト:.co.jp(企業の実在性を保証)
・個人事業主・小規模サイト:.com や .jp(一般的で信頼されやすい)
また、ドメイン名の冒頭に企業名やサービス名を含めると覚えやすく、信頼性の向上にもつながります。
見るだけで「何のサイトか分かる」構成を意識しましょう。
SSL化とは、通信を暗号化して情報漏洩を防ぐ仕組みのことです。
URLの冒頭が「http」ではなく「https」となっているサイトがこれに該当します。
SSL化されていないサイトでは、以下のようなリスクがあります。
・ユーザーが入力した個人情報が盗み見られる危険
・ブラウザに「保護されていません」と警告が出て離脱につながる
・検索順位の低下(検索エンジンのの評価基準に含まれるため)
安全で信頼されるサイト運営のためにも、SSL対応は必須です。
パンくずリストとは、ユーザーがサイト内のどのページにいるかを示すナビゲーション要素です。
これがない場合、ユーザーは現在地を把握しづらくなり、離脱につながる恐れがあります。
例えば「トップ > 商品一覧 > 家電 > 冷蔵庫 > 製品A」と表示されていれば、上位カテゴリへの移動も容易です。
また、検索エンジンはパンくずリストを構造化データとして認識できるため、設置しておくと検索結果にも階層情報が表示される場合があります。
パンくずリストの設置には、次のような効果があります。
・サイト内回遊を促進し、離脱率を下げる
・SEO(構造化データ表示)に有利
・ユーザーの位置把握を助けることでUXが向上
ユーザーの利便性だけでなく、SEOの観点からも効果的な要素といえるでしょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
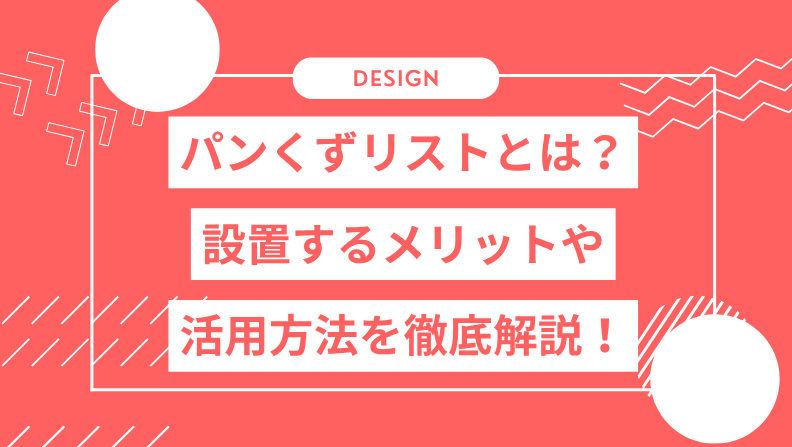
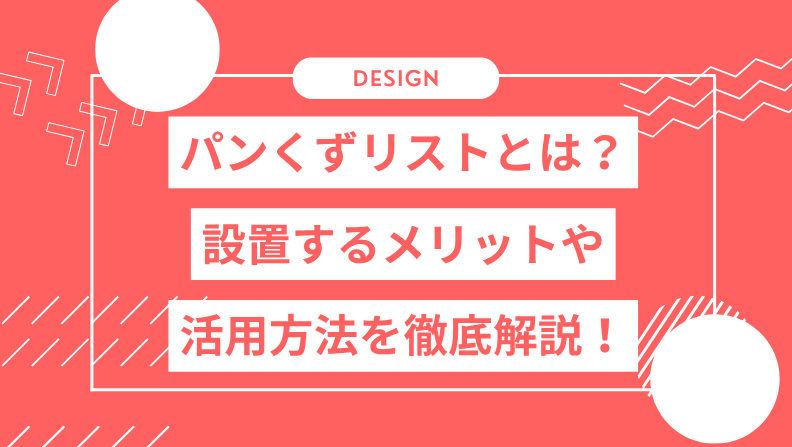
ページの読み込みが遅いだけで、ユーザーはすぐに離脱してしまう傾向があります。
特にECサイトでは、表示に数秒かかるだけで購入をあきらめるケースが増えるといわれています。
表示速度はユーザー満足度だけでなく、検索エンジンの評価にも影響し、サイト全体の順位を左右する要因です。
サイトが重くなる主な原因には、以下のようなものがあります。
・画像の容量が大きすぎる
・JavaScriptやCSSを過剰に使用している
・キャッシュを設定していない
「PageSpeed Insights」などの分析ツールで定期的にスコアを確認し、改善点を把握しておくとよいでしょう。
近年、Webページ閲覧の6割以上がスマートフォンから行われています。
それにもかかわらず、PC向けレイアウトのまま公開すると、以下のような問題が生じます。
・文字が小さく読めない
・ボタンが押しづらい
・画面レイアウトが崩れて見づらい
こうしたモバイル非対応サイトは「使いづらい」と感じられ、離脱につながる要因となるでしょう。
また、検索エンジンはモバイル対応を評価基準の一つとしており、スマートフォンで見づらいサイトは上位に表示されにくくなります。
デザインの段階からスマホやタブレットでの表示を考慮した構成にしておくことが重要です。
実装後は必ず実機で確認し、画面崩れやボタン配置に不具合がないかをチェックしましょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
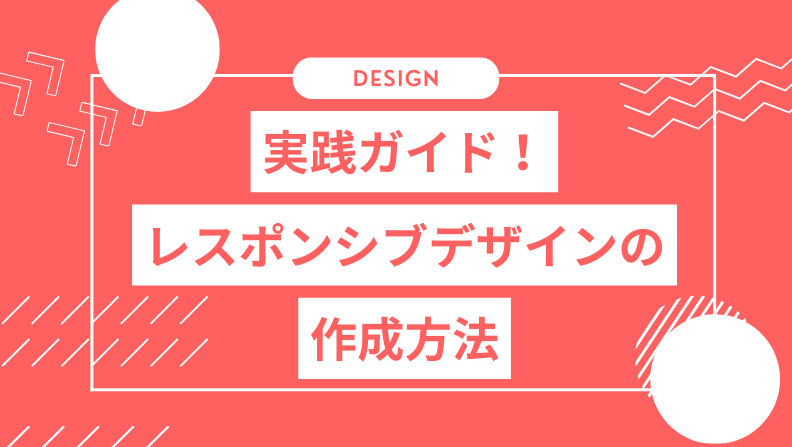
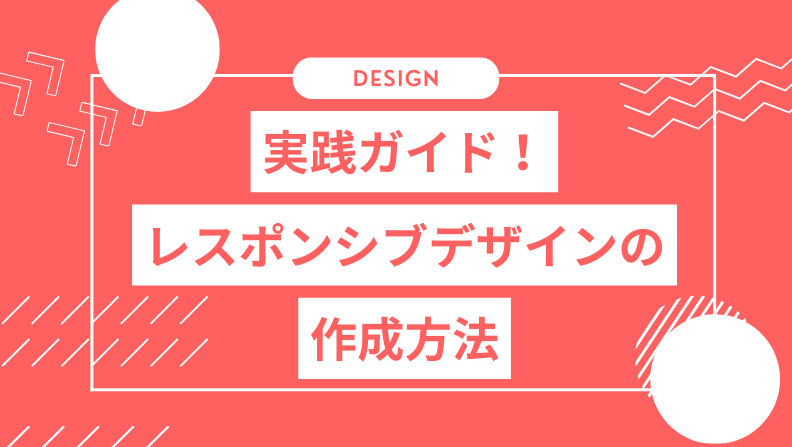
Web制作の目的は「見せること」ではなく「使ってもらうこと」です。
デザイン性ばかりを優先し、更新性を軽視すると、運用段階で大きな負荷を招きます。
専門知識がないと編集できない構造にすると、担当者が更新できず、サイトが放置される原因になるでしょう。
結果として情報が古くなり、「更新されていない=信頼できない」という印象を与えるおそれがあります。
こうした問題を防ぐには、次のような工夫が効果的です。
・WordPressなどのCMSを導入し、管理画面から簡単に更新できるようにする
・更新用テンプレートを用意し、誰でも編集ルールを守れるようにする
・マニュアルを共有し、担当者交代時もスムーズに引き継げるようにする



構築の段階でも“やってはいけないこと”って多いんですね。



うむ。整理整頓こそWeb制作の美学じゃ。」





Webサイトに掲載する文章や画像などのコンテンツは、サイト全体の印象や信頼性を大きく左右するぞ!
作り方を誤ると、検索エンジンの評価を下げるだけでなく、法的リスクや炎上などの深刻な問題を招くおそれもあるんじゃ!
ここでは、コンテンツ制作でやってはいけない代表的なケースを紹介するぞ!
画像・音楽・動画などの素材にはすべて著作権が存在します。
ネット上で公開されているものでも、自由に使えるとは限りません。
「公開=利用許可」とは別の問題であり、営利目的での使用は個人ブログでも著作権侵害にあたるおそれがあります。
特に、画像検索で見つけた写真を無断で転載したり、YouTube動画を埋め込んだりする行為は避けましょう。
画像を使用する場合は、画像を使用する場合は、商用利用可能なフリー素材サイトを利用するのが安全です。
代表的なサイトとしては以下が挙げられます。
・Unsplash
・Pixabay
・ぱくたそ
また、他者の作品を紹介目的で使用する場合は、出典やリンクを明記し、必要最小限の範囲に留めることが重要です。
この基本を守ることで、著作権トラブルを未然に防ぎ、サイト全体の信頼性も維持できます。
時間短縮を目的に他サイトの文章をコピーして掲載するのは厳禁です。
検索エンジンは重複コンテンツを高精度で検出し、コピーと判断されたページは評価が下がります。
表現を一部言い換えただけでは回避できず、サイト全体の信頼性を損なう原因となるでしょう。
また、他人の文章をそのまま引用する行為は、著作権だけでなくブランドイメージにも悪影響を及ぼします。
他サイトの情報を取り入れる場合は、ご自身の言葉で要約し、独自の視点を加えることが大切です。
引用する際は出典を明示し、本文の主張を補足する範囲に留めましょう。
テキスト中心のページは情報量が多くても、ユーザーにとって読みづらく感じられがちです。
長文が続くと離脱率が高まり、最後まで読まれないケースも少なくありません。
さらに、テキストのみの構成はSEOの観点からも不利といえます。
検索エンジンは、画像や表などの補助情報を通じて、ページ内容をより正確に理解します。
そのため、以下のような工夫を取り入れると効果的です。
・文章の途中に図解・表・アイコンを挿入する
・重要な情報は箇条書きで整理する
・見出しや余白を活用してリズムをつける
ただし、利用規約やプライバシーポリシーなどは例外であり、テキスト中心でも問題ありません。
一方で、商品紹介・サービス説明・ブログ記事では、ビジュアル要素を活用して読まれるコンテンツを目指すことが重要です。
コンテンツを充実させたいあまり、根拠のない情報や推測を掲載するのは危険です。
誤情報の拡散は、企業の信頼失墜や法的トラブルにつながるおそれがあります。
例えば以下のようなケースは特に注意が必要です。
・健康食品等の効果を誇張する
・他社製品を根拠なく批判する
・統計や調査を裏付けなしで引用する
これらの行為は、景品表示法や薬機法に抵触する可能性もあります。誤った情報をもとにユーザーが損害を被った場合、損害賠償を請求されるリスクもあります。
記事を作成する際は、公的機関・公式サイト・一次情報を参照し、出典を明記することが基本です。
裏付けのあるデータを提示することで、ユーザーからの信頼を得られるでしょう。
画像はサイトの魅力を高める一方で、サイズが大きすぎると読み込み速度を著しく低下させます。
高解像度の写真をそのまま掲載すると、表示に時間がかかり、離脱率が上がる傾向があります。
また、縦長すぎる画像や比率の合わない写真は、レイアウト崩れを引き起こす要因となるでしょう。
画像を使用する際は、Web向けに圧縮し、解像度と容量のバランスを最適化することが重要です。
リンクはユーザーを導く重要なナビゲーション要素です。
しかし、リンク先の内容がユーザーに伝わらないまま設置すると、クリック率が下がるだけでなく、誤クリックによる離脱を招くおそれがあります。
「こちら」「ここをクリック」などの曖昧な表現は避け、「○○の詳細を見る」「お問い合わせページへ」など、リンク先の内容を具体的に示すことが大切です。
複数のリンクを設置する場合は、色やデザインで区別すると操作性が向上します。



“とりあえず埋める”じゃダメなんですね。



その通り。コンテンツは“伝えるための設計物”じゃ。ユーザーの心に届かぬ言葉は、どんなデザインでも輝かんぞ。
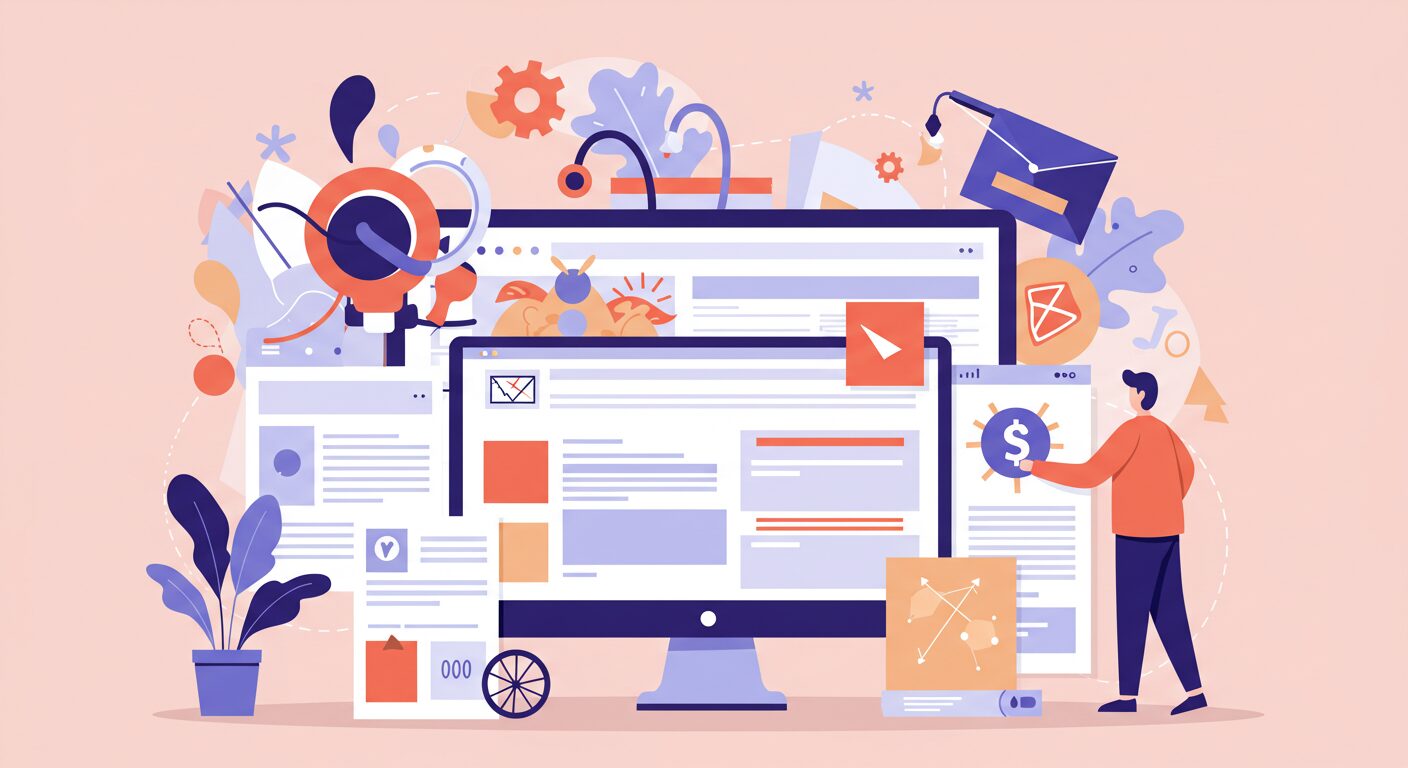
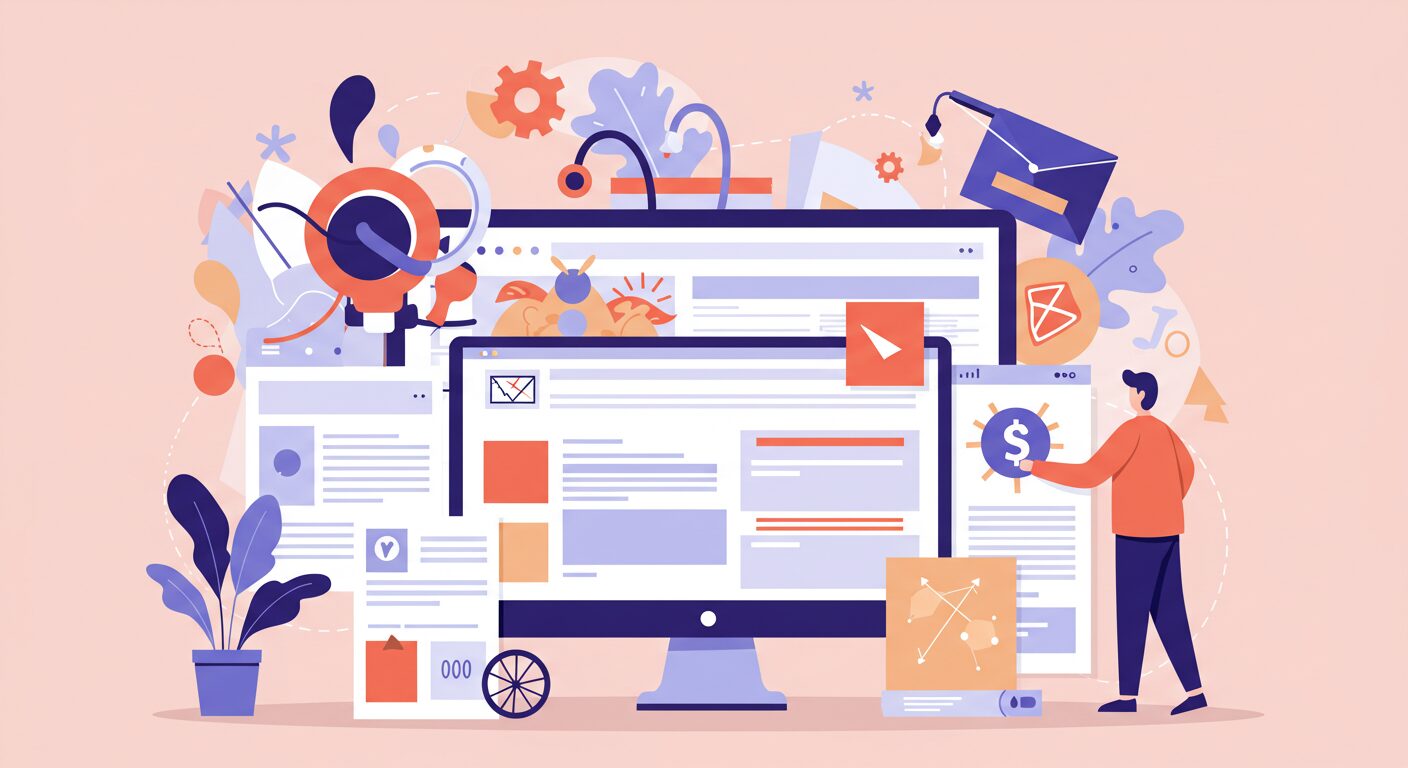



Webサイトの印象を決める最大の要素がデザインなんじゃ!
しかし、見た目ばかりを優先すると、ユーザーが使いにくいサイトになったり、信頼性を損なってしまうんじゃ!
ここでは、デザイン段階でやってはいけない主なポイントを紹介するぞ!
サイト全体で統一された「トーン&マナー(トンマナ)」を決めずに制作を始めるのは危険です。
トンマナとは、フォントの種類や文字サイズ、色合い、余白の使い方など、サイト全体の印象を決めるルールのことです。
例えば、トップページでは落ち着いた色調を採用しているのに、下層ページでは急にポップな配色になっていると、ユーザーは違和感を覚えます。
「同じ企業のサイトなのか?」と思われるほど印象が変われば、信頼感の低下につながるでしょう。
一方で、トンマナを事前に設計しておけば、全ページで統一感を保ちながら柔軟にデザインを展開できます。
具体的には以下のような項目をデザインガイドラインとして文書化するのが理想です。
・カラーパレット(メインカラー/アクセントカラー)
・使用フォントと文字サイズのルール
・ボタン・見出し・リンクなどのスタイル
・余白やレイアウトの基準
このガイドラインを共有しておけば、担当者が変わっても一定の品質を維持でき、ブランド全体の信頼を守ることができます。
一昔前は、動きのあるサイトを作るためにAdobe Flashが多用されていました。
しかし、Flashはすでに2020年12月31日に公式サポートが終了しており、現在の主要ブラウザでは再生できません。
それにもかかわらず、古いテンプレートを使っている企業サイトや個人ページでは、今でもFlashが残っているケースがあります。
Flashコンテンツはセキュリティ上の脆弱性を抱えていることが多く、不正アクセスやマルウェア感染の原因となるおそれがあります。
もしサイト内に古いFlash要素が残っている場合は、速やかにHTML5やCSSアニメーションへ置き換えることが重要です。
強調やカラフルな文字を多用すると、視線が分散し内容が伝わりにくくなります。
特に太字・赤文字・蛍光色を多用すると、チラシのような雑多な印象を与えてしまいます。
装飾はポイントを絞り、読みやすさを最優先にしましょう。
1画面あたりで強調を使う箇所は2〜3カ所程度に抑えるのが理想です。
要点を際立たせつつも、全体として落ち着いた印象を保つことで信頼性が高まります。
アニメーションは、情報を引き立てたり動きを加えたりするのに有効な手段です。
しかし、使いすぎると逆効果になり、ユーザーの視線が分散して肝心なメッセージが届きにくくなります。
また、アニメーションを多用するとデータ容量が増え、読み込み速度の低下を招くこともあります。
特にトップページのスライダーやフェードインなどを過剰に設定すると、初回表示に数秒を要するケースも少なくありません。
多くのユーザーは待たされることを嫌い、ページが表示される前に離脱するおそれがあります。
アニメーションは「飾り」ではなく、情報を伝えるための補助的な要素として使うのが理想です。
注目してほしいボタンやセクションのみに軽い動きをつけるだけでも十分に効果が得られます。
必要最小限の動きを意識すれば、印象的でありながら快適に閲覧できるデザインを実現できるでしょう。
Webサイトは、誰に情報を届けるのかを明確にしたうえで設計することが重要です。
ターゲット像を考慮せずにデザインを進めてしまうと、どれほど美しく仕上げても成果にはつながりません。
例えば、子ども向けのおもちゃを紹介するサイトがあるとします。これが黒を基調としたビジネスライクなデザインだった場合、親しみよりも堅苦しさが目立ち、購買意欲を損ねるおそれがあります。
一方で、法人向けのBtoBサイトに手書き風イラストやカラフルなフォントを多用すれば、企業としての信頼性を失いかねません。
ターゲットに合わせて、以下のような要素を調整しましょう。
・主婦層向け:温かみや安心感のある配色
・若年層向け:明るく動きのある構成
・企業向け:余白を活かした上品で落ち着いたレイアウト
「誰に何を伝えるか」を意識し、デザイン方針を定めることが、成果を生む第一歩です。



見た目が派手でも使いづらかったら意味がないんですね。



うむ。美しさより“目的の達成”が先じゃ。デザインとは、ユーザーの行動を導く“設計の言語”なんじゃよ。





SEO(検索エンジン最適化)は、Webサイトを多くの人に見てもらうために欠かせない施策のことじゃ!
正しい知識を持たずに自己流で行うと、逆に検索順位を下げる結果を招くこともあるから注意が必要なんじゃそ!
ここでは、SEO対策の際にやってはいけないことを紹介するぞ!
かつてのSEOでは、ページ内にキーワードを多く盛り込むほど上位表示されやすいと考えられていました。
しかし現在の検索エンジンは、文章全体の自然さや文脈の一貫性を重視しており、過剰なキーワードの挿入は逆効果です。
以下のような点に注意しましょう。
・不自然なキーワードの繰り返しは避ける
・タイトル・見出し・本文に自然な流れで配置する
・ユーザーが求める情報を中心に構成する
ユーザーが知りたいのは「キーワード」ではなく「信頼できる情報」です。
自然な文脈の中で適切に配置すれば、読みやすさとSEO効果を両立できます。
背景と同じ色でキーワードを埋め込んだり、、極端に小さな文字でテキストを隠したりする行為は危険です。これは検索エンジンのスパム対策ガイドラインで明確に禁止されています。
以下のような手法もペナルティの対象です。
・透明な画像の下にリンクを埋め込む
・画面外にリンクを配置する
・背景と同色の文字を使ってキーワードを隠す
一時的に順位が上がることがあっても、発覚すればインデックス削除や検索順位低下などのリスクがあります。
SEOは「エンジンを騙す技術」ではなく、「ユーザーに正しく情報を届ける技術」であることを忘れてはいけません。
AIツールや自動記事生成ソフトを使って、大量のコンテンツを一度に作成する方法が話題になっています。
確かに短時間で多くのページを作成できる点は魅力的ですが、内容の薄い記事を量産すると逆効果です。
AIを活用する場合は、以下のルールを守ることが重要です。
・作成後に必ず製作者が内容を確認する
・独自の視点や実体験、具体例を加える
・根拠のあるデータ・一次情報を引用する
自動生成はあくまで「下書き」として使い、最終的な品質担保は製作者が行うことを徹底しましょう。
外部サイトからの被リンクは、今もSEO評価における重要な要素の一つです。
ただし、自作自演やリンク購入などで不自然にリンクを増やす行為は、検索エンジンのガイドラインでも明確に禁止されています。
かつてはリンク数が評価の中心でしたが、現在はリンク元の信頼性と関連性が重視されます。
不自然なリンクが多いと「スパムリンク」として無効化されるだけでなく、ドメイン全体にペナルティが及ぶ可能性もあるでしょう。
本質的なSEOとは、リンク集めるのではなく、自然に紹介されるだけの価値あるコンテンツを作ることです。
同一または類似の内容を含むページを複数公開する行為も避けるべきです。
検索エンジンがどのページを評価すべきか判断できず、結果として順位が下がる可能性があります。
URLだけ異なる同一商品ページを複製したり、地域名を変えただけの記事を量産したりするケースが典型です。
これらは「コピーコンテンツ」として扱われ、SEO評価を下げる要因になります。
画像はコンテンツを構成する重要な要素の一つです。
しかし、検索エンジンは画像そのものを理解できません。そのため、内容を説明するalt属性(代替テキスト)を設定する必要があります。
altを設定しない場合の問題点は次のとおりです。
・画像検索からの流入を逃す
・スクリーンリーダーが情報を読み上げられない
画像が何を表しているのかを、短く・具体的に記述しましょう。
例:「会社ロゴ」「商品イメージ」「サービス紹介バナー」など。



SEOって小手先じゃなくて“地道な積み重ね”なんですね!



そうじゃ。検索エンジンは誤魔化せん。正しい構造と良質な情報が、長期的に信頼を築くのじゃ。





どれほど完成度の高いWebサイトでも、公開後の運用や保守を怠れば、すぐに信頼を失ってしまうぞ!
「作って終わり」ではなく、「維持しながら成長させる」視点を持つことが不可欠なんじゃ!
ここでは、運用・保守の段階でやってはいけないことを紹介するぞ!
Webサイトの内容を長期間更新しないのは、よくある失敗のひとつです。
会社概要やニュース欄が数年前から止まっていると、「この会社は今も活動しているのか?」という不信感を与えます。
特にトップページに「最新情報」や「お知らせ」を表示している場合、放置しているだけで企業イメージが古く見える要因となるでしょう。
また、SEOの評価基準のひとつに「情報の新鮮さ(フレッシュネス)」があります。
長期間更新がないサイトは検索順位が下がりやすく、競合サイトに埋もれてしまいます。
例えば次のような工夫をするとよいでしょう。
・月に一度はニュースやブログ記事を追加する
・会社情報や料金ページなど、更新頻度が低い部分も定期的に見直す
・季節に合わせてトップページの画像や文言を変更する
小さな更新でも構いません。継続的な情報発信が、ユーザーからの信頼とSEO効果の維持につながります。
見落とされがちなのが、契約更新忘れによるサイト停止です。
更新期限を過ぎるとサイトが自動的に非公開となり、最悪の場合、ドメインを第三者に取得され悪用されるおそれがあります。
会社名を含むドメインを失効させてしまうと、ブランドや信用に深刻なダメージを与える結果になりかねません。
運用担当者は、契約更新日をカレンダーや管理表に記録し、複数人で管理できる体制を整えておくことが重要です。
WordPressなどのCMSを利用している場合、定期的なアップデートは必須です。
更新を怠ると、セキュリティホールを突かれて不正アクセスやサイト改ざんの被害を受けるリスクが高まります。
古いプラグインを放置したサイトでは、知らないうちにスパム投稿やマルウェア感染が発生することもあります。
特に、サポートが終了したテーマやプラグインには注意が必要です。
脆弱性が見つかっても修正されないため、攻撃対象になりやすくなります。
CMSの管理画面に表示される「更新通知」は見逃さず、更新前にバックアップを取り、慎重に対応するのが基本です。
Webサイト運用の根幹にあるのがセキュリティ対策です。
しかし、パスワードの使い回しやアクセス制限の未設定など、初歩的なミスが原因で情報漏洩が発生するケースは少なくありません。
管理画面のログインURLや初期パスワードを変更せず放置すると、総当たり攻撃(ブルートフォースアタック)の標的になりやすくなります。
また、FTPアカウントを共有したままにしていると、担当者変更時にトラブルを招くおそれがあります。
こうしたリスクを避けるには、以下の対策が効果的です。
・二段階認証を導入する
・アクセス制限(IP制限・VPN接続)を設定する
・定期的にパスワードを変更する
・権限設定を見直し、最小限のアクセス権にする
セキュリティ対策は一度整えたら終わりではありません。
人の入れ替わりや体制変更のたびに、見直しを行うことが重要です。
サイト運営における最も危険なミスのひとつです。
サーバー障害や誤操作、ハッキング被害が発生した際、バックアップがなければ復旧はほぼ不可能といえます。
特にCMSサイトでは、データベースと画像ファイルを分けてバックアップを取ることが重要です。
自動バックアップを設定するほか、定期的にローカル環境にも保存しておくと安心です。
また、バックアップは「取るだけ」では意味がありません。
復元手順を事前に確認し、即時復旧できる体制を整えておくことが、被害を最小限に抑える鍵となります。
サイトを運用するうえで、ユーザー行動の把握と分析は欠かせません。
アクセス解析を行わないと、改善点が見えず、成果につながらない運営を続けることになります。
代表的な解析ツールとして、以下が挙げられます。
・Googleアナリティクス:訪問数や滞在時間を分析
・Search Console:検索流入や表示順位を把握
これらを定期的に分析することで、人気のあるページを強化し、閲覧数の少ないページを改善するなど、データに基づいた運用が可能です。
「勘」や「感覚」ではなく、客観的な数値に基づいて改善を重ねることが、成果を上げるWeb運用の基本です。



公開して終わりじゃないんですね!



まさにそこが落とし穴じゃ。Webサイトは“育てるもの”。更新と分析を怠ると、どんな名作も埋もれてしまうんじゃ。





Web制作を外部に委託する際、依頼内容や契約条件を明確にしないと、トラブルを招くことがあるんじゃ!
特に、価格だけで制作会社を選んだり、契約書を確認せずに進めたりするのは非常に危険じゃぞ。
ここでは、外注する際にやってはいけないことを紹介するぞ!
「できるだけ安く作りたい」と価格だけで判断するのは、よくある失敗の一つです。
低価格をうたう制作会社の中には、テンプレートをそのまま流用したり、修正対応を限定的にしか行わないケースも見られます。
一見コストが抑えられても、品質が低ければ後から修正費用がかさみ、結果的に割高となることもあります。
たしかに初期費用を抑えられる点では魅力的ですが、次のようなリスクがあります。
・品質が低く、修正費用がかさむ
・独自性がなく、他社サイトと似てしまう
・サポート体制が不十分でトラブル時に対応できない
コストだけでなく、目的達成のための提案力やアフターサポートの有無など、総合的な視点で選定しましょう。
複数社の見積もりを比較し、相場から大きく外れる場合は理由を確認しておくことが重要です。
Web制作トラブルの多くは、契約条件の不明確さから発生します。
口頭のやり取りだけで進めると、納品後に「修正回数」「支払い条件」「著作権の帰属」などで揉めることがあります。
契約時には、以下の項目を必ず明文化しておきましょう。
・修正対応の範囲・回数
・支払い時期と条件
・著作権・ソースコードの所有者
・契約解除時の取り決め
「できるだけ早めに」といった曖昧な表現では、制作会社と発注側の認識がずれやすくなります。
その結果、「想定より遅く、リリースに間に合わない」といったトラブルにつながりかねません。
こうした事態を防ぐには、以下のように明確に取り決めておくことが大切です。
・各工程(設計・デザイン・実装・テスト)のスケジュールを共有する
・「◯営業日以内に確認」「◯日までに修正依頼を提出」など具体的な期限を設定する
・進捗確認ミーティングを定期的に実施する
「専門家に任せれば大丈夫」とすべてを委ねるのは危険です。
制作会社はデザインや技術の専門家ではありますが、あなたの事業内容や顧客層まで理解しているとは限りません。
目的やターゲットを共有しないまま進めると、方向性のずれたサイトが完成するおそれがあります。
依頼時には、次のような情報を具体的に伝えましょう。
・目的(集客・採用・認知など)
・想定ターゲット(性別・年齢・業種など)
・競合サイトの情報
・必要な機能・ページ構成
・参考サイト(3つほど提示)
Web制作は「任せる仕事」ではなく、「共に作るプロジェクト」です。
制作者と対話しながら方向性を擦り合わせることが成果への近道です。
制作途中で仕様変更や追加要望が発生することは珍しくありません。
しかし、費用や対応範囲の取り決めをしていないと、請求トラブルを招く原因になります。
例えば、「トップページのレイアウトを少し変えたい」と依頼した場合を考えます。
このような場合でも制作会社によっては「新規デザイン扱い」として、追加費用を請求されることも少なくありません。
契約段階で修正回数・対応範囲・費用発生条件を明確にしておくことが大切です。
また、修正依頼を都度出すと全体の進行が遅れます。
要望はできるだけまとめて伝え、確認時点で仕様を確定させましょう。
制作会社に依頼したWebサイトの著作権は、原則として制作会社に帰属します。
発注者が自由に編集や再利用を行いたい場合は、「著作権譲渡」または「利用範囲」を契約書に明記しておく必要があります。
この取り決めを曖昧にしたままサイトを改修・再利用すると、「無断使用」として法的トラブルに発展する場合もあるので注意が必要です。
また、画像やフォントなどの素材も、ライセンス上の理由で再利用できない場合があります。
契約時には、次の点を必ず確認しましょう。
・納品後に自社で編集可能か
・第三者(他社)による修正が許可されているか
・使用素材のライセンス範囲
これらを明確にしておくことで、納品後のトラブルを未然に防ぐことができます。



ペン博士、Web制作でやってはいけないことを学んでみて、思っていた以上に奥が深いですね!
ちょっとした判断ミスでも大きな影響が出るなんて驚きました。



うむ、これらをしっかり理解して今後のWebサイト制作に生かすんじゃぞ!今回学んだポイントをしっかり意識すれば、失敗は確実に減るはずじゃ!



ありがとうございます!この学びを今後のWebサイト制作に役立てます!
本記事では、Web制作でやってはいけない項目を詳しく解説しました。
要点は以下の通りです。
・企画・設計段階では、目的・ターゲット・数値目標を明確にする。
・サイト構築では、サーバー性能・ドメイン・SSL化など基本設定を怠らない。
・コンテンツ作成では、独自性と信頼性を重視する。
・デザインでは、トンマナを統一し、ユーザー層に合った表現を心がける。
・SEO対策では、自然なキーワード配置と正しい技術実装を意識する。
・運用・保守では、定期更新・セキュリティ対策・バックアップを徹底する。
・外注時は、価格だけでなく契約条件や著作権も確認する。
これらのポイントを押さえておけば、高品質なサイトを継続的に運用できます。
目的に合った設計と正しい運用を心がけ、成果を生むWeb制作を実現しましょう。


副業・フリーランスが主流になっている今こそ、自らのスキルで稼げる人材を目指してみませんか?
未経験でも心配することありません。初級コースを受講される方の大多数はプログラミング未経験です。まずは無料カウンセリングで、悩みや不安をお聞かせください!
公式サイト より
今すぐ
無料カウンセリング
を予約!