
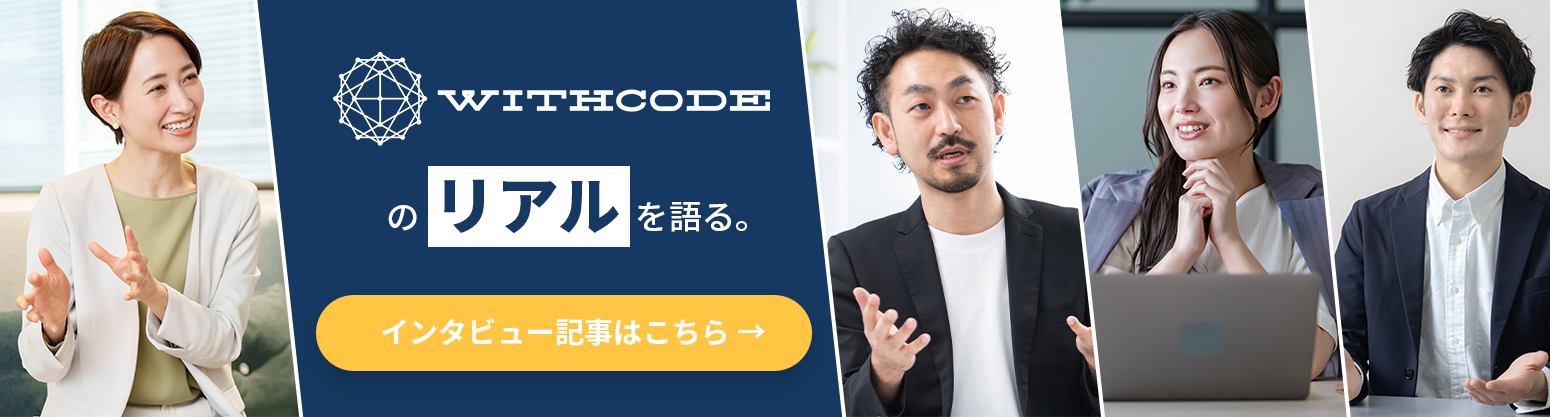
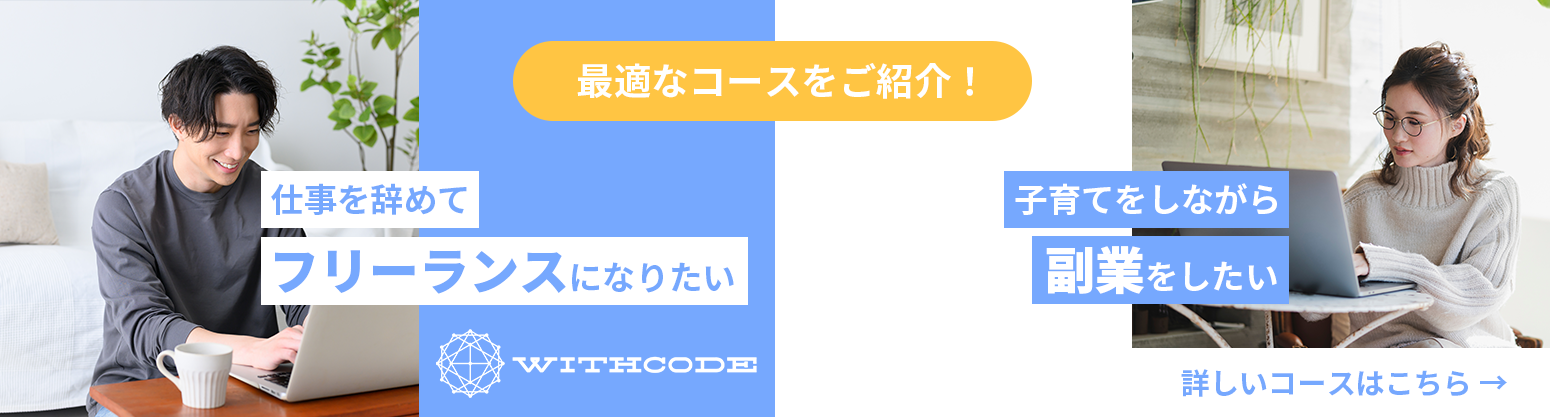
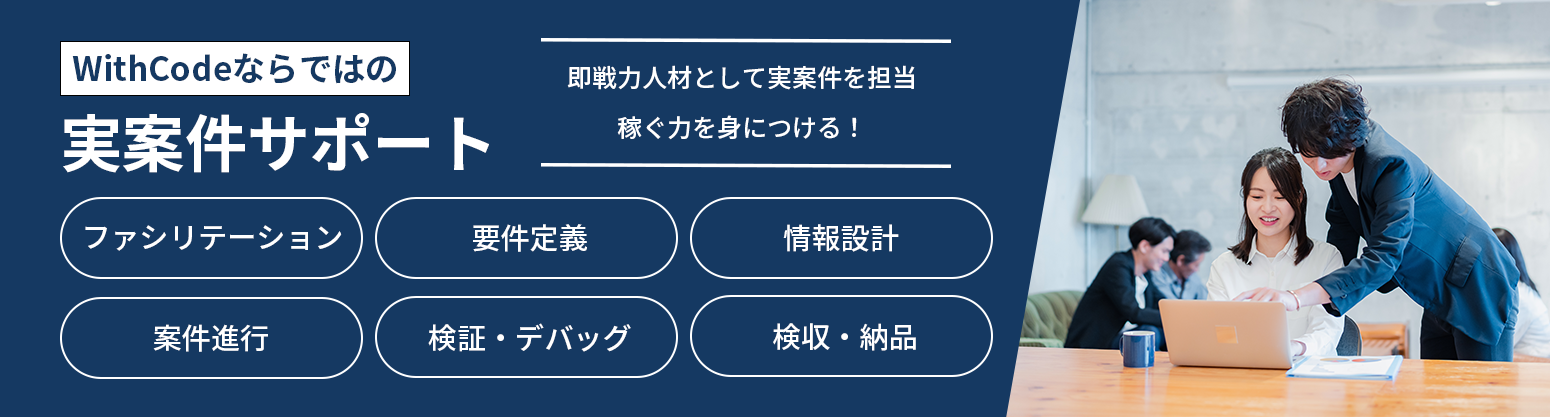
WithCodeMedia-1-pc
WithCodeMedia-2-pc
WithCodeMedia-3-pc
WithCodeMedia-4-pc



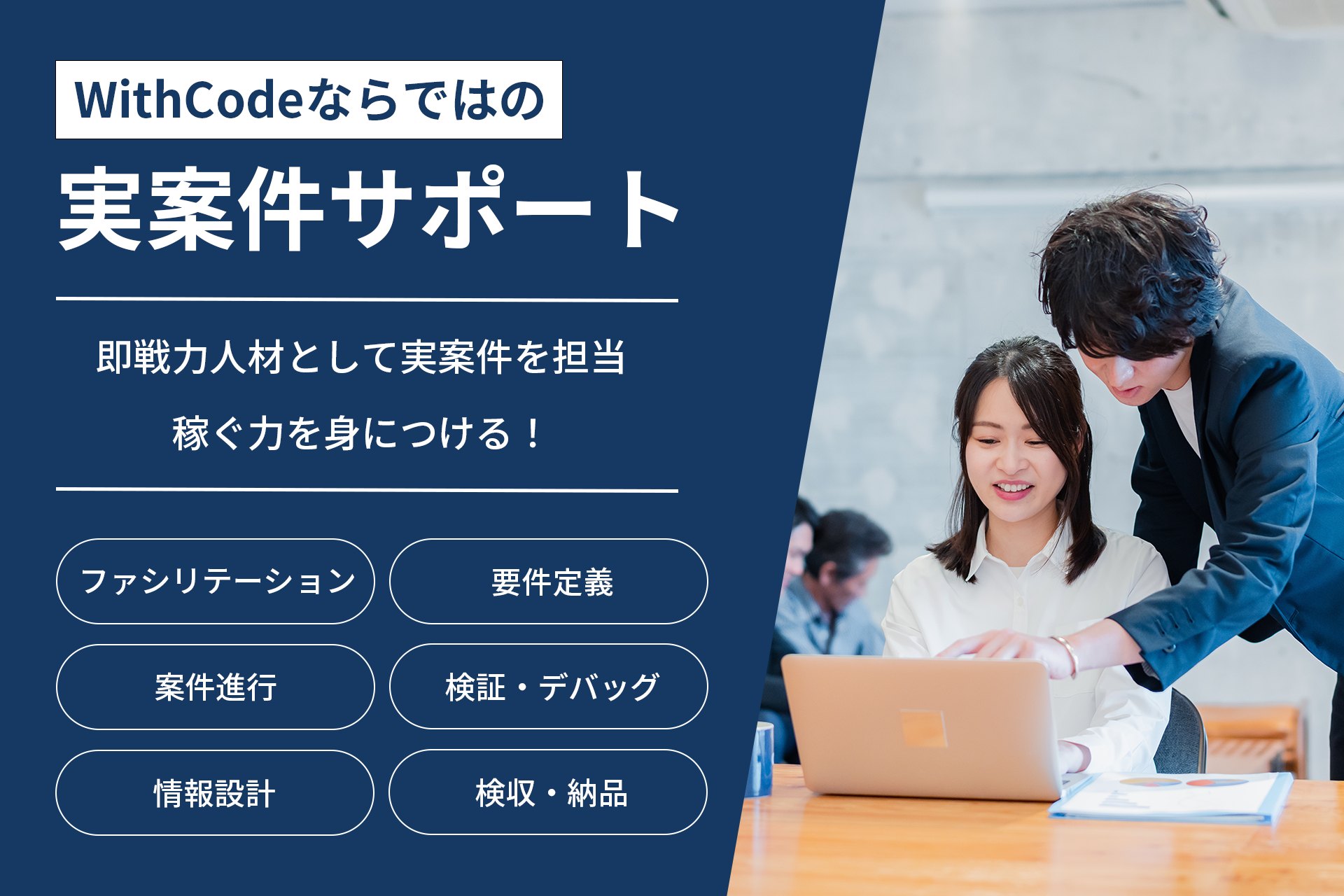
WithCodeMedia-1-sp
WithCodeMedia-2-sp
WithCodeMedia-3-sp
WithCodeMedia-4-sp

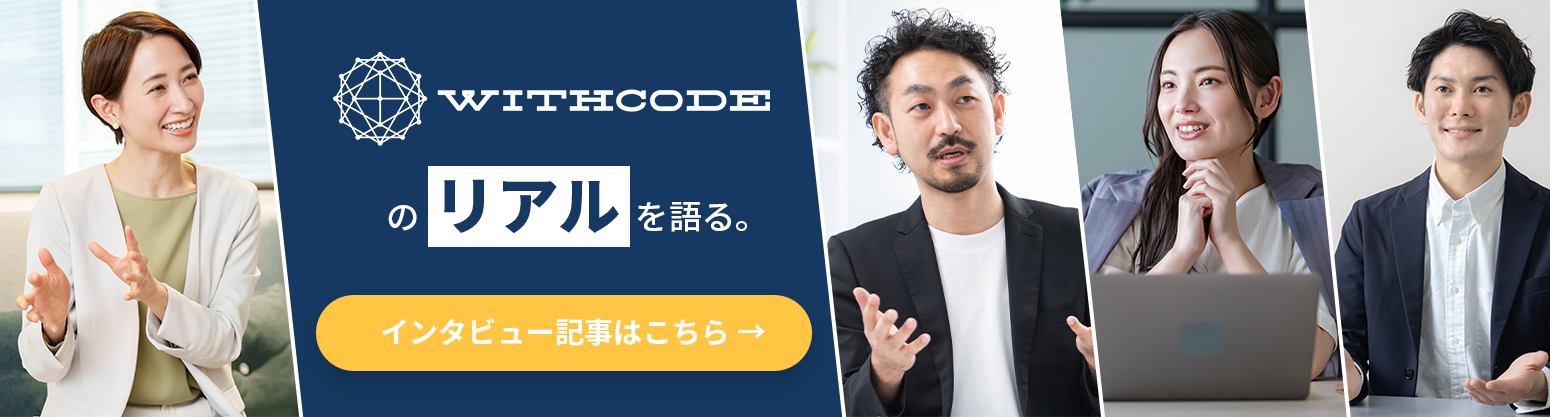
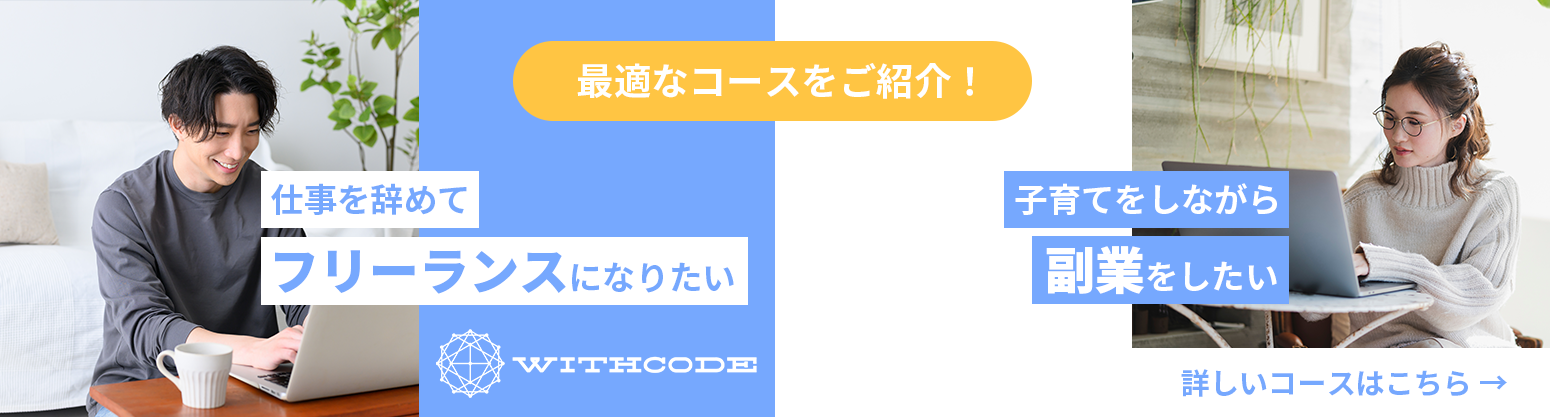
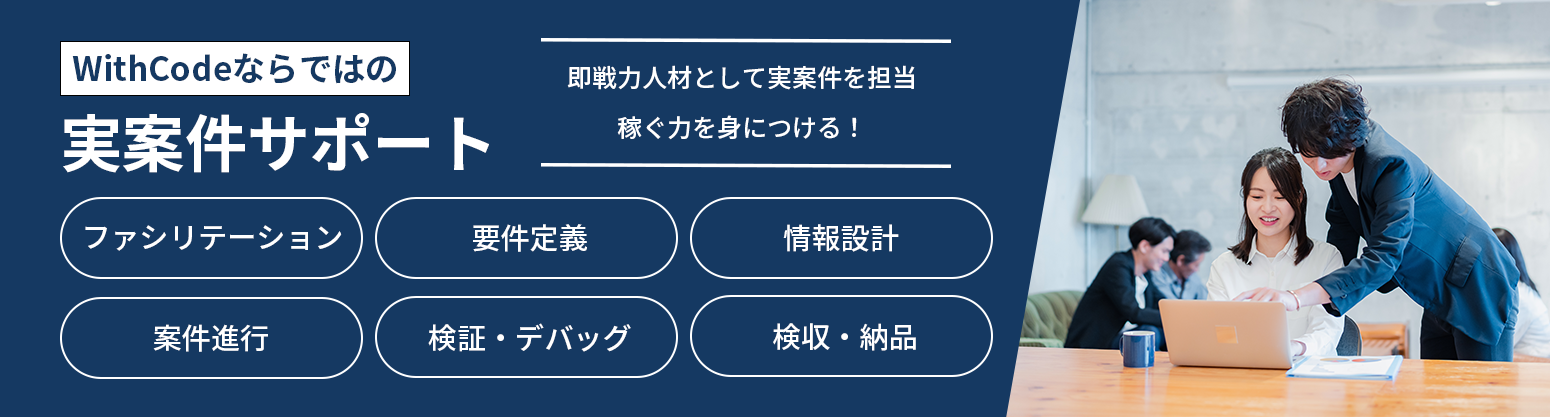



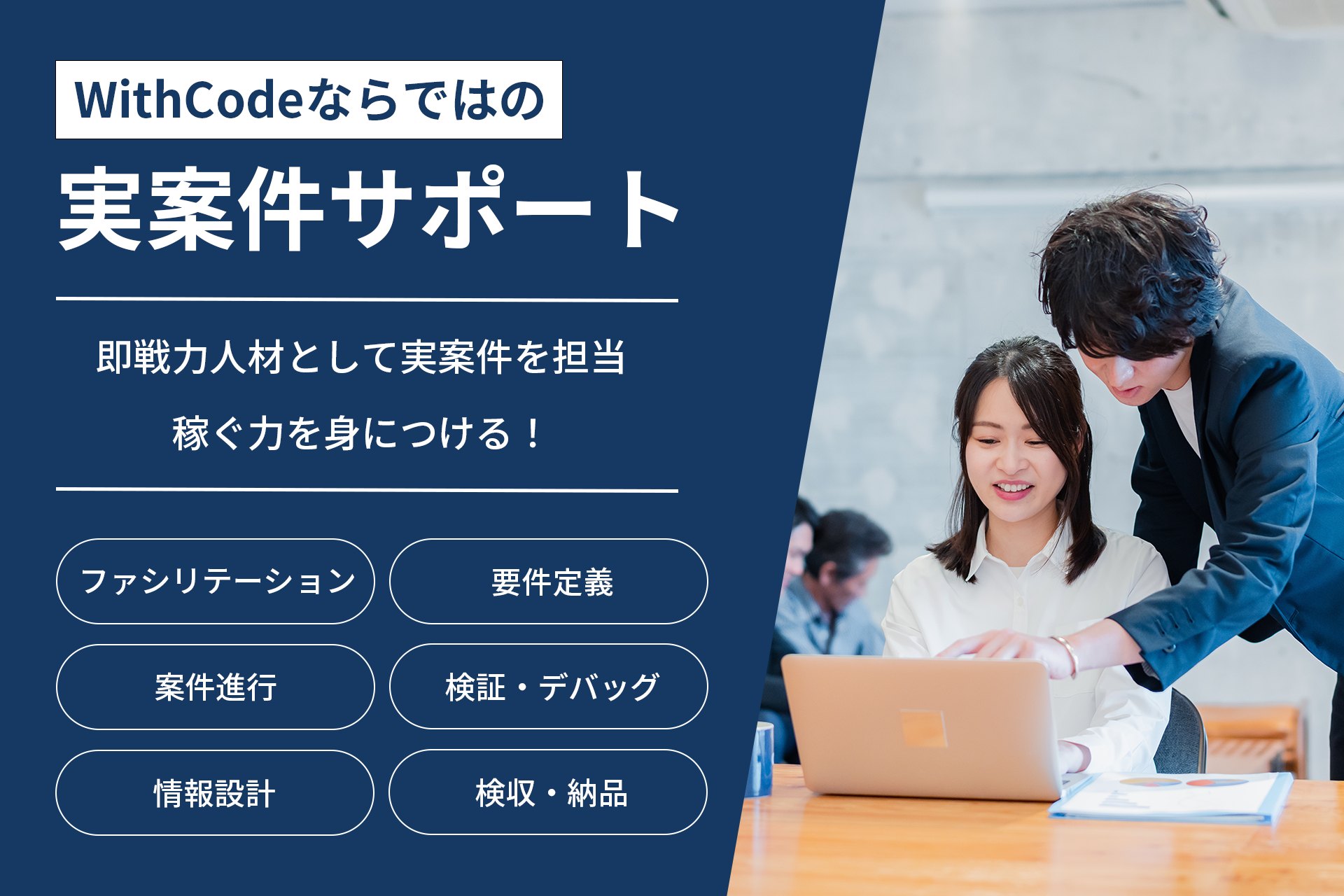
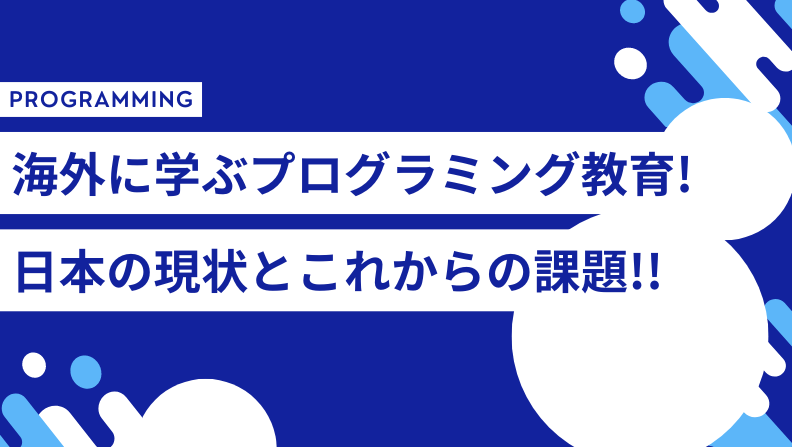
 生徒
生徒ペン博士!海外のプログラミング教育って進んでるって聞いたんですけど、本当なんですか?



うむ、本当じゃ。特にアメリカやフィンランド、イギリスなどでは“プログラミング=創造力を育てる教育”として重視されておる。今回は海外のプログラミング教育の特徴と、日本の現状・課題を比較しながら、今後の学びのヒントを探っていこう。



はい!よろしくお願いします!
「プログラミング教育が日本ではどのように進んでいるのか、そして海外との違いは何なのか知りたい」という疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、そんな疑問を解決するために、海外のプログラミング教育の現状と、日本との違いを詳しく解説していきます。
本記事の内容
「学習→案件獲得」につなげた受講生のリアルな体験談も公開中!
働き方を変えたい方にも響くストーリーです。
内田さん
大学卒業後に結婚を経て、二児を育てながらパートとして勤務。
3人目を妊娠後、将来への不安から、在宅でできる副業を探し始めプログラミングに興味を持つ。
スクールを検討していた中、低価格で実案件までサポートしてくれるWithCodeに出会い受講を決意。約2ヶ月の学習に取り組み、3人目を出産後に卒業テスト合格。
案件対応中の離婚をきっかけに副業から転職に目標を変更。WithCodeで培ったスキルでポートフォリオを作成し就活に励み、無事Webデザイナーとしてアルバイト雇用。
現在は三人の子供を育てながら、時短勤務可能な正社員として活躍しています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。


内田さんの主な制作実績はこちら
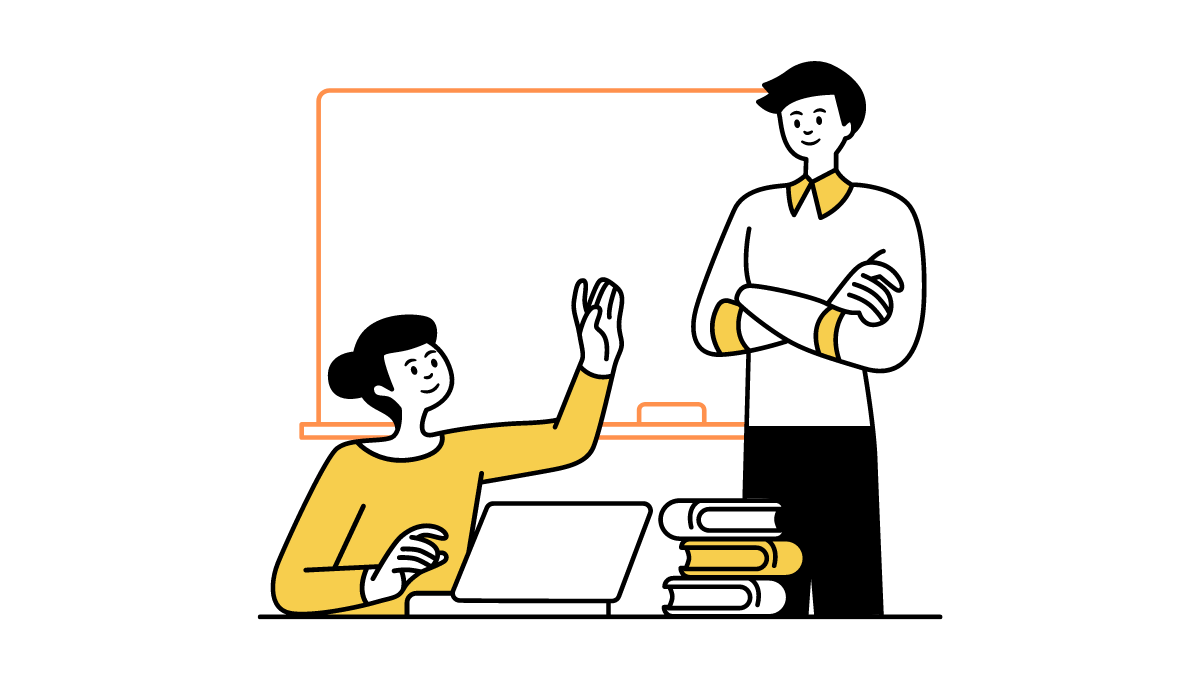
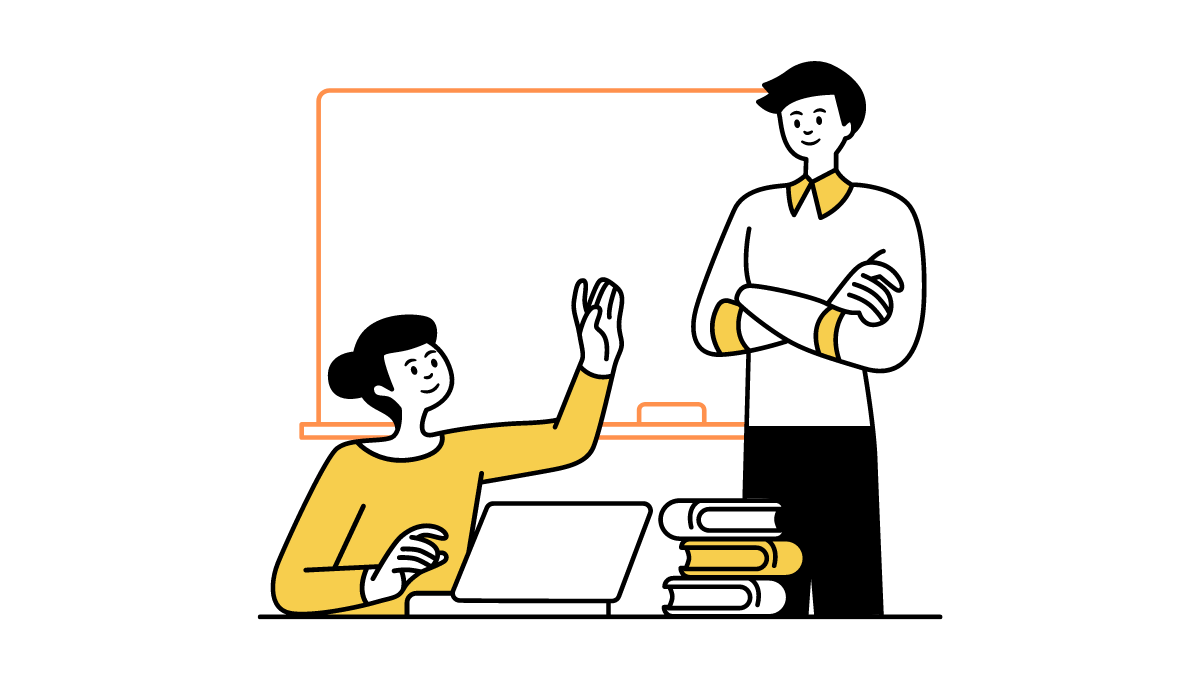
プログラミング教育が世界中で重要視されている理由は、21世紀におけるデジタル社会の発展と密接に関連しています。
現代の社会では、ほぼ全ての業界がデジタル技術に依存しており、その基盤となるプログラミングのスキルがますます求められるようになってきました。
プログラミングは単なる技術習得に留まらず、論理的思考力や問題解決能力を養う手段としても評価されており、未来のリーダーやイノベーターを育成するために、各国がプログラミング教育に力を入れるようになっています。
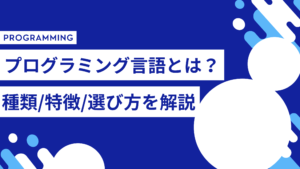
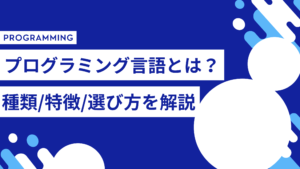
多くの先進国では、プログラミング教育を早期から取り入れています。以下は、主要国におけるプログラミング教育の導入時期の一覧です。
| 国名 | 導入時期 | 年齢層 |
| 日本 | 2020年 | 小学校5年生から |
| イギリス | 2014年 | 小学校1年生から |
| エストニア | 2012年 | 小学校1年生から |
| フィンランド | 2016年 | 小学校1年生から |
| アメリカ | 州ごとに異なるが、多くの州で2013年以降 | 小学校1年生から |
| 中国(上海) | 2015年 | 小学校3年生から |
| デンマーク | 2014年 | 小学校3年生から |
| オーストラリア | 2015年 | 小学校1年生から |
これらの国々では、早期からプログラミング教育を導入し、子どもたちがデジタルリテラシーを自然と身につけられるような教育環境を整備しています。


イギリスは、2014年に全国的なカリキュラムの一環としてプログラミング教育を導入しました。
イギリスの教育システムでは、小学校からコンピューターサイエンスが必須科目となり、子どもたちは若い年齢からプログラミングを学び始めます。
イギリス政府は、このカリキュラムを通じて、次世代のデジタルスキルの向上を目指しています。
エストニアは、ヨーロッパの中でも特に早期にプログラミング教育を導入した国の一つです。
2012年から小学校でのプログラミング教育が始まり、現在ではすべての学生がプログラミングの基礎を学んでいます。
エストニアの教育システムは、ICT(情報通信技術)の活用に非常に積極的で、国内のIT企業と連携して教材を開発しています。
ICT(Information and Communication Technology、情報通信技術)とは?
コンピューターやインターネット、通信ネットワークなどを活用して情報の収集、処理、保存、送信を行う技術のことを指します。簡単に言えば、デジタル技術を使って情報をやり取りしたり、処理したりする仕組みの総称です。
具体的には、スマートフォンやパソコンでのインターネット利用、メールの送受信、SNSの活用、ビデオ会議、クラウドサービスなどがICTの一部であり、ビジネスや教育、医療、日常生活に至るまで、さまざまな分野で活用されており、効率的な情報の伝達や共有を可能にします。
ICTは、情報をより簡単に、そして迅速に扱えるようにするための技術であり、現代社会において欠かせない要素となっています。
フィンランドは、2016年からプログラミング教育を義務教育に組み込みました。
この国の特徴は、プログラミングを単なる技術的なスキルとしてではなく、数学や理科の授業と関連付けて教える点です。
フィンランドの教育モデルは、クリエイティブな問題解決能力を養うことに重点を置いています。
アメリカでは、州ごとにプログラミング教育の導入時期が異なりますが、特に2013年以降、多くの州でコンピューターサイエンス教育が拡充されてきました。カリフォルニア州やニューヨーク州などでは、プログラミングが高校生の必修科目となっており、プログラミング教育が公教育の中で重要視されています。
中国の上海では、2015年から小学校でのプログラミング教育が義務化されました。
中国政府は、国際競争力を高めるために、プログラミング教育を積極的に推進しており、特にAIやビッグデータの分野での人材育成を目指し、プログラミング教育が国の重点政策となっています。
デンマークでは、2014年にプログラミング教育が導入されました。
特にデンマークの教育システムは、学生の創造性を重視し、プログラミングを通じて自らのアイデアを形にする能力を養っています。
また、学校と地域社会が連携してプログラミング教育の支援にも力を入れているようです。
オーストラリアでは、2015年からプログラミング教育が義務化されました。
オーストラリアの教育システムは、実践的なスキルの習得を重視し、プログラミング教育もその一環として位置づけられ、プログラミングを通じて論理的思考力や問題解決能力を高めています。
このように、世界の主要国ではプログラミング教育が急速に普及しており、その重要性が認識されている実情です。
各国の教育政策は、デジタル時代における競争力の向上を目指しており、プログラミング教育の導入が大きな鍵となっています。



国によってプログラミング教育の進め方が全然違うんですね!



うむ、各国の文化や教育方針が反映されておる。ただ、海外の成功例を“形だけ”真似るのではなく、“目的を理解して応用する”ことが大切なのじゃ。
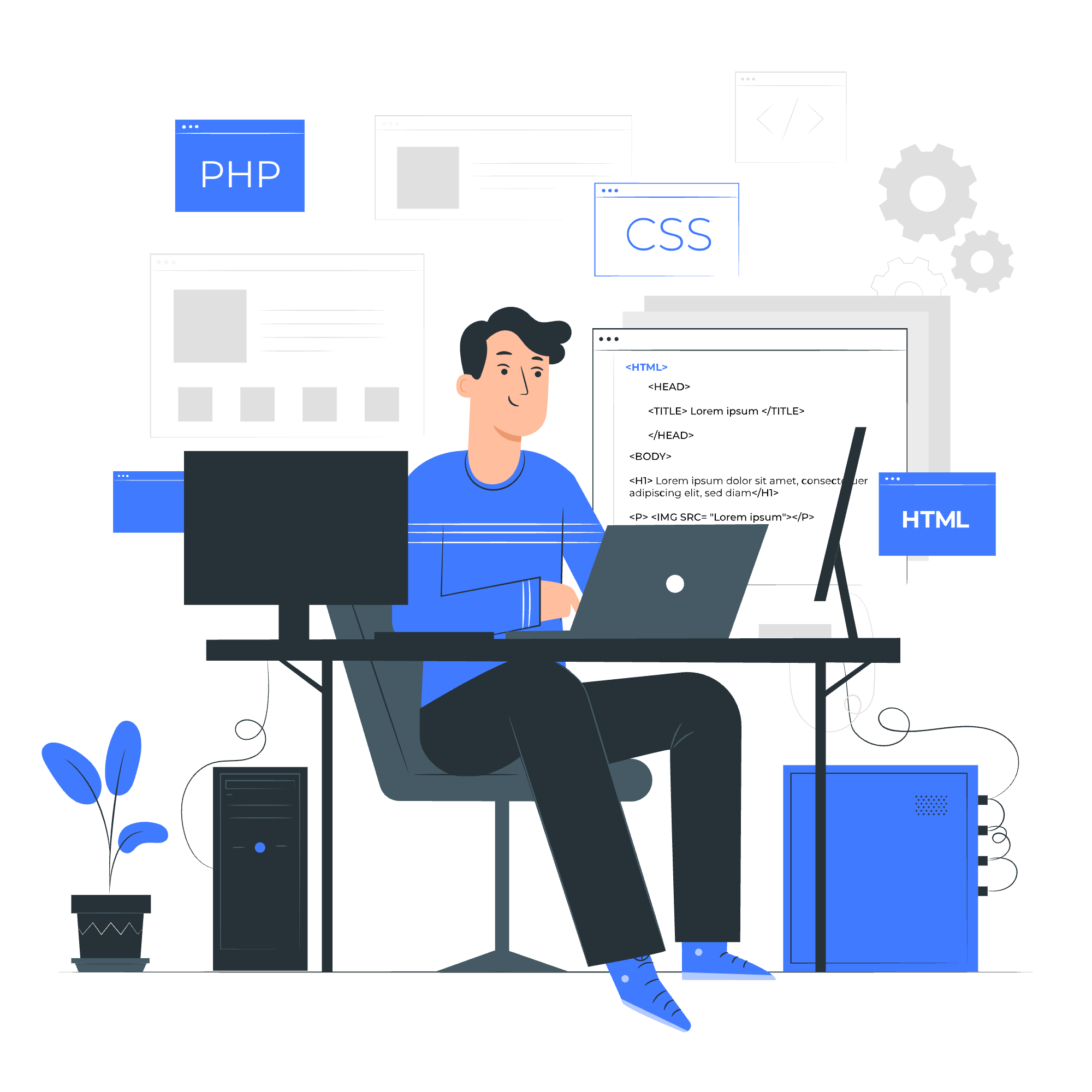
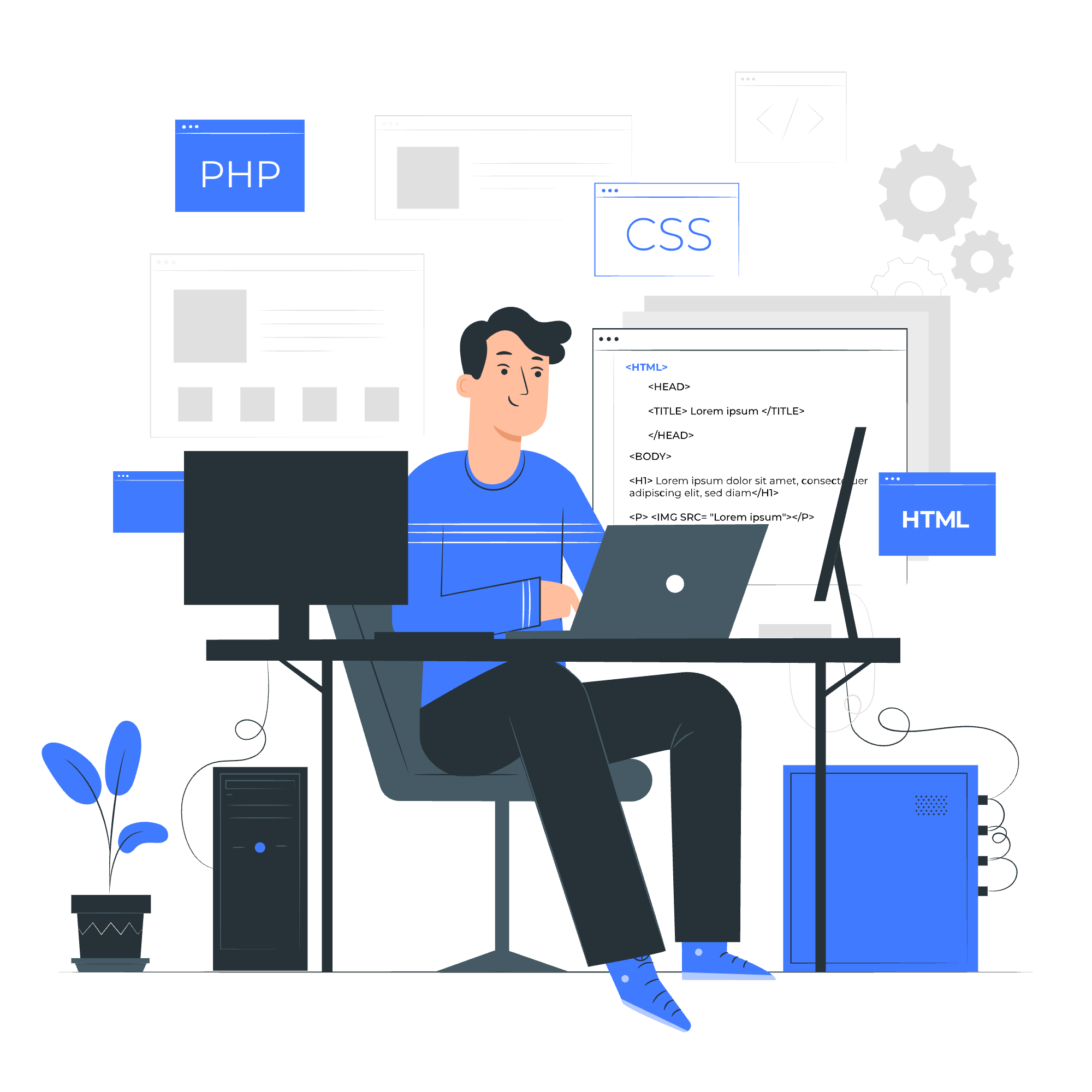
日本では、2020年に小学校5年生を対象にプログラミング教育が必修化されました。
これは、国内外で急速に進むデジタル化に対応し、子どもたちにプログラミングの基礎的なスキルを身につけさせることが目的です。
導入初年度から多くの学校でプログラミング授業が行われていますが、教育内容や実施方法にはまだばらつきがあり、統一されたカリキュラムの整備が求められている現状です。
文部科学省によると、プログラミング教育の主な狙いは「コンピューターを利用した問題解決能力の向上」とされており、簡単なプログラムを作成し、そのプログラムを通じて物事を論理的に考える力を育むことを目指します。
この教育が小学校に導入された背景には、将来の労働市場で求められるスキルとしてのプログラミングの重要性が高まっているという現実があります。
しかし、導入から数年が経過した現在でも、学校間での実施状況には大きな差があり、特に、プログラミングを教える教員のスキルや知識の差が問題視されており、教育の質が一定していない事が課題視されています。
多くの教員が、プログラミングに関する十分な訓練や教育を受けておらず、結果的に授業が表面的な内容にとどまっているのです。
また、プログラミング教育の評価方法についてもまだ確立されておらず、従来の教科と違い、定量的に評価しにくい部分があり、どのようにして生徒の理解度やスキルを評価するかが今後の課題として残されています。



日本ではまだ試行錯誤の段階って感じなんですね。



うむ、まさに“成長期”じゃな。制度としては整ってきたが、教える側の体制や教材の質に課題が残っておる。
日本の小学校でプログラミング教育が導入された目的は、単にプログラムを作る技術を教えるだけではありません。
主な目的は、子どもたちに「論理的思考能力」を育むことです。
これは、プログラミングのプロセスが、問題を段階的に分解し、解決策を導き出す作業を伴うからです。
さらに、プログラミングを通じて、子どもたちは「創造力」や「発想力」を養うことが期待されています。
プログラミングは、与えられた課題に対して単一の解決策があるわけではなく、複数の解決策を模索し、試行錯誤する過程が含まれており、この過程で、子どもたちはご自身なりの発想で問題を解決する力を伸ばしていきます。
もう一つの目的は、子どもたちが「デジタルリテラシー」を身につけることです。
現代社会において、デジタル技術はあらゆる分野で不可欠な要素となっており、その基礎であるプログラミングを理解することは、未来の社会で生き抜くための重要なスキルです。
プログラミングを学ぶことで、子どもたちはデジタル機器を単なる消費者として使うのではなく、創造的に利用する力を持つことができるようになるでしょう。



小学校では“コードを書く”よりも“考え方を学ぶ”のが目的なんですね!



うむ、プログラミング教育の本質は“論理的に考える力”を育てることじゃ。
日本のプログラミング教育にはいくつかの課題があります。
その一つが、教員のスキル不足です。
プログラミングは、これまでの教育カリキュラムには含まれていなかった分野であり、多くの教員が新しい知識やスキルを習得する必要に迫られていますが、教員研修の機会が限られていることや、プログラミング自体が複雑であるため、十分に対応できていない学校が多いのが現状です。
・教員のスキル不足が授業の質に影響
プログラミングに不慣れな教員が多く、授業が操作説明に偏りやすい。
・設備の不十分さ
PCやネット環境が整っていない学校があり、地域間格差が生じている。
・保護者の懸念
基礎学力の低下やデジタル依存への不安の声がある。
これらの課題を解決するためには、教員の研修機会の充実や、設備の整備、さらに保護者への理解促進が求められます。
プログラミング教育が効果的に機能するためには、教育現場と家庭、地域社会が一体となって取り組むことが重要です。
日本のプログラミング教育は、まだ始まったばかりですので、教育現場が抱える課題に対処しつつ、プログラミング教育を推進することが、日本の未来を担う子どもたちの育成にとって不可欠となるでしょう。



日本では先生のスキル不足や地域格差も課題なんですね。



うむ、そして“評価基準の不明確さ”も大きな問題じゃ。ただ、“弱点”ではなく“伸びしろ”と捉えるのが日本教育の進化の鍵じゃ。


日本と諸外国のプログラミング教育を比較すると、その目的やアプローチに明確な違いが見えてきます。
日本では、2020年にプログラミング教育が小学校5年生から必修化されましたが、その主な目的は、プログラミングスキルの習得よりも、論理的思考力を育成することに重きが置かれています。
一方で、諸外国、特に欧米諸国では、プログラミングそのものを「第2の言語」として扱い、実践的なスキルを身につけることを重視しているのです。以下、イギリスの事例を紹介します。
・イギリス
2014年から小学校1年生でプログラミング教育を義務化。
技術習得を通して「問題解決能力」を養うことを目的としている。
・日本
「プログラミングで考える力を育てる」ことに重点を置き、具体的なスキル教育はまだ発展途上。
・OECD調査の結果
日本の小中学生は他国に比べデジタルリテラシーが低く、ICTを活用した問題解決能力でも遅れが指摘されている。
※参考 OECDの学習到達度調査 PISA2022のポイント
このような背景から、日本のプログラミング教育は、諸外国と比較して実践的なスキルの習得には遅れを取っているものの、論理的思考力の育成という点では独自のアプローチを取っていることが分かりますね。
これが日本の教育システムの特徴とも言えますが、今後はより実践的なプログラミングスキルの育成も求められるでしょう。



海外は“体験型”、日本は“座学型”って感じですね!



うむ、まさに本質の違いじゃな。海外は“学びながら遊ぶ”、日本は“理解してからやる”傾向にある。海外の柔軟さを取り入れつつ、独自の強みである“計画性”を活かすのが理想じゃ。
日本と海外の子どもたちのプログラミングスキルやPCスキルを比較すると、技術的な習熟度やその背後にある教育方針に違いが見えてきます。
欧米諸国、特に北欧諸国では、ICT教育が早期から導入されており、小学校低学年からPCの基本操作や簡単なプログラミングに親しんでいる子どもたちが多いです。
・日本の現状
PC・プログラミング教育が十分に行き届いていない。
総務省の調査では、小中学生の約60%が自宅にPCを持たない。
PC操作に不慣れな子どもが多い。
・他国との環境差
アメリカやフィンランドでは、ほぼ全ての学生がPCを使用可能。
早期からデジタルスキル習得が進む。
・スキル面での差
日本の子どもは海外に比べ実践的スキルが遅れ気味。
シリコンバレーやエストニアでは、子どもが自作アプリを開発するなど、高度なプログラミング教育が行われている。
日本におけるプログラミング教育は、2020年にスタートしたばかりであり、まだ試行錯誤の段階にあるため、海外の事例を参考にしつつ、子どもたちのデジタルスキルを向上させるための教育改革が必要になるでしょう。



海外の子どもたちはやっぱりPC操作に慣れてるんですね!



うむ、家庭や学校で触れる機会の多さが大きく影響しておるのじゃ。環境を“与えるだけでなく、使いこなす力を育てる”ことが次の課題じゃな。
日本と海外のプログラミング教育における大きな違いの一つが、「学び方」にあります。
日本では、プログラミング教育が学校の授業の一環として行われることが多いですが、その内容は基礎的なものであり、主にプログラミング的思考を育てることが目的とされています。
プログラミングに関する具体的なスキルは、家庭での学習や民間のプログラミングスクールに委ねられることが多いです。
一方、海外、特に北欧諸国やアメリカでは、プログラミング教育が学校教育の中核に位置付けられており、子どもたちは教室で実際にプログラムを作成する実践的な学びを経験します。
例えば、フィンランドでは「現実世界の問題を解決するためのツールとしてプログラミングを学ぶ」というアプローチが取られており、プロジェクトベースの学習が主流です。これにより、学生たちは自分たちのアイデアを形にする力を養うことができるのです。
また、エストニアでは、全ての学生が全国統一のプログラミングカリキュラムに従って学ぶことが求められており、教師は専門的な訓練を受けたプログラミング教育のプロフェッショナルですが、日本の教育現場では、教員がプログラミングに関して十分な知識を持っていないケースが多く、授業の質にばらつきが生じることが懸念されています。
このように、日本と海外のプログラミング教育の学び方には大きな違いがあり、それが子どもたちのスキル習得に大きく影響している現状です。
日本でも、より実践的で主体的な学びを提供するための教育改革が必要とされており、そのためには、教員の育成やカリキュラムの整備が急務となっています。
このような背景を踏まえると、日本と海外のプログラミング教育には明確な違いがあることが理解できるでしょう。
それぞれの国が持つ教育の目的や社会的背景に基づいて、独自のアプローチが取られていますが、グローバルな視点で見ると、日本のプログラミング教育は今後、さらなる改善と発展が期待されます。



日本ももっと実践的な授業を取り入れてほしいです!



うむ、それがまさに次世代教育のカギじゃ。学ぶだけではなく、やってみることを大事にすることが成長につながるのじゃ。


前述の通り、
日本のプログラミング教育はまだ発展途上であり、今後さらに進化する余地が大いにあります。
2020年に小学校でのプログラミング教育が必修化されたことは大きな一歩でしたが、これはあくまでスタートに過ぎません。
これからの課題としては、教育内容の充実、教員のスキル向上、そして教育環境の整備が求められています。
・教育内容の充実
現在は「論理的思考力の育成」が中心。
実践的なスキル習得のために、より高度な技術教育が必要。
海外の事例を参考に、カリキュラムの更新が求められる。
・教員のスキル向上
多くの教員がプログラミング教育に不安を抱えている。
研修の充実とスキルアップ支援が不可欠。
より質の高い授業を実現する体制づくりが重要。
・教育環境の整備
地方や予算の限られた学校では設備不足が課題。
政府や自治体の支援による環境整備が必要。
すべての子どもたちが平等にプログラミング教育を受けられる環境を整えることが、日本の教育の質を高める鍵となるでしょう。



日本のプログラミング教育もまだまだこれからですね!



うむ、まさに“伸びしろの塊”じゃな。今は他国を追う立場じゃが、数年後には世界のモデルになる可能性もある。教育は一夜で変わらぬが、学ぶ意欲が未来を動かすのじゃ!
今後、日本におけるプログラミング教育はさらに普及し、社会全体に大きな影響を与えるでしょう。
現在、プログラミング教育は主に小学校で行われていますが、これが中学校や高校、さらには大学教育にも広がることで、より高度なITスキルを持つ人材が育成されることが期待されます。
・中学・高校での強化
基礎から応用まで体系的に学べる環境づくりが必要。
PythonやJavaScriptなどを学び、アプリ開発経験を積む機会を拡大。
・大学教育の広がり
情報系以外の分野でもプログラミングが必修化する可能性。
医療・農業・製造業などでのイノベーション促進が期待される。
・社会人教育の普及
キャリアアップ・転職支援のためのプログラミング教育が拡大。
オンライン講座やスクール増加により学習機会が広がる。
・政府・企業の支援
経済産業省の「未来の学校創造推進事業」などが普及を後押し。
プログラミングを新たな“社会リテラシー”として位置づけ。
今後の日本では、プログラミング教育がさらに普及し、それに伴って社会全体のITリテラシーが向上し、日本がデジタル社会に適応することがグローバル競争力を維持するために必要なステップだと考えられます。
教育現場、企業、そして政府が一丸となってプログラミング教育を推進することで、未来の日本を支える人材が育成されることでしょう。



海外では“プログラミング=考える力を育てるもの”として扱われているのが印象的でした!日本でももっと“考える授業”が増えたら、面白く学べそうです!



うむ、まさにそこが本質じゃ。単にコードを書く技術ではなく、“問題を分解して解決する力”こそがプログラミング教育の目的なのじゃ。海外の良いところを取り入れつつ、“日本流の学び方”を築いていくのが理想じゃな。



僕もその変化の波に乗って、学び続けていきます!
ありがとうございました!
今回の記事では、日本と海外のプログラミング教育の違いについて解説しました。要点は以下の通りです。
・海外は実践重視で早期導入
・日本は論理的思考の育成が中心
・日本は今後の発展に期待が必要
プログラミング教育の重要性を理解した今、WithCodeの無料カウンセリングで具体的なステップを踏み出しましょう。無料カウンセリングを受けることで、ご自身やお子様の最適なプログラミング学習方法を見つけられるはずです。ぜひご利用ください。


副業・フリーランスが主流になっている今こそ、自らのスキルで稼げる人材を目指してみませんか?
未経験でも心配することありません。初級コースを受講される方の大多数はプログラミング未経験です。まずは無料カウンセリングで、悩みや不安をお聞かせください!
公式サイト より
今すぐ
無料カウンセリング
を予約!