
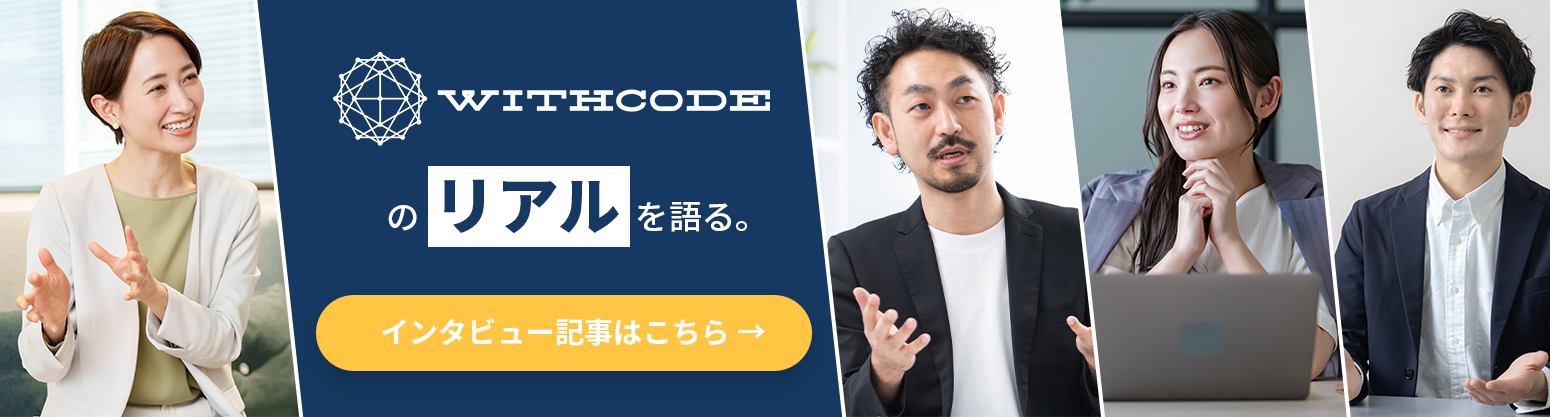
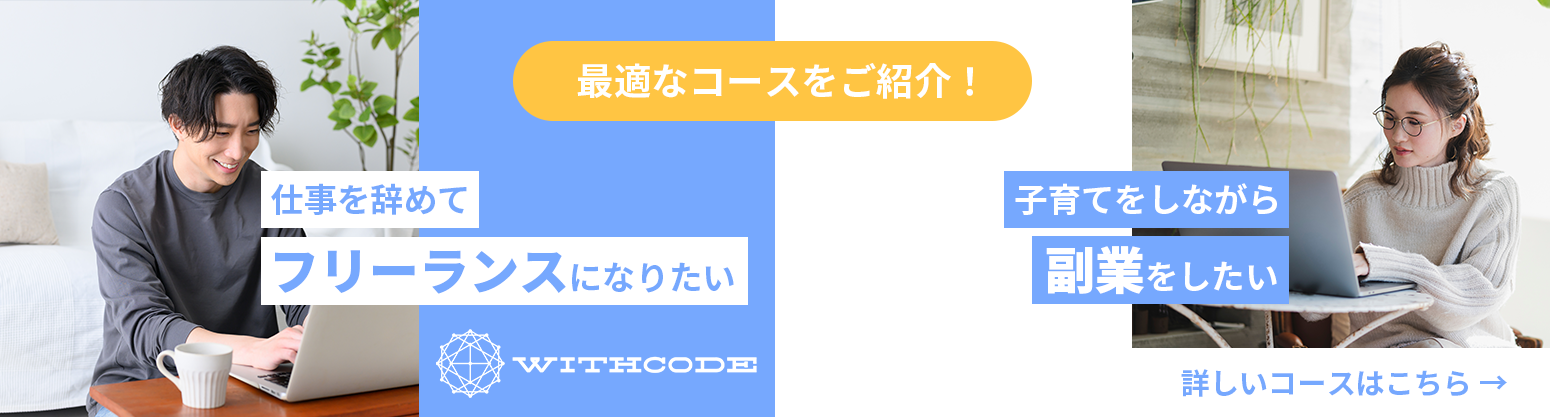
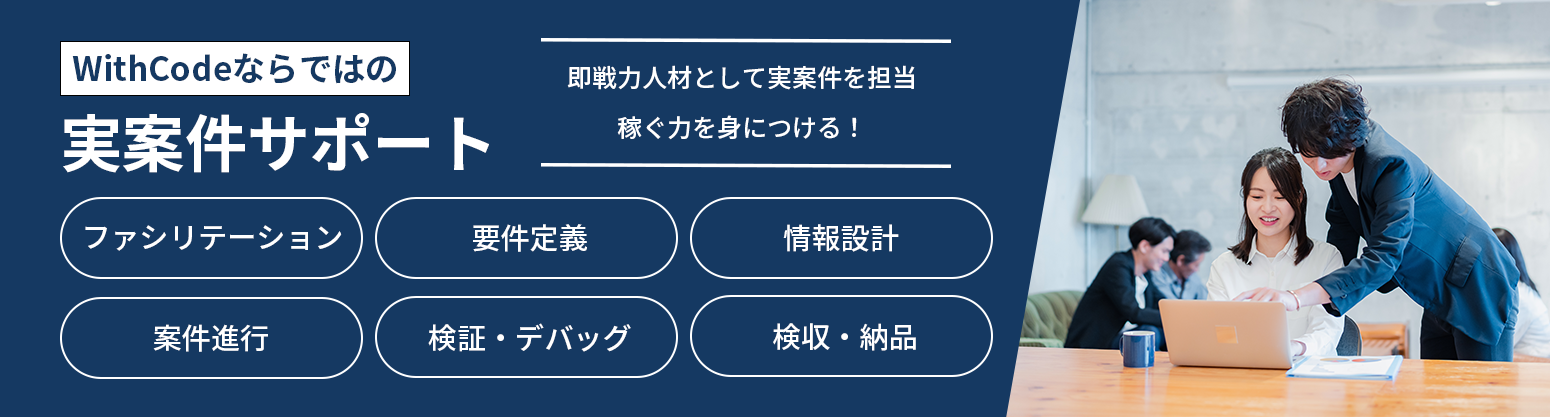
WithCodeMedia-1-pc
WithCodeMedia-2-pc
WithCodeMedia-3-pc
WithCodeMedia-4-pc



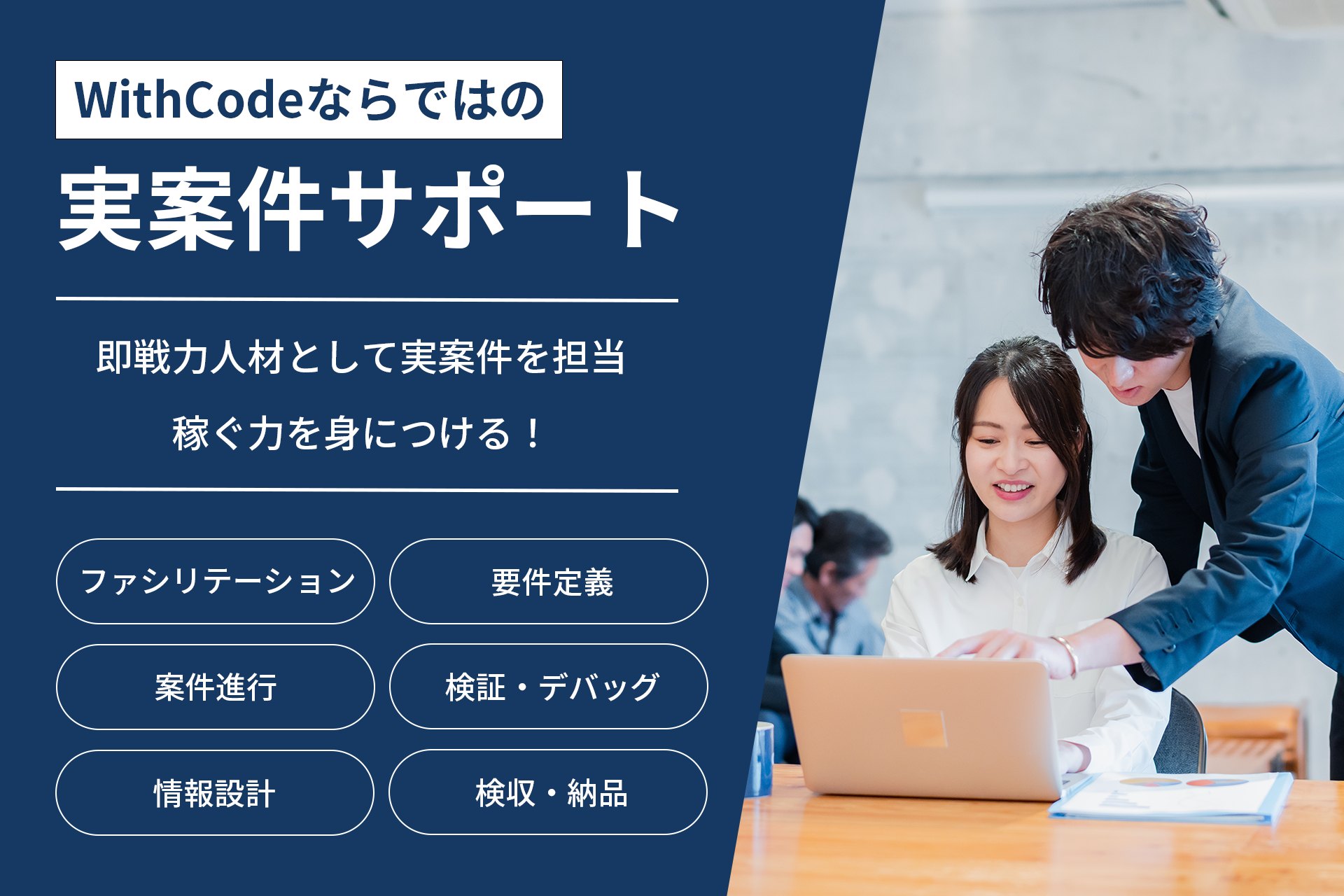
WithCodeMedia-1-sp
WithCodeMedia-2-sp
WithCodeMedia-3-sp
WithCodeMedia-4-sp

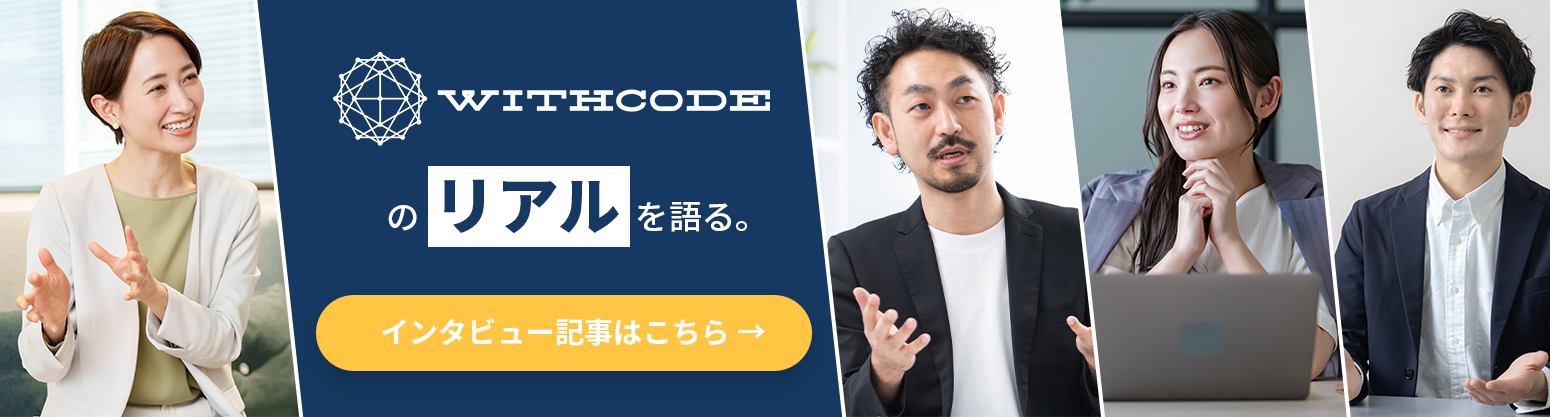
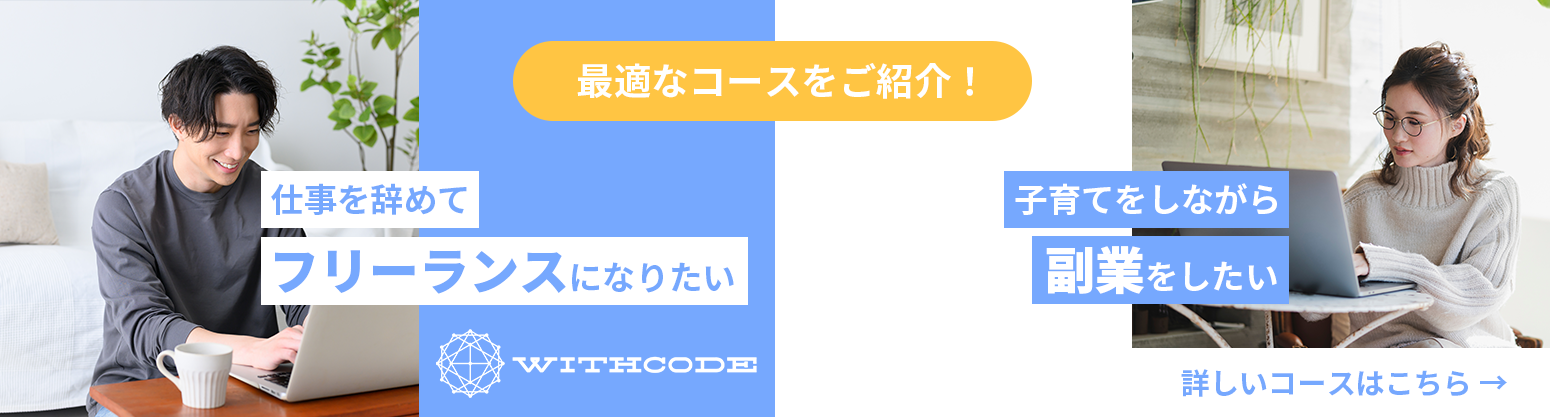
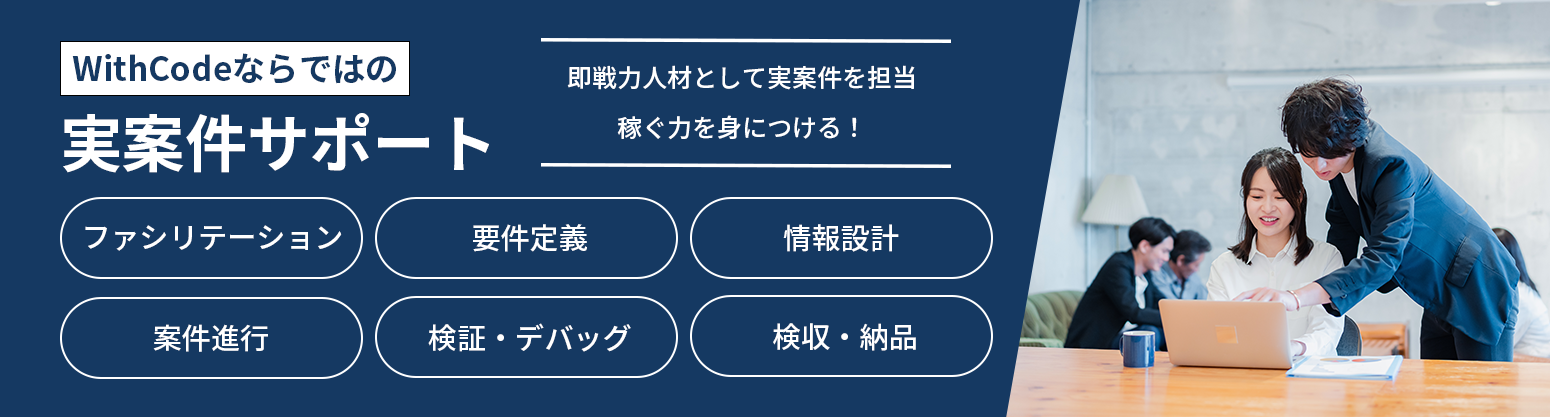



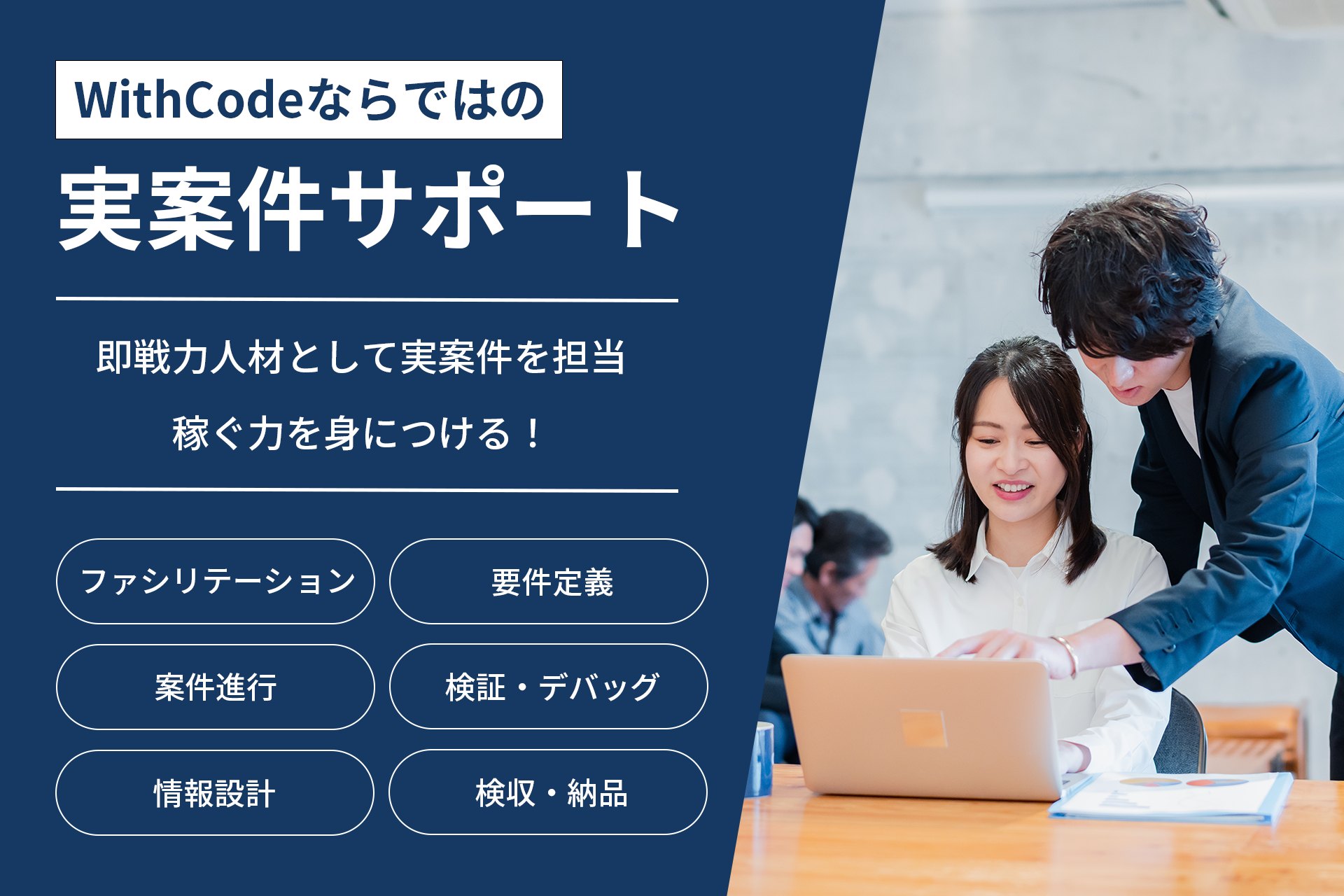

 生徒
生徒ペン博士!SEO対策を始めたいのですが、何から手をつければいいのか分からなくて困っています…



SEO検索で見つけてもらうための工夫じゃ。
まずは仕組みを知り、正しい順序で対策を進めることが大切なんじゃ!しっかり覚えていくんだぞ!



そうなんですね!ありがとうございます!
Webサイトを作ってもアクセスが伸びない原因は、SEO対策が挙げられます。
SEO(検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索結果で上位に表示されるために欠かせない基本施策です。
本記事では、検索エンジンの仕組みや評価の仕方を分かりやすく解説します。
「学習→案件獲得」につなげた受講生のリアルな体験談も公開中!
働き方を変えたい方にも響くストーリーです。
堀さん
働く場所や時間に縛られない生活を送りたいと考え、独学でプログラミング学習を開始するもレベルの差を感じ、WithCodeに入会されました。カリキュラムを進めた結果、見事卒業テストを合格し、現在は、WithCode Platinumで副業として案件を担当しています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
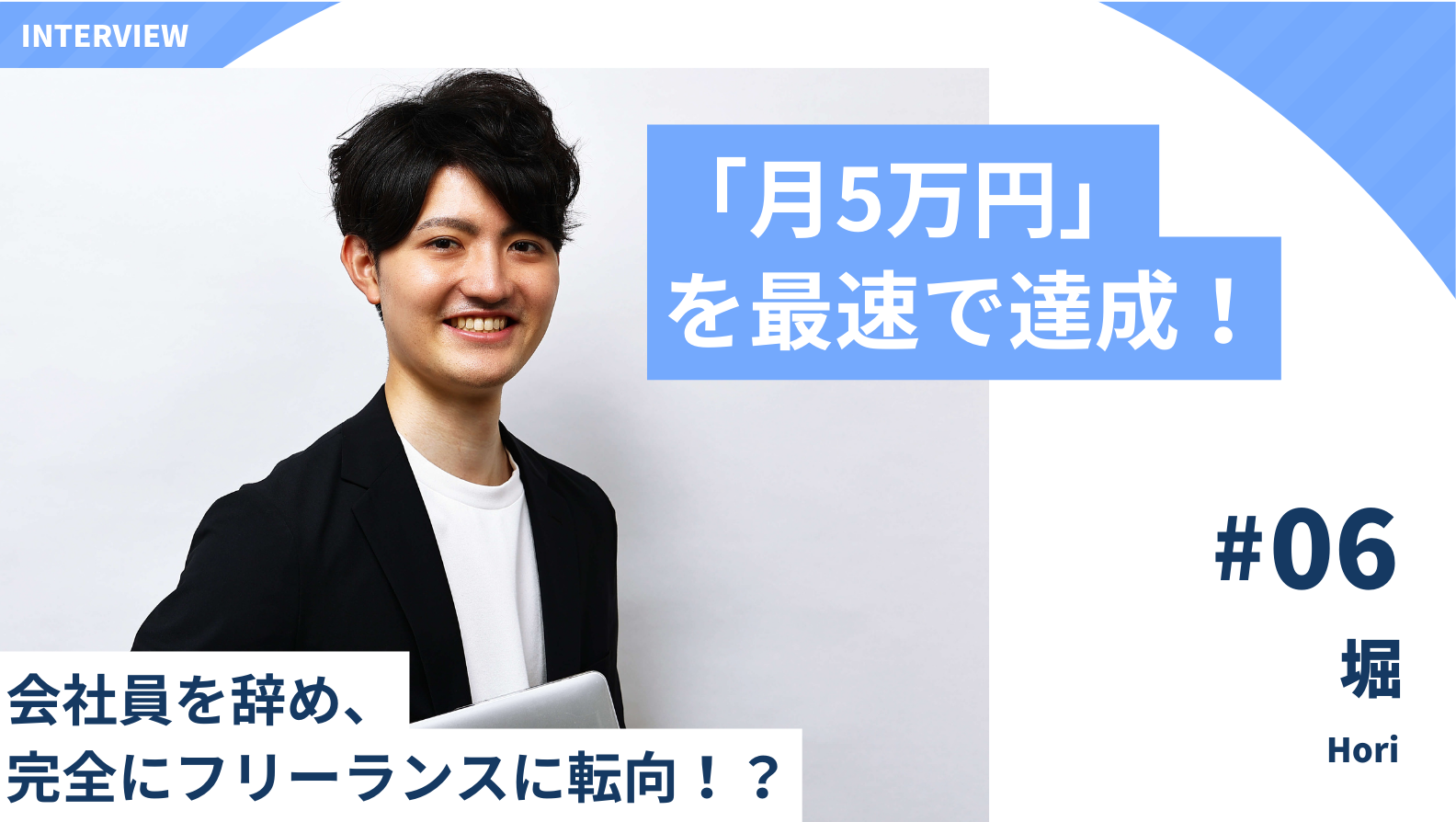
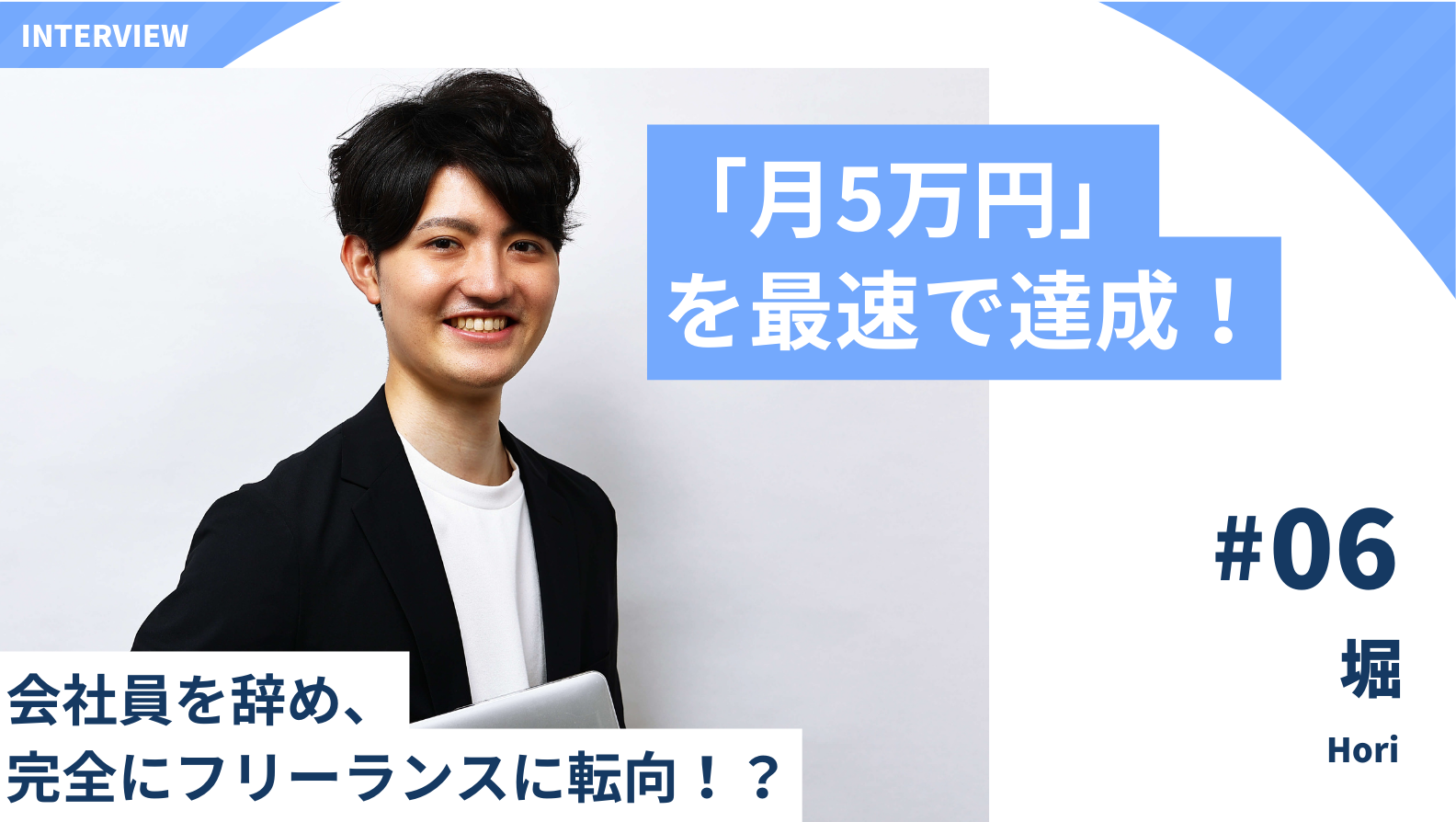
堀さんの主な制作実績はこちら
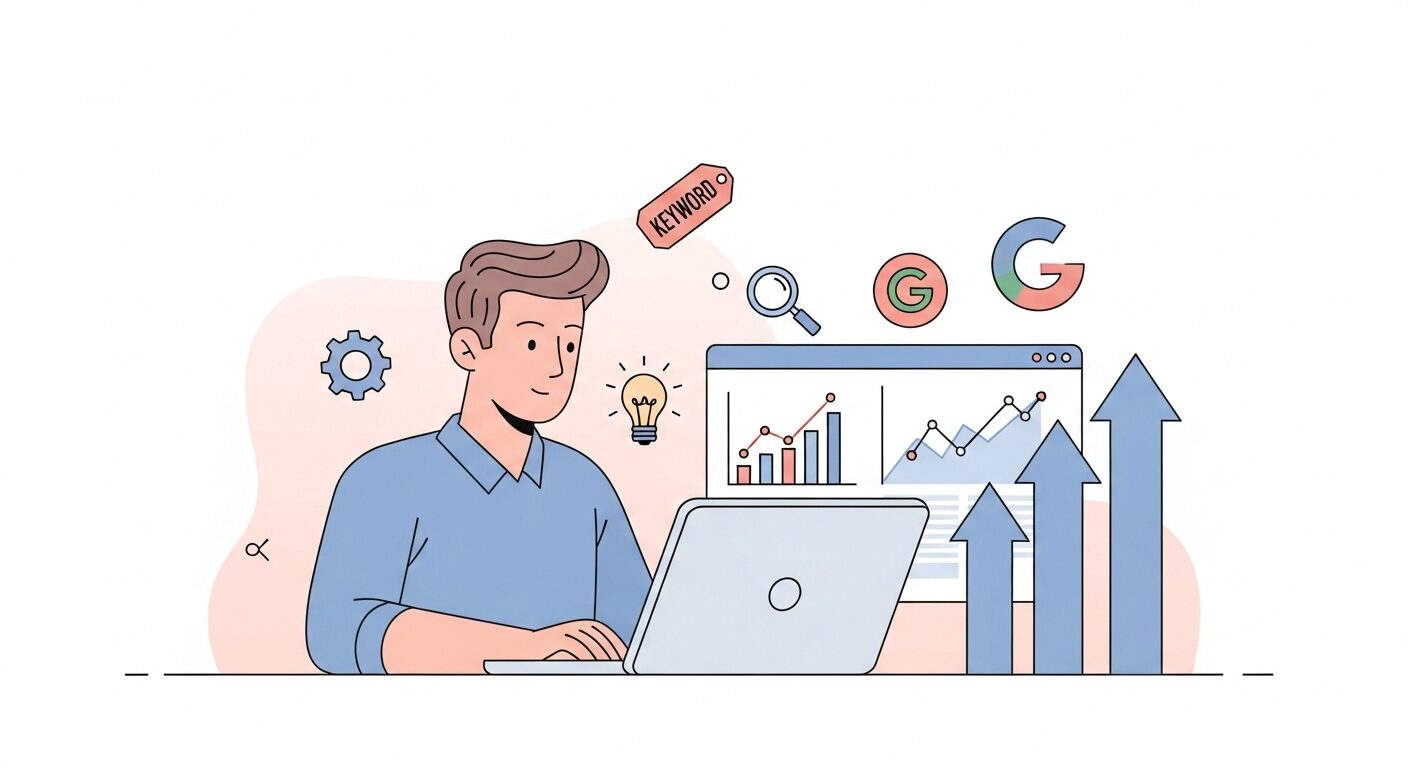
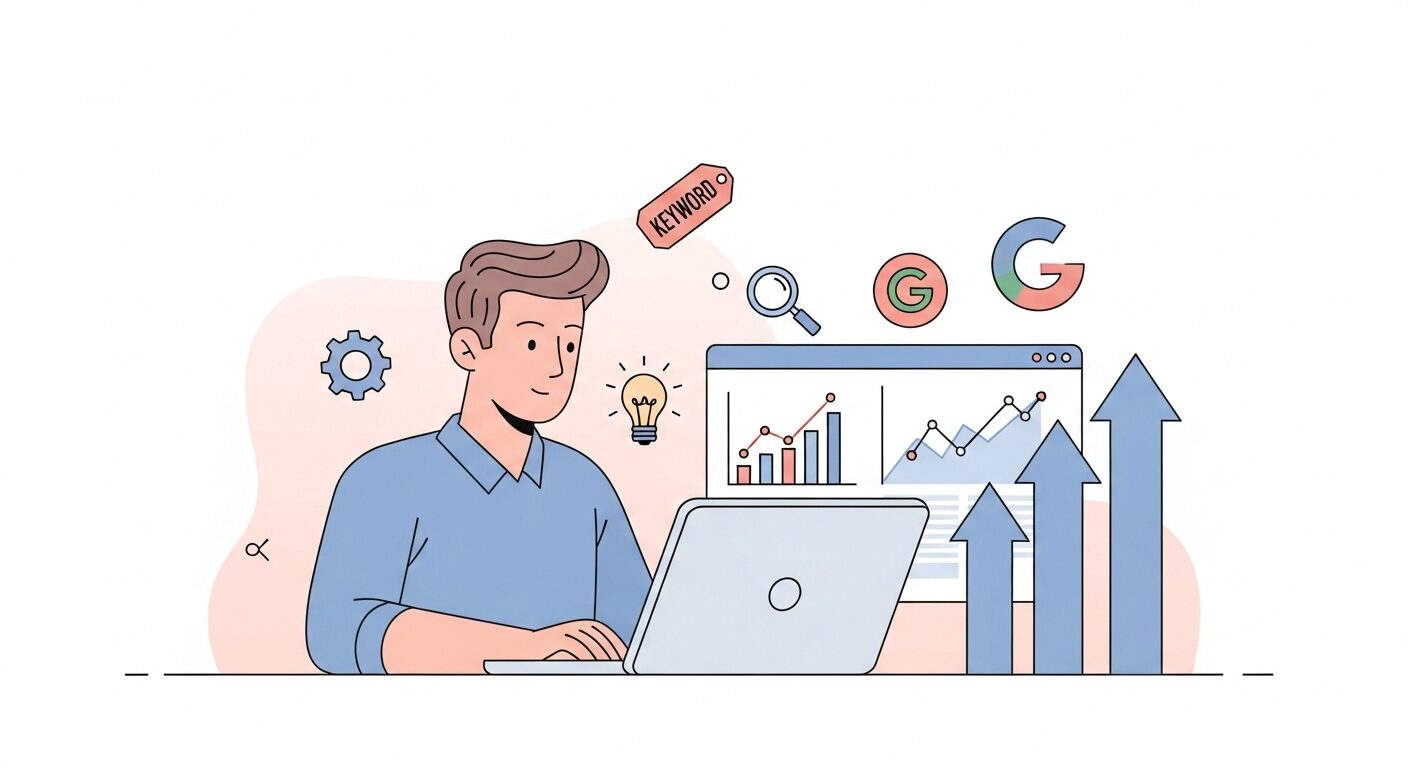



Webサイトを多くの人に見てもらうには、Googleなどの検索結果で上位に表示されることが必要不可欠。
その仕組みを理解するうえで最初に押さえておきたいのが「SEO(検索エンジン最適化)」じゃ。
ここでは、SEOの意味と、効果的な対策を行ううえで欠かせない考え方を解説するぞ!
SEO(Search Engine Optimization)とは、日本語で「検索エンジン最適化」と呼ばれます。
Googleなどの検索エンジンで上位に表示されるよう、Webサイトを改善する取り組みのことです。
インターネット上には膨大な数のWebページが存在しますが、ほとんどのユーザーは検索結果の1ページ目しか見ません。
つまり、上位に表示されるかどうかがWebサイトのアクセス数を大きく左右するのです。
例 :Aさんが「健康食品」を扱うサイトを運営していると仮定。
→ユーザーが Google で「健康食品」と検索したとき、Aさんが運営しているサイトが上位表示されれば多くの人が訪問。
この上位表示を目指す仕組みづくりが SEO の目的です。
さらに、Google に「信頼できる情報源」と判断されることが
SEO における最も重要な本質です。
検索エンジンは、ユーザーの検索意図に最も合致し、有益な情報を提供するページを上位に表示します。
したがって、単にキーワードを詰め込むだけではなく、ユーザーの課題を解決する価値あるコンテンツを提供することが何より重要です。
SEO対策における最重要の考え方は、「ユーザーファースト」と「検索エンジンフレンドリー」を両立させることです。
ユーザーファースト
ユーザーが求める情報をわかりやすく・正確に提供する姿勢のこと。
検索エンジンフレンドリー
Google のクローラー(情報収集ロボット)がページ内容を正しく理解できる構造 を整えることを指す。
読みやすく整理された文章構造、正しいHTMLタグの使い方、そしてモバイルでも見やすいデザインなど、これらすべてが評価対象となります。



なるほど…!SEOって、検索エンジンに気に入られるように工夫することなんですね。
でも、ユーザーにとっても読みやすい内容にしなきゃ意味がないんだ!



その通りじゃ。検索エンジンはユーザーにとって役立つ情報を上位に出すんじゃ。
検索エンジンとユーザー、どちらにも優しいサイトを目指すのが本当のSEOじゃぞ!
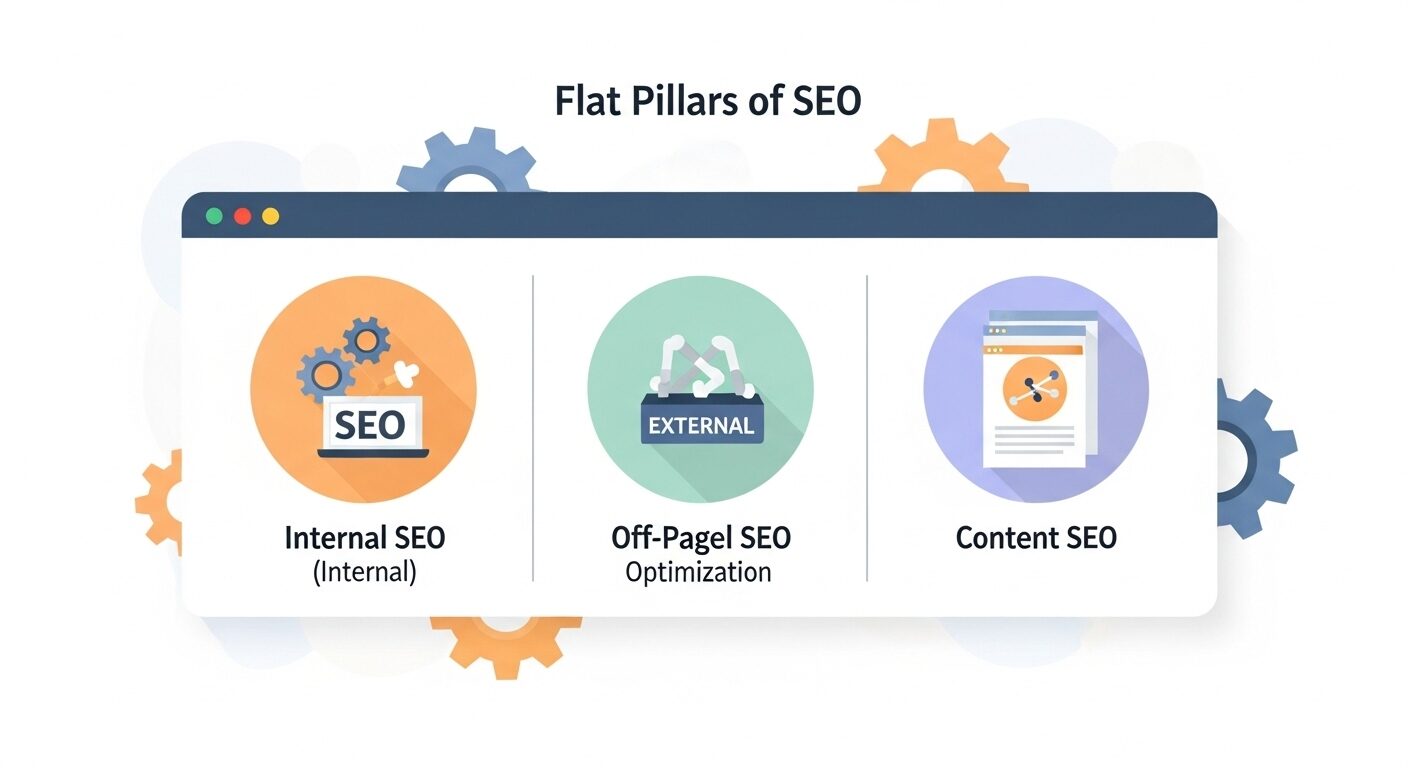
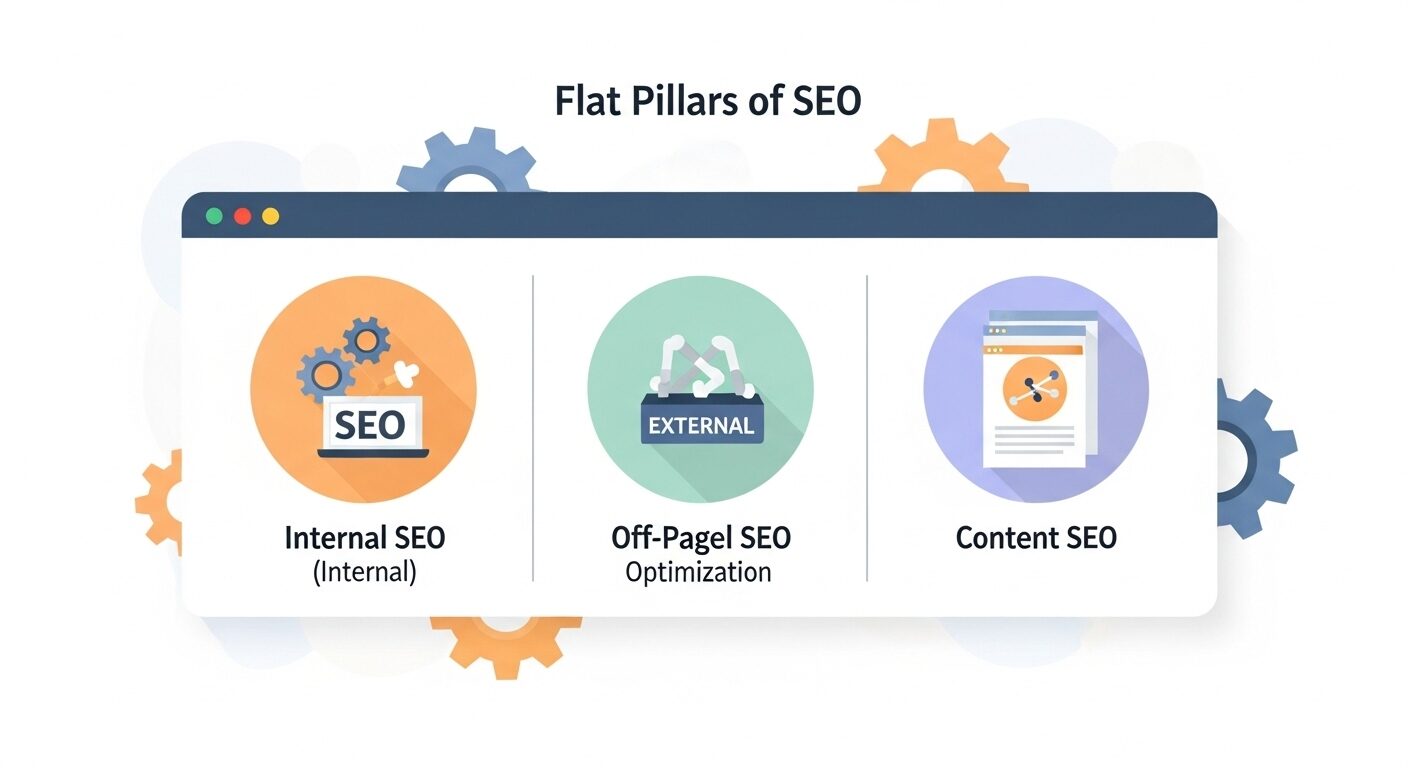



SEOは「内部対策」「外部対策」「コンテンツSEO」の3本柱で構成される。
初心者の方は、まずこの3要素を理解するところから始めよう!
内部対策とは、Webサイト内部の構造を最適化することです。
クローラーが効率よく情報を収集できるようにし、サイト全体の評価を高めます。
外部対策は、ご自身のWebサイトが他の信頼あるサイトから評価される仕組みを作ることです。
Googleは、被リンク(外部サイトからのリンク)を「信頼の投票」とみなしています。
コンテンツSEOとは、Webサイトの中身そのものを最適化することです。
検索エンジンが評価するのは「ユーザーにとって有益かどうか」です。



SEOって、外からのリンクだけじゃなくて中身も大事なんですね!
やることが多くて少し大変そうです…。



その通りじゃ。内部・外部・コンテンツ、この3つをバランスよく整えるのがコツじゃ。
土台(内部)を固めてから、信頼(外部)と価値(コンテンツ)を育てるんじゃ!





SEOを成功させるためには、Googleがどのような基準でページを評価しているかを理解することが欠かせん。
特に「E-E-A-T」「YMYL」「MFI」は、Googleの品質評価ガイドラインの中でも最重要とされる3つの概念じゃ。
これらを意識してサイトを作ることで、検索結果での上位表示につながるぞ!
E-E-A-Tは、Googleがコンテンツ品質を判断するための4つの指標をまとめた考え方です。
具体的には以下の4項目から構成されています。
これら4つの要素を満たしたコンテンツは「ユーザーの役に立つ」と評価され、検索順位にも良い影響を与えます。
YMYLとは「あなたのお金、または人生に関わる内容」を意味する概念です。
健康、医療、金融、法律、教育など、人の生活や幸福に大きく関わる情報を扱うページが該当します。
この領域では、誤った情報を発信するとユーザーに深刻な影響を与える可能性があるため、Googleは特に厳しい基準で審査します。
YMYL分野で高く評価されるためには、以下のような対策が必要です。
例えば、「税金の申告方法」や「健康サプリの効果」といったテーマでは、正確性と根拠が欠かせません。
MFI(Mobile-First Index)は、Googleが「モバイル版のページを検索評価の基準にする」という方針です。
かつてはPCページを基準に評価していましたが、現在はスマートフォンでの閲覧体験を最優先しています。
モバイルでの表示崩れや読み込み遅延は、検索順位の低下につながります。
次のポイントを押さえて最適化しましょう。
モバイル対応はSEOだけでなく、ユーザー満足度の向上にも直結します。



E-E-A-TとかYMYLって、なんだか難しそう…!
全部意識しないとSEOで評価されないんですか?



全部が繋がっとるんじゃ。専門性と信頼性を高め、スマホでも見やすくする。
この3つを押さえれば、Googleから「良いサイトじゃ」と認められるんじゃぞ!



SEOの基礎を理解するうえで、まず押さえるべきなのが「検索順位がどのように決まるのか」という仕組みじゃ。
その根本となるのが「クロール → インデックス → ランキング」という3つのプロセスなのじゃ!
Googleのクローラー(bot)は、世界中のWebページを常に巡回しています。
新しいページや更新されたページを自動的に見つけ、内容を読み取ってデータベースに送ります。
クロールによって収集された情報はGoogleのデータベースに登録されます。
これが「インデックス(Index)」と呼ばれる段階です。
最後に、Googleがインデックスされたページを評価・順位付けします。
このとき基準となるのが「検索クエリとの関連性」と「ページの品質」です。
例えば、「SEO 初心者」と検索した場合、Googleは次のような観点から上位表示するページを選びます。
つまり、単にキーワードを詰め込むだけでは上位表示はできません。
「ユーザーにとって価値があるかどうか」が、最も重要な判断基準となるのです。



なるほど…!検索結果って、こんな風に仕組みがあったんですね。
ただ人気順じゃないんだ!



その通りじゃ。「関連性」と「品質」、そして「使いやすさ」が三位一体になって順位を決めとるのじゃ。



検索アルゴリズムは年々進化しており、従来のテクニック中心のSEOからユーザー体験中心のSEOへと変化している。
ここでは、特に重要視されている3つの要素を解説するぞ!
GoogleのAI技術(BERT・MUM・Geminiなど)の発展により、検索エンジンは「単語」ではなく「文脈」や「目的」を理解できるようになりました。
つまり、キーワードの数ではなく、検索意図(インテント)に沿ったコンテンツが上位に表示される時代です。
例
・「SEO 初心者」と検索したユーザーの意図
「SEOの手順を知りたい」
「具体的に何をすればいいか知りたい」
・「SEO ツール 無料」と検索したユーザーの意図
「無料で使えるSEO分析ツールを比較したい」
このように、キーワードの背景にあるユーザーの思考を読み解くことが大切です。
また、単なるまとめ記事ではなく、自身の知見や体験を踏まえた内容が求められます。
SEOは「検索結果に出すための施策」ではなく、「サイトを使いやすくするための設計」でもあります。
特にGoogleが公式に重視しているのが Core Web Vitals(コアウェブバイタル) という指標です。
Core Web Vitalsでは次の3つの要素が測定されます。
| 指標名 | 内容 | 理想値 |
|---|---|---|
| LCP(Largest Contentful Paint) | ページの主要コンテンツが表示されるまでの時間 | 2.5秒以内 |
| INP(Interaction to Next Paint) | ユーザー操作に対する反応速度 | 200ms以下 |
| CLS(Cumulative Layout Shift) | レイアウトのズレ(視覚的安定性) | 0.1未満 |
これらを改善することで、ユーザーのストレスを軽減し、離脱率を下げることができます。
快適な操作性こそが、SEOの成果を最大化する鍵となるでしょう。
近年では、ChatGPTのような生成AIやSiriなどの音声検索が急速に普及しています。
従来のテキスト検索とは異なり、音声では「自然言語(話し言葉)」が中心となるため、文体や構造の工夫が必要です。
例えば、「SEOとは何ですか?」と話しかけたとき、自然なQ&A形式で明確に答えているページは上位に表示されやすくなります。
そのため、以下のような施策が効果的です。



最近はAIとか音声検索も関係してるんですね!
昔みたいにキーワードを詰め込むだけじゃ通用しないのか…。



その通りじゃ。今のSEOは検索意図と体験がすべて。
AIにも人にも伝わる構成を作るのが、これからの時代のSEOなんじゃ!
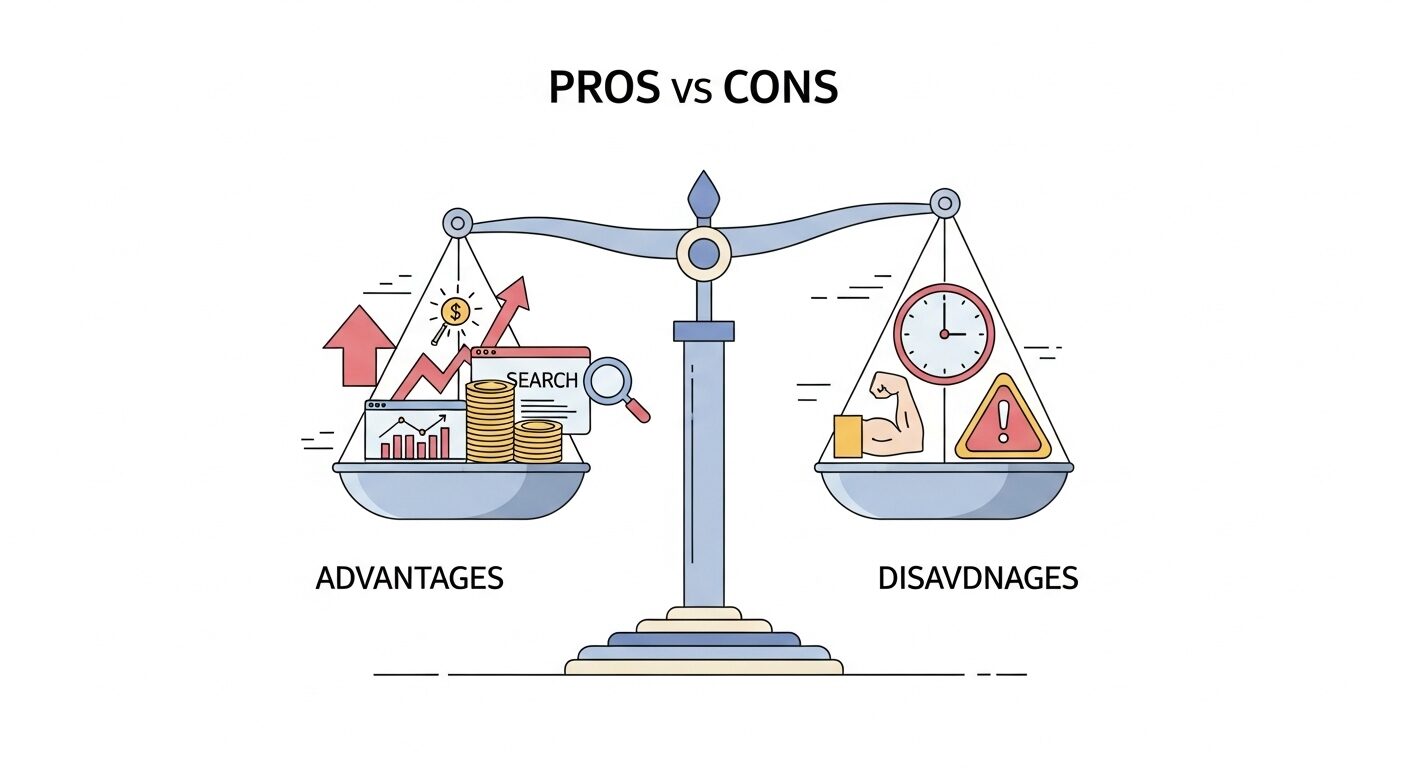
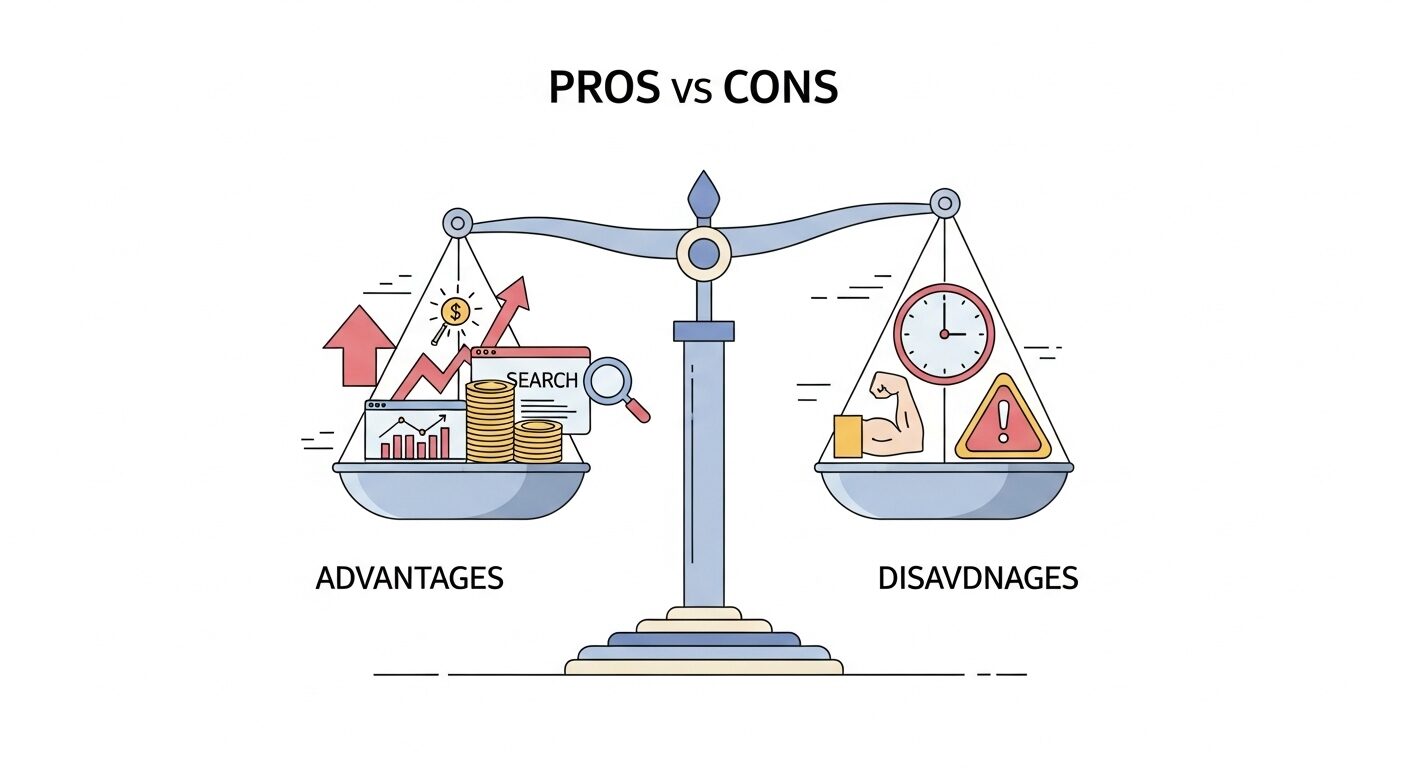



SEOには大きなメリットがある一方で、短期的な効果を求めすぎると失敗しやすい側面もある。
ここでは、実践前に押さえておくべき利点と注意点を整理するぞ。



SEOって効果が出るまで時間がかかるんですね…。
ちょっと根気がいりそうです。



うむ、育てる農業のようなもんじゃ。
じっくり続ければ、長く実を結ぶ資産になるんじゃぞ!





SEO対策はやみくもに始めても成果につながらない。
まずは現状を数値で可視化し、正しい方向に改善を積み重ねるための「分析環境」を整えることが大切じゃ。
この下準備が、その後の戦略や優先順位、そして施策の精度を大きく左右するぞ。
Googleサーチコンソール
検索キーワード(クエリ)、クリック率(CTR)、平均掲載順位、表示回数、インデックス状況、モバイルの使いやすさなどが把握できます。
特に「どんな検索語で表示・クリックされているか」を明らかにできる点が大きな利点です。キーワードの手応えを見ながら、次に伸ばすべきテーマを判断するとよいでしょう。
Googleアナリティクス
集客チャネル別の流入、ユーザー属性、ページごとの滞在・離脱、コンバージョンまでの導線を確認できます。
「読まれている記事」や「離脱が多い箇所」を特定することで、体験面の課題を把握しやすくなります。
ここでは、取得したデータをもとに、サイトの強み・弱み、そして成長のチャンス(機会)を整理していきます。
重要なのは、感覚ではなく数値に基づいて意思決定を行うことです。
アクセス数やクリック率、離脱率などの指標を根拠に、どこを改善すれば成果につながるのかを見極めましょう。
分析を進めるうえで、よくある問題のパターンを整理すると理解しやすくなります。
次のような「症状」と「改善策」を対応させて考えると、課題を素早く特定できます。
こうして課題を洗い出したら、次にやるべきは優先順位をつけることです。
限られた時間とリソースを最大限活かすには、「どの改善が最も成果に影響するか」を見極める必要があります。
判断基準として、「影響度(潜在的な流入数)」「実装にかかる工数」「緊急度(季節・キャンペーンなど)」の3軸で考えると整理しやすいです。
また、改善を始める際は明確な目標を設計しましょう。
例として、以下のような数値目標を設定できます。
「3か月で自然検索からのコンバージョン数を25%増やす」
「主要記事10本のCTRを平均1.2ポイント向上させる」
このように 具体的な数値目標 を立てることで、
進捗を正確に測定できる ようになります。
改善は一度で完結するものではなく、小さな施策 → 結果の確認 → 次の改善という短いサイクルを繰り返すことが重要です。
この継続的なプロセスこそが、SEO成功の最短ルートといえます。



なるほど…!SEOって、記事を書くだけじゃなくて、最初に分析やツール設定も大事なんですね!
数字を見ながら改善するって、ちょっとプロっぽくてワクワクします!



その通りじゃ。SEOは勘ではなくデータで育てるんじゃ。
最初に環境を整え、仮説→検証→改善を繰り返す──これが本当のSEO運用じゃぞ!
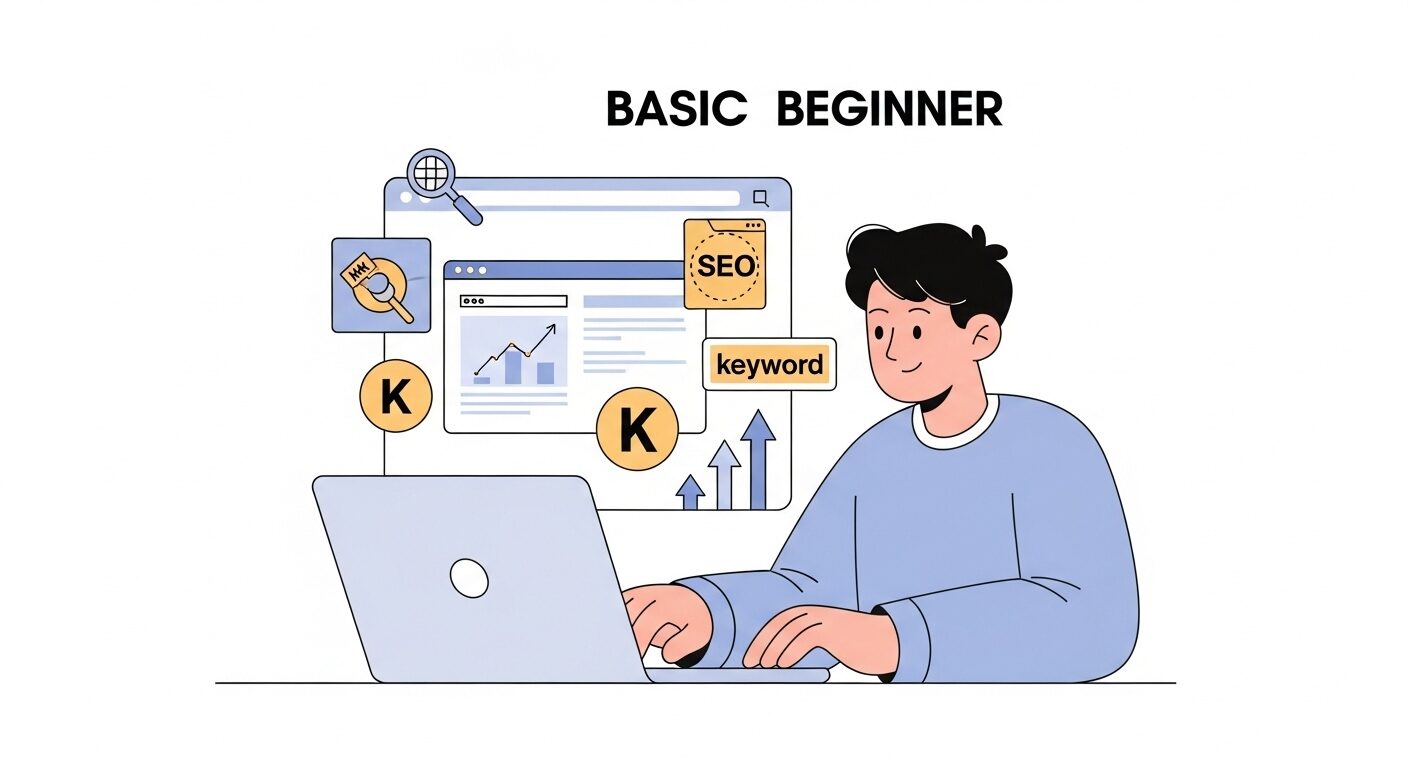
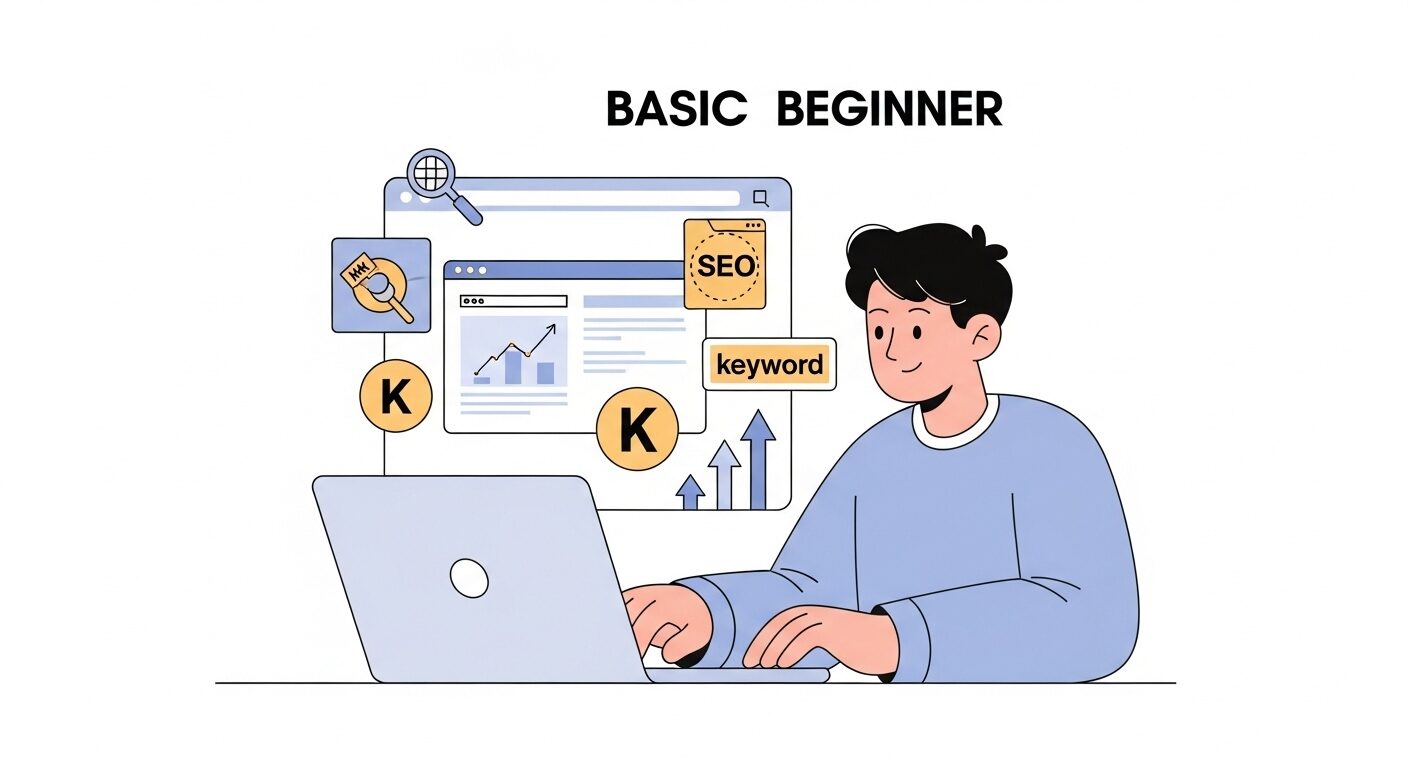



SEOの準備が整ったら、いよいよ改善に取りかかるのじゃ!
ここでは、初心者でも今日から実践できる7つの基本施策を解説するぞ。
最初に取り組むべきは、コンテンツの方向性を決める「キーワード選定」です。
ご自身が書きたいテーマではなく、ユーザーが実際に検索している言葉に合わせることが基本となります。
例えば、「ホームページ 作り方 初心者」や「SEO 対策 すぐできる」といった、意図が明確な言葉が効果的です。
検索ボリュームや競合の強さを確認し、「知りたい」「比較したい」「購入したい」など、検索目的を理解することが大切です。
キーワードの選び方ひとつで、記事の流入数は大きく変わります。
正確な設計が、SEOの基盤となる第一歩です。
次に意識すべきは、検索結果に表示されるタイトルとメタディスクリプションです。
これらはユーザーがクリックするかどうかを左右する重要な要素です。
タイトルには主要キーワードを自然に含め、内容が一目で伝わるようにしましょう。
例えば、「SEO対策とは?」よりも「SEO対策の基本と今すぐできる改善7選」の方がクリック率は上がります。
メタディスクリプションはおよそ100文字前後が理想です。
ページの要点を簡潔にまとめ、「このページで何がわかるか」を明確にするとクリック率の改善につながります。
URLは検索エンジンにもユーザーにも読まれる住所です。
短く、意味のある単語で構成すると内容が正確に伝わります。
例えば、「/seo-beginner-guide」のように英単語をハイフンでつなぐと、Googleがテーマを理解しやすくなります。
反対に、数字や記号が並んだURLは評価が下がる傾向があります。
内部リンクとは、同じサイト内のページ同士を結ぶリンクのことです。
関連性の高いページを正しく結ぶことで、クローラーがサイト構造を理解しやすくなります。
リンクテキストには「こちら」や「詳しく見る」などの曖昧な言葉ではなく、リンク先の内容を明確に示すフレーズを使うようにしましょう。
例えば、「SEO対策の内部施策を詳しく見る」といった表現が効果的です。
また、記事の冒頭や末尾に関連ページを配置することで、ユーザーの回遊率も自然に高まります。
SEOで最も重要なのは、やはりコンテンツの質です。
検索順位を上げるには、小手先のテクニックよりも読者の疑問を解決することが大切です。
単なる情報の羅列ではなく、実体験やデータ、専門家の意見を交えて独自性を出しましょう。
比較表や図解、引用を加えると理解度と信頼性が高まります。
また、執筆者情報や参考元を明記すると、E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)の評価も向上します。
「役立つ情報をご自身の言葉で伝える」ことが、何よりも価値あるSEO対策です。
Googleはモバイルファーストインデックスを採用しています。
つまり、スマートフォンでの表示がSEO評価の基準になるということです。
文字サイズや行間、ボタンのタップしやすさを確認しましょう。
どの端末からでも快適に閲覧できることが理想です。
また、画像の圧縮やキャッシュ設定を行い、ページ速度を上げることも重要です。
レスポンシブデザインを採用すれば、端末に応じてレイアウトが自動で調整されます。
最後に、コンテンツを「公開して終わり」にしないことが大切です。
記事を作成したら、SNSや外部メディアで積極的に発信し、より多くの人に届けましょう。
X(旧Twitter)やInstagramなどで紹介することで、新しい読者層にリーチできるだけでなく、被リンクの獲得にもつながります。
被リンクは検索エンジンからの信頼を示す要素のひとつであり、SEO効果を高める重要な要因です。
また、SNSのシェアボタンを設置しておくと、ユーザー自身が自然に拡散してくれる可能性も高まります。
地道な発信の積み重ねが、検索順位の底上げにつながります。



ペン博士、SEOについてたくさん学べました!
キーワードの選び方から内部対策、E-E-A-TやCore Web Vitalsまで、意識するポイントがこんなにあるなんて驚きです!



うむ、その通りじゃ。SEOは「テクニック」ではなく、「ユーザーの信頼を積み上げる設計」なんじゃ。
正しい知識をもとに改善を続ければ、必ず結果はついてくる。焦らずコツコツ進めるのじゃ!



ありがとうございます!今回の学びを活かして、ユーザーにも検索エンジンにも愛されるWebサイトを作っていきます!
本記事では、SEO対策の基本や実践方法を詳しく解説しました。
SEO対策を効果的に行うためのポイントを以下に整理します。
・検索意図を理解する:ユーザーが何を知りたいのかを正確に読み取り、意図に沿った内容を提供する。
・構造を最適化する:タイトルやURL、内部リンクを整理し、検索エンジンと読者の両方に伝わりやすくする。
・信頼されるコンテンツを作る:経験・データ・専門性をもとに、E-E-A-Tを意識した情報を発信する。
・使いやすいサイトにする:Core Web Vitalsを基準に、読み込みの速さと操作のしやすさを最適化する。
・データを基に継続的に改善する:分析ツールを活用し、結果をもとに改善を繰り返して成長させる。
これらを意識することで、勘や思いつきではなくデータに基づくSEO運用が可能になります。
SEOは一度きりの作業ではなく、「改善 → 検証 → 成長」の循環を続けることが大切です。
小さな最適化を積み重ねて、検索エンジンにもユーザーにも信頼されるサイトに育てていきましょう。


副業・フリーランスが主流になっている今こそ、自らのスキルで稼げる人材を目指してみませんか?
未経験でも心配することありません。初級コースを受講される方の大多数はプログラミング未経験です。まずは無料カウンセリングで、悩みや不安をお聞かせください!
公式サイト より
今すぐ
無料カウンセリング
を予約!